

ぐるっとパス2023年。 第4日目。
・ぐるっとパス2023: [その3] 帆船日本丸/横浜みなと博物館、そごう美術館 さくらももこ展
・ぐるっとパス2023: [その2] 東京都庭園美術館、泉屋博古館東京、大倉集古館
・ぐるっとパス2023: [その1] 東洋文庫ミュージアム、六義園(りくぎえん)、旧古河庭園、旧岩崎邸庭園
■ 神代植物公園
春のバラフェスタ2023は昨日の記事にした。主にバラ以外の画像と昨日載せなかったバラ画像を。








神代植物公園からバスで調布駅へ。調布駅から京王線で八王子へ行った。
■ 八王子美術館

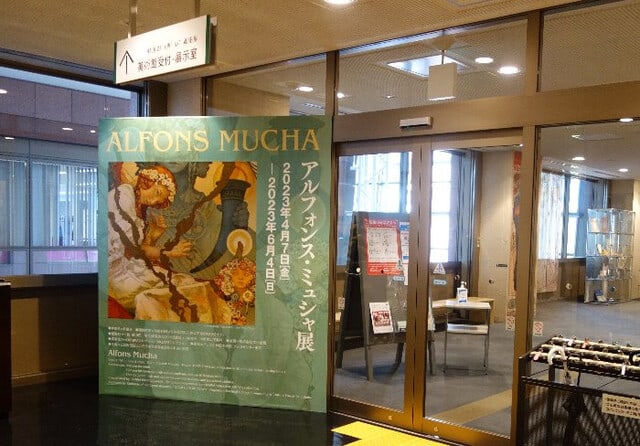
アルフォンス・ミュシャ、(1860年7月24日 - 1939年7月14日)は、チェコ出身でフランスなどで活躍したグラフィックデザイナー、イラストレーター、画家。
アール・ヌーヴォーを代表する画家で、多くのポスター、装飾パネル、カレンダー等を制作した。ミュシャの作品は星、宝石、花(植物)などの様々な概念を女性の姿を用いて表現するスタイルと、華麗な曲線を多用したデザインが特徴である。Wikipedia




▼ 汎スラブ主義
アメリカの富豪チャールズ・クレーン(英語版)から金銭的な援助を受けることに成功し、財政的な心配のなくなったミュシャは1910年、故国であるチェコに帰国し、20点の絵画から成る連作『スラヴ叙事詩』を制作する[5]。 。この一連の作品はスラヴ語派の諸言語を話す人々が古代は統一民族であったという近代の空想「汎スラヴ主義」を基にしたもので、この空想上の民族「スラヴ民族」の想像上の歴史を描いたものである。スメタナの連作交響詩『わが祖国』を聴いたことで、構想を抱いたといわれ、完成までおよそ20年を要している。(wikipedia)

▼ 『ロシア復興』

リトグラフ 1922年
チェコ時代
"聖母子"と"ピエタ"
「幼子イエスを抱く 聖母マリア」を思わせるポスターは 「ロシアは救われねばならない」 とラテン語で呼びかけています。
ロシアでは1917年の革命後も内戦の混乱が続き、戦時共産主義導入によって農業と工業が崩壊、燃料危機、食糧危機をもたらし、1920年の大凶作、さらに1921年から1922年には多数(100万~500万人)の餓死者が出るロシア飢饉に陥りました。
経済が破綻したロシア救援の活動が党派を超えて国際的に呼びかけられました。
抱かれている幼児は救援を待っている子どもたちであり、同時に4才の新生ロシア(ロシア・ソヴィエト共和国 後のソヴィエト社会主義共和国連邦(1922年12月30日成立))をあらわしています。
幼児が腕をだらりと下げているのは、眠っているのではなく 死んでいることをあらわす絵画表現(腕の状態によって眠りと死を描きわける西洋絵画の約束事)です。このポスターが「聖母子」だけでなく「ピエタ」 (十字架で死んだイエスの遺体を抱いて悲しむ聖母マリアの像) を思い起こさせるため、欧米キリスト教圏の人々に強く訴えかけます。(ミュシャの『ロシア復興』と同じく、幼子イエスが手をだらりと下げて"ピエタ"を思わせる"聖母子像"にはパルミジャニーノの『首の長い聖母』があります。)
誰にもわかるように
ミュシャは、どの国でも理解できるように「聖母子」と「悲しみの聖母」のダブル・イメージでポスターを描き、キリスト教世界共通の古典語ラテン語でロシア救済を訴えました。この呼びかけにこたえてアメリカが食料船を送ったのをはじめロシア農民救援の募金運動が世界各国で広がり、さらにロシアとドイツの国交が回復してイギリス、イタリア、中国(中華民国)、日本などがソビエト連邦を正式に承認するきっかけにもなりました。(web site) << ミュシャを楽しむために Web Site

▼
アルフォンス・ミュシャ展
19世紀末パリ、ベル・エポック(美しき時代)を彩り、アール・ヌーヴォーを牽引したアルフォンス・ミュシャ。1860年、民族意識の色濃いモラヴィア地方の村イヴァンチッツェ(現チェコ共和国)に生まれたミュシャは、27歳のときパトロンの援助を受けパリ留学を果たします。その後援助が終了すると、挿絵画家として細々と生計を立てていましたが、34歳のとき転機が訪れます。当時パリで名高い女優サラ・ベルナールの舞台「ジスモンダ」の宣伝用ポスターを手掛けたことで、一躍時代の寵児となったのです。貼ったそばから剥がされるほど反響を呼んだミュシャのポスターは、サラの心をも掴み6年間のポスター制作契約を結ぶに至ります。
サラとの仕事で名を馳せたミュシャのもとには、ポスターはもとより装飾パネル、カレンダー、商品パッケージなど様々なデザインの依頼が殺到します。とりわけ装飾パネルは、リトグラフで制作することで大量生産と安価での販売が可能になり、それまで富裕層の特権であった芸術を、一般市民にまで広める役割を果たしました。そして何より、優美な女性像と草花の有機的な曲線美を活かしたデザインは、「ミュシャ・スタイル」としてひとつのデザインのジャンルを確立し、ついにミュシャはアール・ヌーヴォーを代表する芸術家(ポスター画家、デザイナー)にまで昇りつめます。
1900年には第5回パリ万博において、ボスニア・ヘルツェゴビナ館の装飾および、オーストリア=ハンガリー帝国のためのポスター制作の依頼を受けます。特にボスニア・ヘルツェゴビナ館の装飾は、晩年の《スラヴ叙事詩》制作の足掛かりとなりました。ミュシャはこの後商業的な仕事からは距離を置き、後半生を祖国チェコとスラヴ民族に捧げることになります。
1906年以降アメリカに拠点を移したミュシャは、《スラヴ叙事詩》制作のための資金の目途が立つと、1910年チェコに帰国します。祖国に戻ったミュシャは《スラヴ叙事詩》制作と並行して、プラハ市民会館の壁面装飾のほか、1918年にチェコスロヴァキア共和国が独立すると、切手や紙幣など新国家に関連するあらゆるデザインを無報酬で引き受けました。こうした姿勢は、パリ時代に芸術を一般市民も親しめるものにしたいと尽力した姿と重なり、ミュシャが「民衆のための芸術」という信念を終生貫いたことを表しています。
本展では、パリ時代の華やかなポスター、装飾パネルをはじめ、画学生の手引きになるようにと制作された『装飾資料集』などを中心に、祖国発展のため手がけた切手や紙幣のデザイン、《スラヴ叙事詩》のパネルなどを通して、後半生を捧げた祖国チェコへの献身にも焦点を当てます。 (web site)









