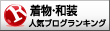展示品は織機、壁一面の先生が作られた織物の見本裂、設計図、完成品、著作と並んでいます。いずれも先生の仕事の片鱗を見ることができます。



しかし思うに宮坂先生の業績は岡谷のモノづくりの継続、発展を期待して作った「岡谷絹工房」にその集大成を見る事ができます。
展示会場を見に行った日には、自分で若しくはご友人が織ったと思われる帯や生地を使ったバックを持った方が大勢観覧にこられていました。おそらく岡谷絹工房に関連したみなさんなのでしょう。
岡谷に根付いた蚕糸、製織を続ける行動、あるいは指導に向かわれていた全国の織物産地に先生の遺伝子があるように思います。
当時岡谷では夏に「製糸夏季大学」という口座が開かれ、そこに参加する日に、少し早く岡谷に行って宮坂先生に教えを乞うのでした。
先生の自宅に隣接して工房があり、何度か覗かせていただきました。
織機等は今、各産地で使われているものに比べるとローテクなもので、動力は殆どついていません。
現在はシャトルのある織機ですら珍しくなり、複雑な綜絖の制御はコンピュータです。
いずれも宮坂先生が手で行っていたものをより早く作れるようにしたものなのです。残念ながら僕はそうした複雑な組織の織物を理解しませんが、組織というのはそう変わっていないのかもしれません。
宮坂教室について書くとお恥ずかしい事も含めて100年くらいかかるかもしれないので、また岡谷、諏訪を訪れた機会に。
つづく



しかし思うに宮坂先生の業績は岡谷のモノづくりの継続、発展を期待して作った「岡谷絹工房」にその集大成を見る事ができます。
展示会場を見に行った日には、自分で若しくはご友人が織ったと思われる帯や生地を使ったバックを持った方が大勢観覧にこられていました。おそらく岡谷絹工房に関連したみなさんなのでしょう。
岡谷に根付いた蚕糸、製織を続ける行動、あるいは指導に向かわれていた全国の織物産地に先生の遺伝子があるように思います。
当時岡谷では夏に「製糸夏季大学」という口座が開かれ、そこに参加する日に、少し早く岡谷に行って宮坂先生に教えを乞うのでした。
先生の自宅に隣接して工房があり、何度か覗かせていただきました。
織機等は今、各産地で使われているものに比べるとローテクなもので、動力は殆どついていません。
現在はシャトルのある織機ですら珍しくなり、複雑な綜絖の制御はコンピュータです。
いずれも宮坂先生が手で行っていたものをより早く作れるようにしたものなのです。残念ながら僕はそうした複雑な組織の織物を理解しませんが、組織というのはそう変わっていないのかもしれません。
宮坂教室について書くとお恥ずかしい事も含めて100年くらいかかるかもしれないので、また岡谷、諏訪を訪れた機会に。
つづく