

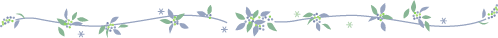
| 夫人の話す声は綺麗に澄んでいた。 あんまり近い故か、響いて抜け、 何を話すか分からなかった。 ただ澄み切った綺麗な声調が、 ソプラノの歌声のように思われた。 時々緑の耳へ遠い世界からの 夢の音楽の余韻のように響いて来た。 ―― いいえ ―― どう致しまして ―― こちらこそ ・・・・・ まあ、早く拝見したいのね ―― こちらは、相変わらず ・・・・・えゝ ・・・・・ ・・・・・ それから ・・・・・ まあ ・・・・・ それは日常誰でも使う言葉であったが、 しかしこの場合、夫人の唇を通して電話機の 前で響く時、みな立派な装飾音を振り蒔いて 綺麗に流れて行った。 何か、心憎い軽い小唄の節のように。 吉屋信子作 「地の果まで」 |
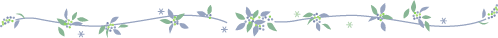

雨は上がったと思ったのですが・・。
今日は少々、荒れ模様の天気になっています。
気紛れに太陽は顔を出すのですが、パ~ッと雨も。
引き続き気温は高めです。庭の匂い菫も、その雨粒を受けてキラッ。
さて、吉屋信子作 「地の果まで」、読了。
ここまで女史の小説は一気に読んで来ましたが、今は一息入れています。
ところで、この小説は、女史の処女作なのだそうですね。
そしてあの 「氷点」 で有名な朝日新聞の懸賞小説、入選作なのだとか。
女史自身、その事について次のように触れています。


 それにしても、この作品が
それにしても、この作品が大正9年作と言うのですから
驚きます。
「地の果まで」 という、
タイトルからはどうしても、
最果ての地に逃避行と言ったような、
もの哀しい悲劇を連想しますが、
少々、意味合いが違うものに
なっています。
悲劇は悲劇なのですが、
その中でも明日があり、
希望の光が見えるような・・。
それは今日のブログタイトル、
及び引用文にもありますように、
文章の美しさにもあるのかも
知れません。
それにうっとりしているもの
ですからつい悲劇に鈍感に
なっているのかも・・
~なんて思ったりします。
「血は水よりも濃し」、
全編に姉弟愛を初め、
肉親愛に溢れていて。
それらが希薄になった現在と比べ
随分、新鮮に感じたものです。
でも、その中にいれば当然、息苦しさや反発も感じるのでしょうけれど。
今とは違う家長制度や立身出世主義なども垣間(かいま)見えますが、
やはりこれらもビシッと1本筋が通っているような、
凛としたものを感じます。
翻(ひるがえ)って現在。いいえ、我が身。
何と言う体(てい)たらく。いいえ、軟弱になってしまったのでしょう。
覚悟が違うのですね。貧しさも、ここでは 「清貧」 という言葉がぴったり。
ともあれ、この作品で日本人の原点を見たような気持ちです。









