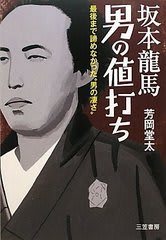『坂本龍馬・男の値打ち』(芳岡堂太著、三笠書房)を読む。
後輩に薦められて読んだ。基本的には龍馬の伝記だが、史実を追いながら、筆者の解説が主観的に述べられている。「器の大きさ・深さ」、「バカを演じられる性格」、「人望・他人への思い」みたいなところに龍馬の魅力が集約されるという。知らなかったこともけっこう書いてある。真偽のほどは分からないが、免許皆伝された「北辰一刀流」は実は剣ではなく、薙刀(なぎなた)だったかもしれない、という説など。
細かいところで、大河ドラマ「龍馬伝」でのシーンと本書で述べられている史実がつながるところも散見される。例えばドラマの中で龍馬が三味線を弾きながら歌っているシーンが何度か出てきたが、これは演者の福山雅治がミュージシャンなので、その片鱗を見せるための架空の設定だろうと思っていたら、実際に龍馬は三味線が得意だったと書いてある。
また本書では、「この場面では実際にこんな会話が交わされたのだろう」みたいな感じで、想像の台詞が挿入されている箇所がところどころある。龍馬:「~じゃき」とか、西郷「おいどんは~でごわす」みたいな。じゃっかん胡散臭い(^_^;)
後輩に薦められて読んだ。基本的には龍馬の伝記だが、史実を追いながら、筆者の解説が主観的に述べられている。「器の大きさ・深さ」、「バカを演じられる性格」、「人望・他人への思い」みたいなところに龍馬の魅力が集約されるという。知らなかったこともけっこう書いてある。真偽のほどは分からないが、免許皆伝された「北辰一刀流」は実は剣ではなく、薙刀(なぎなた)だったかもしれない、という説など。
細かいところで、大河ドラマ「龍馬伝」でのシーンと本書で述べられている史実がつながるところも散見される。例えばドラマの中で龍馬が三味線を弾きながら歌っているシーンが何度か出てきたが、これは演者の福山雅治がミュージシャンなので、その片鱗を見せるための架空の設定だろうと思っていたら、実際に龍馬は三味線が得意だったと書いてある。
また本書では、「この場面では実際にこんな会話が交わされたのだろう」みたいな感じで、想像の台詞が挿入されている箇所がところどころある。龍馬:「~じゃき」とか、西郷「おいどんは~でごわす」みたいな。じゃっかん胡散臭い(^_^;)