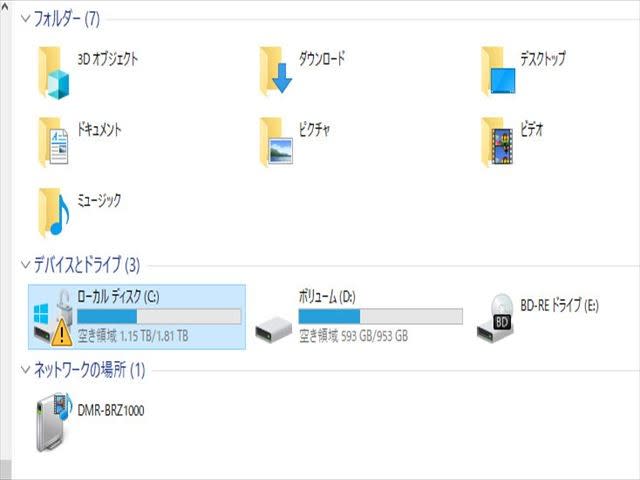藤井棋聖が木村王位を破って見事二冠に。地元の瀬戸でもくす玉が割れて祝福ムード、大曾根の行きつけのラーメン屋さんも盛り上がっているでしょうね。
テレビでは戦いの解説をやっていました。こっちは駒の動き方を知っている程度なので、盤面を見せて「これは本当に激しい戦いですねぇ」といわれても駒が激しく飛び跳ねているわけではないので実感としてはピンときません。将棋の解説をする人はプロのそれもかなりの高位の方がやっていますので、とても的確(な感じ)です。でもピンときません。AIで一億回読んでやっと最善手となるような妙手といわれるとなんとなく納得です。
でも将棋の解説を素人の人にやらせてみるというのも案外いけるのではないでしょうか、音楽評論みたいに。コンサート評やCD評を書いたり話したりする人はほとんどの場合演奏家ではありません。将棋界では将棋を指すプロ中のプロが解説するのに、音楽界では演奏できない人が演奏を評論します。ふしぎなことにその音楽評論はとてもわかりやすいのです、けどデタラメです。でもそのわかりやすい、というところが重要なのです。将棋界も音楽界(美術界もかな)に学んでみてはどうでしょうか、レベルが下がらないように注意する必要はありますが。
テレビでは戦いの解説をやっていました。こっちは駒の動き方を知っている程度なので、盤面を見せて「これは本当に激しい戦いですねぇ」といわれても駒が激しく飛び跳ねているわけではないので実感としてはピンときません。将棋の解説をする人はプロのそれもかなりの高位の方がやっていますので、とても的確(な感じ)です。でもピンときません。AIで一億回読んでやっと最善手となるような妙手といわれるとなんとなく納得です。
でも将棋の解説を素人の人にやらせてみるというのも案外いけるのではないでしょうか、音楽評論みたいに。コンサート評やCD評を書いたり話したりする人はほとんどの場合演奏家ではありません。将棋界では将棋を指すプロ中のプロが解説するのに、音楽界では演奏できない人が演奏を評論します。ふしぎなことにその音楽評論はとてもわかりやすいのです、けどデタラメです。でもそのわかりやすい、というところが重要なのです。将棋界も音楽界(美術界もかな)に学んでみてはどうでしょうか、レベルが下がらないように注意する必要はありますが。