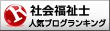『死の臨床』Vol.28 No.1 2005
遺族のリスク評価法の開発に向けて、遺族自身及び看護師によるリスク評価と、遺族の精神健康との関連を検討し、高リスク遺族を予測する因子を探索している。遺族自身、看護師に対し、郵送による質問紙調査を実施している。
引用
・遺族リスク評価法とは、死別体験を遺族自身だけでうまく乗り越えられず、第三者からの援助を必要とする可能性が高い、いわゆる高リスク遺族を予測することである。
・リスク評価は限られた資源の中でのサポートの配分に注目しており、低リスクと評価された遺族に対して、サポートを行わないということではない。
・遺族自身のリスク評価の結果から見出された、リスク評価因子⇒「過去の喪失をうまく乗り越えられていなかった」「不安が強かった」など


どんな状況にある人が、グリーフケアをより必要とするのか?この研究はこれを導き出す、根っこの根っこになっている研究であろう。今となっては「そうだろうね」とうなずける結論ではあるが、およそ7年前の論文発表時には、臨床家たちにとっては救いの研究であっただろう。
しかし逆に、7年経った今でもなお、グリーフケアは十分には行き届いていない。具体的な危険因子が提示されているにもかかわらず、現場では生かしきれていない…いや、情報へのアクセスがしにくいのかもしれない。
現場の人たちが使いやすいツール…札幌医科大の岩本先生たちが、開発を進めている。多くの選択肢、多くの引き出しが用意されるといい。
遺族のリスク評価法の開発に向けて、遺族自身及び看護師によるリスク評価と、遺族の精神健康との関連を検討し、高リスク遺族を予測する因子を探索している。遺族自身、看護師に対し、郵送による質問紙調査を実施している。
引用

・遺族リスク評価法とは、死別体験を遺族自身だけでうまく乗り越えられず、第三者からの援助を必要とする可能性が高い、いわゆる高リスク遺族を予測することである。
・リスク評価は限られた資源の中でのサポートの配分に注目しており、低リスクと評価された遺族に対して、サポートを行わないということではない。
・遺族自身のリスク評価の結果から見出された、リスク評価因子⇒「過去の喪失をうまく乗り越えられていなかった」「不安が強かった」など


どんな状況にある人が、グリーフケアをより必要とするのか?この研究はこれを導き出す、根っこの根っこになっている研究であろう。今となっては「そうだろうね」とうなずける結論ではあるが、およそ7年前の論文発表時には、臨床家たちにとっては救いの研究であっただろう。
しかし逆に、7年経った今でもなお、グリーフケアは十分には行き届いていない。具体的な危険因子が提示されているにもかかわらず、現場では生かしきれていない…いや、情報へのアクセスがしにくいのかもしれない。
現場の人たちが使いやすいツール…札幌医科大の岩本先生たちが、開発を進めている。多くの選択肢、多くの引き出しが用意されるといい。