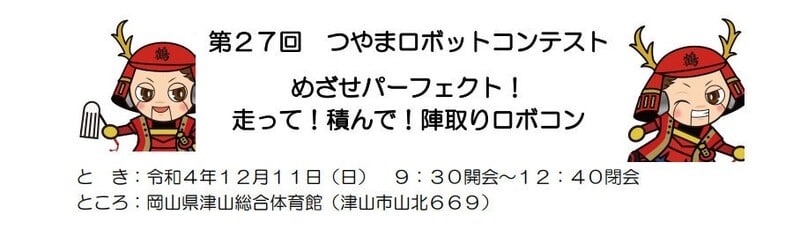令和4年12月10日
水田の畑地化重視
基本法検証 多面機能影響指摘も
農水省は9日、※1「食料・農業・農村基本法」の検証部会を開き、農産物の需要に応じた生産について議論した。
※1平成11年7月16日法律第106号)は、国土や環境の保護など、生産以外で農業や農村の持つ役割を高めること、
食料自給率を高めることなどを目的として、1999年に制定された法律である。
農水省は主食用米の需要量は、2040年度に20年度より3割少ない493万トンに落ち込むと試算。
水田が大幅に余るとして畑地化の必要性を強調した。
委員からは、水田の多面的機能への影響を注視する意見が出た。
食料・農業・農村政策審議会の基本法検証部会で議論した。
同省は、水田は減少ペースがこのまま続けば40年度に203万ヘクタールになると試算。
需要量が減るため、このうち主食用米を栽培しない面積は100万ヘクタールを超えると見込んだ。
本来稲作に使う水田は、増産が求められる麦・大豆などの生産に十分に利用されない可能性があるとして、畑地化が重要との考えを示した。
ニーズのある作物への転換を「政策として推進する必要があるのではないか」とも提起した。
日本生活協同組合連合会の二村睦子常務は「畑地になることで多面的機能がどう変化するのか」と、同省の認識をただした。
基本法は理念の一つに「農業の多面的機能の発揮」を掲げている。
同省は、食料安全保障強化へ必要な小麦などへの転換へ、余剰水田は「阻害要因」(大臣官房)との認識を示した。
「多面的機能をどうみるのかは非常に大きな政策的な課題」とし、年明け以降に本格議論するとした。
他の委員からは畑地化推進を巡り、必要性を指摘する意見の一方、他作物への転換は容易ではないとの声もあった。
JA全中の中家徹会長は小麦などへの転換は重要だとしつつ「改めて米の消費拡大の視点が重要」と訴えた。
現行基本法に沿って農産物を市場評価に委ねた結果、「再生産可能な価格になったのか検証する必要がある」とも強調した。
令和4年12月9日 農業
麦大豆でも畑地化整備支援
農水省は、水田を畑地化・汎用(はんよう)化する基盤整備事業の対象を広げる。
従来は野菜など高収益作物の生産農地のみが対象だったが、麦・大豆をはじめとする畑作物全般を対象とする。
海外依存度の高い小麦や大豆の増産を促すと同時に、需要減が進む主食用米から畑作物への転換を進める狙い。
2022年度第2次補正予算に盛り込んだ。