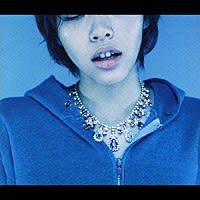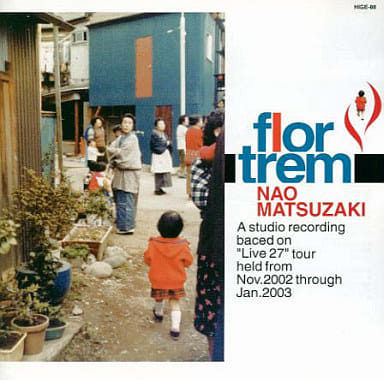■ 「消費税増税が異次元緩和の効果を相殺した」という主張は正しい ■
一部の「リフレ論者」が「消費税増税が異次元緩和の効果を相殺した」と主張していますが、私もこれは正しいと思います。但し、消費税増税の影響よりも「便乗値上げ」の影響の方が大きいかと。
牛丼 290円 → 380円
これは極端な例ですが、消費税は3%しか値上がりしていないのに、牛丼は30%も値上がりしています。スーパーの食材など、消費税増税に伴って便乗値上げされた商品は沢山あります。
何故便乗値上げされたかと言えば、円安で輸入コストが上昇していたから。本来ならばそのコストは商品の価格に上乗せされるはずでが、デフレ下で価格下落圧力が有る中では値上げは売れ行きを低下させるだけで、需要低下を招きます。
仕入コストを価格転嫁出来なかった各企業ですが、消費税増税時に商工会議者などは価格転嫁を指導していたとも噂されています。日銀の異次元緩和がインフレを達成する為には、標品の値上げが不可欠だからです。
結果的に、便乗値上げによって需要は低下し、日本経済は消費税増税以上のダメージを負ったと私は妄想しています。
■ 財政ファイナンス継続の為には2%のインフレ達成は阻止する必要が有る。 ■
財務省と日銀は異次元緩和によって「金融抑圧政策」という財政の延命作戦に突入しています。
金融抑圧= 低金利 + 適度なインフレの進行
第二次世界大戦後、アメリカは国債の上限金利をインフレ率よりも低く固定して、財政赤字を相対的に圧縮します。イギリスも同様に30年程を掛けて戦時国債の負担を軽減しました。これらを「金融抑圧政策」と呼び、財政赤字の軽減の一つの方法とされています。
「金融抑圧」の成立要件は、国債金利を低く固定したまま、インフレが進行する事で、まさに「異次元緩和」が目的としている事に見えなくもありません。しかし、現在の日本の潜在成長率はゼロ%近傍に張り付いていますから、「金融抑圧政策」は基本的に成立しません。
では、日銀の異次元緩和とは何かと問われれば「財政ファイナンス」に他なりません。日本は100兆円近い予算を組んでいますが、税収はせいぜい40兆~50兆円の間です。50兆円近くを国債で調達する必要が有りますが、それを支える国民の預金は、近い将来国債発行残高を上回ってしまいます。こうなると、国内で日本国債を安定的に消化する事が出来ななくなり、国債金利が上昇し始め財政の継続性に赤信号が灯ります。
こうなる前、国債市場を利用した間接的な財政ファイナンスで、日銀が国債を購入出来る様にしたのが「異次元緩和」の目的です。
異次元緩和は2%のインフレ率を達成すると国債買い入れを減らすテーパリングに着手する必要が有ります。しかし、新発国債の90%に相当する額を日銀が購入している状況で、日銀がテーパリングに踏み切れば、国債金利はポンと跳ね上がってしまい、低利の国債を大量に保有する金融機関や生保などはパニックに陥ります。
そもそも、現在の日本の財政は税収で支える事が出来ないので、異次元緩和という事実上の財政ファイナンス政策に突入した今の日本で、日銀のテーパリングは既に不可能となっています。
■ 消費税増税で景気に冷や水を浴びせる事で景気回復を阻害する財務省 ■
政府は実質2%(名目3%)の成長率で財政赤字を将来的に解消できるとしています。アベノミクス第二弾のGDP600兆円の目標も、この経済成長率を基本としています。
しかし、実際には実質成長率はゼロ近傍に張り付いていて、この目標を達成できそうにありません。その原因は消費税と便乗値上げに求められます。(当然、少子高齢化が最大の要因ですが)
日銀が資金供給を拡大する異次元緩和で、短期的に2%の成長を達成する事は多分可能でしょう。円安による輸入物価の上昇もそれに貢献します。しかし、異次元緩和を止めてしまえば円高に振れるので、すぐにインフレ率の上昇は下降に転じます。
景気が下降して税収が下がる中で、日銀の国債買い入れが減少すれば日本の財政が危機的状況に陥ります。
ですから、財務省は消費税増税で景気に適度に冷や水を浴びせて、2%の物価目標の達成を防いでいると私は妄想しています。消費税10%増税という予定も、景気回復の足を引っ張ります。
■ 既に景気回復に耐えられない日本の財政 ■
日本の成長力が安定して実質2%を達成するならば、財務省が表向き目指す財政再建は可能っでしょう。しかし、少子高齢化の状況でそれは無理です。結局、日本は異次元緩和という財政ファイナンスを止める事が出来ません。
これを言い方を変えれば、「日本の財政が景気回復に耐えられない」となります。この場合の景気回復とは短期的な2%の成長です。(継続的なら問題有りませんが・・・)
では、異次元緩和が10年も20年も継続可能かと言えば、それでは誰がどう見ても「財政ファイナンス」となってしまい、為替市場で円が暴落します。
・・・・そう考えると、今後5年以内に「ウヤムヤになる法則」が発動するのではないかと妄想が膨らみます。「ウヤムヤになる法則」とは、世界的な金融危機の勃発と、それに伴う軍事的緊張の高まりで、世界の国々が「戦時経済に突入する」という「歴史的な法則」です。
リフレ政策という「異常な金融政策」の結果はドルもユーロも含めて「通貨の信用喪失」で終わると思われますが、そうなると国債市場も暴落を演じますから、「ウヤムヤになる法則」を発動せざるを得なくなります。
もしこのシナリオが現実化するならば、財務省も日銀も、異次元緩和の継続性や、日本の財政の継続性を本気で考える必要が無くなります。時間稼ぎで良いのですから・・・。
まあ、クレージーな妄想ですが、陰謀論ですから笑い飛ばしていただけたら・・・。