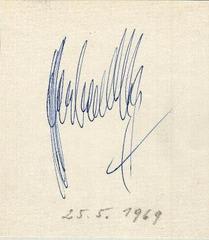○ギーレン指揮南西ドイツ放送交響楽団、ジョンソン(B)、オーサニック(SP)(ARTE NOVA/BMG他)1994・CD
マーラーよりはずっと客観的で単純な思考にもとづく曲で、大地の歌を参照したのは言うまでもなかろうが内容的には抽象度が高い。天国的な楽観性が支配的で、此岸のリアルな苦難と救済は全くあらわれない。だから熱狂的にのめりこむ要素というのは余りなく近代好きに今ひとつ人気がないのもわかる(現代好きには人気がある)。シェーンベルクの師匠というか少し年長の友人、シェーンベルクが時期的にブラームスからウェーベルンを包蔵した広大でやや生臭さも残る世界観を持ったとすれば、ツェムリンスキーは初期リヒャルトやマーラーの狭い世界の中で書法の純化をすすめていこうとしていた感もある。この作品に一貫する響きの透明性と音響的な怜悧さはギーレンの手によって更にその印象を強くさせるように仕上がっている。ブラスの盛大な響きでロマンティックに盛り上げることはせず(「春に酔えるもの」のような表現は無いと言うことだ)計算された管弦楽配置によって効果的に聞かせようとする方法論は現代指揮者向きである。生臭い音楽が嫌いな人にマーラー的なものを聞かせたいとき、唯一旋律にマーラーの影響の強いものが伺えるこの曲はうってつけだろう。このオケらしい清潔さがまた余りにすんなり曲に受け容れられているため、どこで終わったのかわからないくらい自然に終わってしまうようなところもあり、歌唱自体もこれはデジタル録音のためか余りに綺麗に捉えられすぎてライヴ的感興を多少残すことすらもしないため、大地の歌の延長戦を要望していた向きにはやや物足りなさを感じさせるかもしれないが、魅力的な旋律だけは評価してほしい。タゴール詩の世界との違和感は唐詩とベトゲ訳とマーラーの間の乖離に似て非なる、といったところか。マーラーはとにかく主観の存在が強い。目下薦められる演奏の上位にあることは確かだが、非常に純化され綺麗ではあるものの、交響曲としてのまとまりの演出と、押しの強さが無いのが難点か。○。
マーラーよりはずっと客観的で単純な思考にもとづく曲で、大地の歌を参照したのは言うまでもなかろうが内容的には抽象度が高い。天国的な楽観性が支配的で、此岸のリアルな苦難と救済は全くあらわれない。だから熱狂的にのめりこむ要素というのは余りなく近代好きに今ひとつ人気がないのもわかる(現代好きには人気がある)。シェーンベルクの師匠というか少し年長の友人、シェーンベルクが時期的にブラームスからウェーベルンを包蔵した広大でやや生臭さも残る世界観を持ったとすれば、ツェムリンスキーは初期リヒャルトやマーラーの狭い世界の中で書法の純化をすすめていこうとしていた感もある。この作品に一貫する響きの透明性と音響的な怜悧さはギーレンの手によって更にその印象を強くさせるように仕上がっている。ブラスの盛大な響きでロマンティックに盛り上げることはせず(「春に酔えるもの」のような表現は無いと言うことだ)計算された管弦楽配置によって効果的に聞かせようとする方法論は現代指揮者向きである。生臭い音楽が嫌いな人にマーラー的なものを聞かせたいとき、唯一旋律にマーラーの影響の強いものが伺えるこの曲はうってつけだろう。このオケらしい清潔さがまた余りにすんなり曲に受け容れられているため、どこで終わったのかわからないくらい自然に終わってしまうようなところもあり、歌唱自体もこれはデジタル録音のためか余りに綺麗に捉えられすぎてライヴ的感興を多少残すことすらもしないため、大地の歌の延長戦を要望していた向きにはやや物足りなさを感じさせるかもしれないが、魅力的な旋律だけは評価してほしい。タゴール詩の世界との違和感は唐詩とベトゲ訳とマーラーの間の乖離に似て非なる、といったところか。マーラーはとにかく主観の存在が強い。目下薦められる演奏の上位にあることは確かだが、非常に純化され綺麗ではあるものの、交響曲としてのまとまりの演出と、押しの強さが無いのが難点か。○。