源実朝の和歌の漢詩への翻訳に挑戦しています。今回の歌は、獣を主題とする珍しい歌です。解りやすい歌ですが、繊細ながら、想いを独特の居丈高い調子で強く訴える、実朝の特徴がよく表れた歌と言えるでしょうか。
“すらだにも”と、強めの助詞を二つ重ねたり、また“あわれなるかなや”と字余りの表現にして想いを強く訴えています。それに呼応して、漢詩でも、杜甫・「貧交行」の表現を借りて字余りの句となし、強く訴えるよう試みてみました。
ooooooooooo
(詞書) 慈悲の心を
物いわぬ 四方(ヨモ)の獣(ケダモノ) すらだにも
あわれなるかなや 親の子を思ふ (源実朝 金槐和歌集・雑・607)
(大意) 話すことができない、何処にでもいる、どんな獣でさえも、親は子を大切に
思っているのだ。何とも胸に響くことだなあ。
xxxxxxxxxxx
<漢詩>
母慈子心 子を慈しむ母(オヤ)の心 [上声六語韻]
四方獣類呀, 四方(ヨモ)の獣類(ジュウルイ)呀(ヤ),
根本無話語。 根本 話語(ワゴ)無し。
甚至它類也, 甚至(ハナハダシキハ) 它(カ)の類(タグイ)也(サエ),
一何深情緒。 一(イツ)に何ぞ深き情緒(ジョウショ)ならん。
君不見母慈子,君見ずや 母(オヤ)の子を慈しむを,
令人促省処。 人を令(シ)て省(セイ)を促す処(トコロ)にやあらん。
註] 〇四方:(東西南北)四方の; 〇呀:肯定、催促、賛嘆の語気を表す助詞“啊”の
音便変化した語; 〇話語:言葉、話; 〇甚至……也:接続詞、…でさえ…;
〇情緒:心の動き、感情; 〇省:自省する。
<現代語訳>
子を思う親心
身の廻りのどこにでもいる獣を見てごらん、
元々話すことなどできないのだ。
その獣類でさえ、
何と深くしみじみと心に響くことをしていることか。
君も見たことがあろう 親獣が子獣を慈しんでいる情景を、
人をして自省を促さずにはおかない。
<簡体字およびピンイン>
母慈子心 Mǔ cí zǐ xīn
四方兽类呀, Sì fāng shòu lèi ya,
根本无话语。 gēn běn wú huà yǔ.
甚至它类也, Shèn zhì tā lèi yě,
一何深情绪。 yī hé shēn qíng xù.
君不见母慈子,Jūn bù jiàn mǔ cí zǐ,
令人促省处。 lìng rén cù xǐng chù.
xxxxxxxxxxx
本ブログ上、これまでに読んできた実朝の幾首かの歌では、実朝が“思い”を庶民に向けている事に触れました。上掲の歌では、「人」一般に目を向けているように読めます。但し、「獣さえ……ですよ」、と問題提起に終わっていますが、漢詩では一歩踏み込みました。
実朝は十二歳(1203)の頃から『法華経』を習い、十三歳の頃には宗教行事に参加し始め、『天台止観(シカン)』の談義を聴講し始めたという。上掲の歌は、天台の教えが説く、“慈悲とは父母の心をいう”とする教えを素直に心に留め、歌にしたものでしょう。
なお、1214年(24歳)には、鎌倉に新御堂と呼ばれる大慈寺を建立している。同年7月27日には、京都より招いた禅僧・栄西(1141~1215)が導師を務めた大供養が行われた(『吾妻鑑』)。現在は、その跡として、民家と路地の狭間に石碑が残っている と。
歌人・源実朝の誕生 (3)
先に実朝の学問の師として源仲章、また和歌の師として源光行が公式に当てられていたことに触れました。以下、『吾妻鑑』を参照しつゝ、時を追って、歌人・実朝として成長していく様をみます。
1205(元久二)年(14歳)、9月2日には、実朝の元に『新古今和歌集』が届けられている。京都では後鳥羽上皇を中心に、当年は『古今和歌集』の成立(905)後300年の節目に当たることから、その編纂が急ピッチで進められていたものである。なお、届けられた『新古今和歌集』は、完成を祝う“竟宴”もまだ済まず、未公開の出来立てホヤホヤのものであった。
同集には、父・頼朝の歌2首が撰されていることを、実朝はすでに知っており、待ち望んでいた筈です。入手後はむさぼり読み、それを参考に作歌が始められたのではないでしょうか。『吾妻鑑』(1205.04.12)には、《12首 歌を詠む》との記載があります。但し、それらの歌は今日知られていない。
翌年、2月4日大雪の日、鶴岡八幡宮の祭礼を通常通り行っている。その夜、雪を見るため名越山の辺りに出ていて、北条義時の山荘(北条時政の名越邸か?)で和歌の会を催している。この頃から、実朝は本格的に歌を詠み始めたとされています。
1208(承元二)年、御台所(実朝奥方)の侍・兵衛尉清綱が京都から下り実朝の御所に参上、『古今和歌集』を献上した。 これは先祖から伝わった重宝であったとのことで大変実朝を喜ばせた。この頃から歌会で多く読まれ、歌会を想定しながら作歌を進めていきます。
1209(承元三)年(18歳)、実朝が二十首の和歌を“和歌の神”を祀る住吉大社に奉納した。使者は、藤原定家の門弟で実朝の近臣・内藤知親、このついでに去る建永元年(1206)に習い始めてから詠んだ和歌三十首を選び、評価を受けるために定家に届けさせている。
鎌倉では、実朝の主催に拠るばかりでなく、その他の歌会も頻繁に実施されていたようで、実朝が歌題を用意する機会も度々あったようである。のちに纏められた家集・『金槐和歌集』をみれば、同じ主題で種々表現を変えた複数の歌が続けざまに現れます。
以上、実朝が歌を詠み始めてのち、ある程度の数の歌が出来、定家に提示するまでを年を追って見てきました。実朝の歌の習得、つまり腕を磨く道場は、鎌倉でも頻繁に催されていた歌会の場であったと言えそうです。



















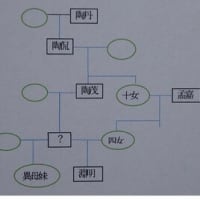






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます