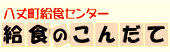みなさま、こんにちは!海風おねいさんです。
今日は十五夜ですね。あいにく曇り空の八丈島です。
今日は午後から全国的に晴れの予報が多いのですが、
八丈島は雨が降ったりやんだりしています。
月月に月見る月は多けれど 月見る月はこの月の月
有名な歌です。きれいなお月見したいですね。
 月見
月見  クリック
クリック
みなさまのお宅では、お月見はどのようになさいますか?
わたしが子どもの頃には、八丈島ではお月見は盛んに行われていた覚えがあります。
縁側を開けて、そこにすすきとお団子やおはぎをお供えします。
もちろん季節の収穫物も供えるのです。
八丈島では、必ずおいしい島の里芋を供えます。
(正式には3方に供えるらしいですが)
わが家では、生の里芋だけでなく、きぬかつぎにしたものや
きしょげた里芋を煮付けにしたものも供えました。
他にも秋の果物をいろいろとお供えしました。
そして、一寸変わった風習として、昔は暗黙の了解で、
子どもたちがこれを盗って行ってもいいことになってましたね。
縁側のガラス戸を開いておいしいご馳走をたくさん並べておきますと、
近所の子どもたちがこれを盗りに来ます。(ハロウィンみたいですね)
家の人は、気づかぬフリをして、ご馳走を持って行かせます。
お皿は元通りに戻してあります。ご馳走は、からっぽです。
「ご馳走様!」と闇の中から、元気な笑い声が聞こえます。
わが家も例年、こんなかんじでした。
調べてみましたら、こちらのサイトにこの風習について詳しく書かれてありました。
 十五夜の民俗
十五夜の民俗  クリック
クリック
●十五夜の貰い歩きと盗み
十五夜の供えものを、子どもたちが貰い歩くという伝承が各地にあります。
早いところでは大正時代に途絶えたようですが、
昭和の大戦後も細々と行われていた地域があります。
その内容も、家の人に見つからないように盗む場合もあれば、
家の人が黙認するかたちで持って行く場合、
さらには家の人に許可を得てから持って行く場合など、
地域によりさまざまなパターンがみられます。
いずれにしても、このような習俗が地域の子どもたちによって
支えられていたことは、ほぼ共通した要素となっています。
十五夜に供えものを貰い歩くことは、
社会的にもその地域で半ば公認された行為であっただけに、
子どもたちにとっては待ち遠しい行事の一つとされていました。
そこには、ごちそうをたくさん食べたいという願望と、
いかにうまく供えものを盗むことができるかという
遊び感覚の楽しさがあったといわれます。
また、盗まれる(あるいはさげてもらう)側では、
供えものを失うことが翌年の豊作につながるという期待感を
もつことができたのではないかと考えられます。
(以上、同サイトより引用)
※現在も八丈島にこの風習が残っているかは、知りません。
最近では、こんなのどかな話はあまり聞きませんので、
これを読んで盗りに行くのは、やめといてくださいね。
わたしも現在は縁側のない家に住んでますので、
お供えをするのは、2階の窓辺です。
眺めるのも食べるのもわが家の者だけです。
今年は忙しくて、まだお供えしておりません。夕方に少しだけお飾りします。
ちょっと寂しい感じがしますね。
わたしがもしも縁側のある家に暮らしていたら、
いまでもこの風習を続けたい気がします。
だけど、待ちぼうけになりそうですね。
いまの子どもで、この風習を知ってる子はいないでしょう。
このブログをご覧の方々に、盗りに行ったことのあるかた、いらっしゃいますか?
これは八丈島では男の子の遊びでした。
女の子は行きませんでした。わたしも行ったことがありません。
さて、連休明けの特売チラシは、(水)(木)のチラシとなります。
掲載は明日になりますので、よろしくお願いいたします。
今日は十五夜ですね。あいにく曇り空の八丈島です。

今日は午後から全国的に晴れの予報が多いのですが、
八丈島は雨が降ったりやんだりしています。

月月に月見る月は多けれど 月見る月はこの月の月
有名な歌です。きれいなお月見したいですね。

 月見
月見  クリック
クリック
みなさまのお宅では、お月見はどのようになさいますか?
わたしが子どもの頃には、八丈島ではお月見は盛んに行われていた覚えがあります。
縁側を開けて、そこにすすきとお団子やおはぎをお供えします。
もちろん季節の収穫物も供えるのです。
八丈島では、必ずおいしい島の里芋を供えます。
(正式には3方に供えるらしいですが)
わが家では、生の里芋だけでなく、きぬかつぎにしたものや
きしょげた里芋を煮付けにしたものも供えました。
他にも秋の果物をいろいろとお供えしました。
そして、一寸変わった風習として、昔は暗黙の了解で、
子どもたちがこれを盗って行ってもいいことになってましたね。
縁側のガラス戸を開いておいしいご馳走をたくさん並べておきますと、
近所の子どもたちがこれを盗りに来ます。(ハロウィンみたいですね)
家の人は、気づかぬフリをして、ご馳走を持って行かせます。
お皿は元通りに戻してあります。ご馳走は、からっぽです。
「ご馳走様!」と闇の中から、元気な笑い声が聞こえます。

わが家も例年、こんなかんじでした。
調べてみましたら、こちらのサイトにこの風習について詳しく書かれてありました。
 十五夜の民俗
十五夜の民俗  クリック
クリック
●十五夜の貰い歩きと盗み
十五夜の供えものを、子どもたちが貰い歩くという伝承が各地にあります。
早いところでは大正時代に途絶えたようですが、
昭和の大戦後も細々と行われていた地域があります。
その内容も、家の人に見つからないように盗む場合もあれば、
家の人が黙認するかたちで持って行く場合、
さらには家の人に許可を得てから持って行く場合など、
地域によりさまざまなパターンがみられます。
いずれにしても、このような習俗が地域の子どもたちによって
支えられていたことは、ほぼ共通した要素となっています。
十五夜に供えものを貰い歩くことは、
社会的にもその地域で半ば公認された行為であっただけに、
子どもたちにとっては待ち遠しい行事の一つとされていました。
そこには、ごちそうをたくさん食べたいという願望と、
いかにうまく供えものを盗むことができるかという
遊び感覚の楽しさがあったといわれます。
また、盗まれる(あるいはさげてもらう)側では、
供えものを失うことが翌年の豊作につながるという期待感を
もつことができたのではないかと考えられます。
(以上、同サイトより引用)
※現在も八丈島にこの風習が残っているかは、知りません。
最近では、こんなのどかな話はあまり聞きませんので、
これを読んで盗りに行くのは、やめといてくださいね。

わたしも現在は縁側のない家に住んでますので、
お供えをするのは、2階の窓辺です。
眺めるのも食べるのもわが家の者だけです。
今年は忙しくて、まだお供えしておりません。夕方に少しだけお飾りします。
ちょっと寂しい感じがしますね。
わたしがもしも縁側のある家に暮らしていたら、
いまでもこの風習を続けたい気がします。
だけど、待ちぼうけになりそうですね。
いまの子どもで、この風習を知ってる子はいないでしょう。
このブログをご覧の方々に、盗りに行ったことのあるかた、いらっしゃいますか?
これは八丈島では男の子の遊びでした。
女の子は行きませんでした。わたしも行ったことがありません。
さて、連休明けの特売チラシは、(水)(木)のチラシとなります。
掲載は明日になりますので、よろしくお願いいたします。