暗い夜道を照らす照明。
一般に街灯とか街路灯とか呼んでしまうかと思うが、住宅地の生活道路などに設置されている、小型のものは「防犯灯」が正式な名称。
自治体によって差はあるが、市町村や町内会が設置・管理を行うようだ。
秋田市内には約2万8500の防犯灯があるそうだ。
秋田市では、町内会の要望に応じて市が設置(年度ごとに数に限りあり)し、それを各町内会が管理して電気代を支払い、市から町内会へ助成があるという仕組みだったはず。
今年度、秋田市ではそのすべての防犯灯を白色LEDタイプに更新する事業を行なっている。
一斉に低消費電力のLEDに更新すれば、電気代(=町内会への助成)が大きく削減でき、総合的にコストダウンになるし、環境にやさしいということらしい。
※市の資料などでは特に触れていないが、古い照明を一掃することにより、水銀などの有害物質や割れやすいガラスをなくしたり減らしたりできる効果もあるだろう。
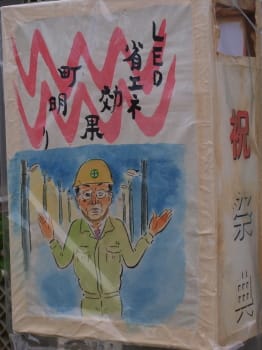 (再掲)勝平神社の風刺絵灯籠にも登場
(再掲)勝平神社の風刺絵灯籠にも登場
従来の秋田市内の防犯灯は、水銀灯(HID)や蛍光灯が多かったはず。
 ナショナルブランドのHID防犯灯。笠が錆びている
ナショナルブランドのHID防犯灯。笠が錆びている
LEDは、数年前に大町の秋田ニューシティ西側の茶町通りにおいて、たしか町内会独自で青色LEDの防犯灯が設置されたくらいかと思う。(今はどうなってるんだろう? ちなみに、防犯効果があると言われてもてはやされた青色照明だが、現在はその効果を疑問視する声も多く、下火になっているそうだ)
今年度に入ると、あちこちで集中的に防犯灯の更新作業が見られた。
気がつけば、(雄和・河辺地区は分からないので、それ以外の)市内の街路灯のほとんどがLEDになってしまっていた。交換作業は9月末までに終了する約束になっているようだ。
意識して見ると、袋小路や砂利道のような、住民以外ほとんど人が通らない道にも街路灯は設置されており、我々の生活に欠かせないものだったことを認識させられた。そしてそのほとんどがLED化された。
LED化された場所では、従来よりも明るくなった、広範囲が照らされるようになったと感じる人が多いようで、好評。(記事冒頭の夜道はすべてLED化済み)
ただし、LEDの特性としては、むしろ狭い範囲の照射のほうが得意なはず。従来のものが汚れたり老朽化したりして、充分に性能を発揮できていなかったという原因があるかもしれない。
 灯具自体もコンパクトになった。真下から見るとまぶしい
灯具自体もコンパクトになった。真下から見るとまぶしい
新しい防犯灯は、すべて同じ製品。
おそらく、パナソニックの「NNY20432LE1」という、消費電力8.4ワット、税込希望小売価格17850円の製品かと思われる。
 黄色いシールに管理番号と思われる数字が記載されている【番号については末尾の追記参照】
黄色いシールに管理番号と思われる数字が記載されている【番号については末尾の追記参照】
※ちなみに仲小路商店街の照明もパナソニック製
ところで、上の写真の防犯灯が取り付けられている柱には、ヒビが入っている。
この柱、今では珍しくなった、
 木の電信柱なのです!
木の電信柱なのです!
正確には電信柱ではなく、防犯灯を設置するためだけに立っている柱(照明柱)。
僕が子どもの頃でさえ、木の電柱はほとんどなかったが、未だに秋田市内にいくつかは残っているのだ。
秋田市内の別々のエリアをちらりと見ただけでも、計5本以上発見できた。
柱が腐っているとか危険なようにも見えないし、防犯灯を付けるだけなら充分に役目を果たせそう。これはこれでエコだ。
それにしても、昭和(中期以前?)を連想させるような木の電柱に、21世紀のアイテムである白色LED照明が取り付けられるとは、なんとも不思議な光景。

 これはまた別の木柱
これはまた別の木柱
「クレオソート」というコールタール系のものを塗って防腐加工された、味のある柱。
 頼もしい木柱とLED防犯灯
頼もしい木柱とLED防犯灯
秋田市の既存の防犯灯は、電力や電話の柱に間借りすることも多いが、道路に面した私有地に専用の柱を立てたり学校のグラウンドのネットの柱に設置されているものもある。
ただし、現在、秋田市で防犯灯を新設する際には「防犯灯を取り付けることができる電柱(木柱を除く)があること」が条件となっているようだ。(広報あきた2011年5月20日号)
じゃあ、秋田市内でLEDでない防犯灯は皆無になったのかといえば、そうでもない。
更新作業が終わった町内・地域にあっても、以前のものがそのままのところも、たまにある。(駐車場やマンションなど私有地内や管轄が違う公園や学校敷地内などに設置されている“防犯灯もどき”は、当然更新対象外)
 LED(手前)と既存のHIDが並ぶ
LED(手前)と既存のHIDが並ぶ
理由はよく分からないが、路上にあるのにLED化されなかったものは、市の助成を受けずに、町内会が自腹で購入・設置した防犯灯ということなのだろうか。
 昼行灯の状態で残るHID
昼行灯の状態で残るHID
防犯灯の電気代って定額なんだっけ? とすれば直接的な損失はないが、節電が求められるご時世だし、電球や灯具の寿命を早めることにはなる。
見た限りでは、残っている古い防犯灯は、水銀灯か蛍光灯ばかりだった。
昔ながらの白熱電球の防犯灯は…
 これ?
これ?
秋田市中心部のとある町内で、ボロボロのものを発見。おそらく電球だと思う。
複数個あったが、どれも配線が切られており、中には電球が外された状態のものもあり、使われていないようだ。
【10月15日追記】10月12日付けで、秋田市市民生活部生活総務課のホームページが更新され、LED防犯灯の不具合発生時の連絡方法が掲載された。(http://www.city.akita.akita.jp/city/copr/ctcm_new/light.htm)
「市と契約した事業者(ESCO事業者)が、平成34年9月30日までの10年間、自動点滅器の不良や不点灯などの故障、灯具が落下しそうであるなどといった不具合が発生した場合の対応を行います。」
契約先の「秋田電気工事協同組合」へ電話またはファクス(いずれも市外局番018の一般電話)で、不具合の内容と防犯灯に貼られている「7桁の番号」を伝えるようにとのこと。
連絡先が一元化されたのはいいことだと思うが、できればメールでも連絡できるようにしてほしい。メールなら通話料がかからないのだから。(善意で伝える人に10円とはいえ負担させるべきではないと僕は思う)
「7桁の番号」は灯具に貼ってある黄色いシールのことで、「灯具管理番号」と呼ぶそうだ。前4ケタが「町内会コード」で、後ろ3ケタが「灯具番号」。
※2020年度には、秋田県道の照明で類似の手法が導入。
一般に街灯とか街路灯とか呼んでしまうかと思うが、住宅地の生活道路などに設置されている、小型のものは「防犯灯」が正式な名称。
自治体によって差はあるが、市町村や町内会が設置・管理を行うようだ。
秋田市内には約2万8500の防犯灯があるそうだ。
秋田市では、町内会の要望に応じて市が設置(年度ごとに数に限りあり)し、それを各町内会が管理して電気代を支払い、市から町内会へ助成があるという仕組みだったはず。
今年度、秋田市ではそのすべての防犯灯を白色LEDタイプに更新する事業を行なっている。
一斉に低消費電力のLEDに更新すれば、電気代(=町内会への助成)が大きく削減でき、総合的にコストダウンになるし、環境にやさしいということらしい。
※市の資料などでは特に触れていないが、古い照明を一掃することにより、水銀などの有害物質や割れやすいガラスをなくしたり減らしたりできる効果もあるだろう。
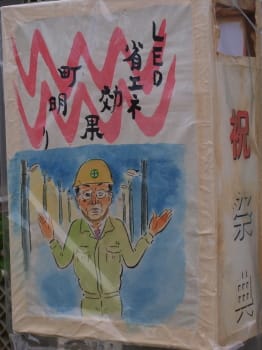 (再掲)勝平神社の風刺絵灯籠にも登場
(再掲)勝平神社の風刺絵灯籠にも登場従来の秋田市内の防犯灯は、水銀灯(HID)や蛍光灯が多かったはず。
 ナショナルブランドのHID防犯灯。笠が錆びている
ナショナルブランドのHID防犯灯。笠が錆びているLEDは、数年前に大町の秋田ニューシティ西側の茶町通りにおいて、たしか町内会独自で青色LEDの防犯灯が設置されたくらいかと思う。(今はどうなってるんだろう? ちなみに、防犯効果があると言われてもてはやされた青色照明だが、現在はその効果を疑問視する声も多く、下火になっているそうだ)
今年度に入ると、あちこちで集中的に防犯灯の更新作業が見られた。
気がつけば、(雄和・河辺地区は分からないので、それ以外の)市内の街路灯のほとんどがLEDになってしまっていた。交換作業は9月末までに終了する約束になっているようだ。
意識して見ると、袋小路や砂利道のような、住民以外ほとんど人が通らない道にも街路灯は設置されており、我々の生活に欠かせないものだったことを認識させられた。そしてそのほとんどがLED化された。
LED化された場所では、従来よりも明るくなった、広範囲が照らされるようになったと感じる人が多いようで、好評。(記事冒頭の夜道はすべてLED化済み)
ただし、LEDの特性としては、むしろ狭い範囲の照射のほうが得意なはず。従来のものが汚れたり老朽化したりして、充分に性能を発揮できていなかったという原因があるかもしれない。
 灯具自体もコンパクトになった。真下から見るとまぶしい
灯具自体もコンパクトになった。真下から見るとまぶしい新しい防犯灯は、すべて同じ製品。
おそらく、パナソニックの「NNY20432LE1」という、消費電力8.4ワット、税込希望小売価格17850円の製品かと思われる。
 黄色いシールに管理番号と思われる数字が記載されている【番号については末尾の追記参照】
黄色いシールに管理番号と思われる数字が記載されている【番号については末尾の追記参照】※ちなみに仲小路商店街の照明もパナソニック製
ところで、上の写真の防犯灯が取り付けられている柱には、ヒビが入っている。
この柱、今では珍しくなった、
 木の電信柱なのです!
木の電信柱なのです!正確には電信柱ではなく、防犯灯を設置するためだけに立っている柱(照明柱)。
僕が子どもの頃でさえ、木の電柱はほとんどなかったが、未だに秋田市内にいくつかは残っているのだ。
秋田市内の別々のエリアをちらりと見ただけでも、計5本以上発見できた。
柱が腐っているとか危険なようにも見えないし、防犯灯を付けるだけなら充分に役目を果たせそう。これはこれでエコだ。
それにしても、昭和(中期以前?)を連想させるような木の電柱に、21世紀のアイテムである白色LED照明が取り付けられるとは、なんとも不思議な光景。

 これはまた別の木柱
これはまた別の木柱「クレオソート」というコールタール系のものを塗って防腐加工された、味のある柱。
 頼もしい木柱とLED防犯灯
頼もしい木柱とLED防犯灯秋田市の既存の防犯灯は、電力や電話の柱に間借りすることも多いが、道路に面した私有地に専用の柱を立てたり学校のグラウンドのネットの柱に設置されているものもある。
ただし、現在、秋田市で防犯灯を新設する際には「防犯灯を取り付けることができる電柱(木柱を除く)があること」が条件となっているようだ。(広報あきた2011年5月20日号)
じゃあ、秋田市内でLEDでない防犯灯は皆無になったのかといえば、そうでもない。
更新作業が終わった町内・地域にあっても、以前のものがそのままのところも、たまにある。(駐車場やマンションなど私有地内や管轄が違う公園や学校敷地内などに設置されている“防犯灯もどき”は、当然更新対象外)
 LED(手前)と既存のHIDが並ぶ
LED(手前)と既存のHIDが並ぶ理由はよく分からないが、路上にあるのにLED化されなかったものは、市の助成を受けずに、町内会が自腹で購入・設置した防犯灯ということなのだろうか。
 昼行灯の状態で残るHID
昼行灯の状態で残るHID防犯灯の電気代って定額なんだっけ? とすれば直接的な損失はないが、節電が求められるご時世だし、電球や灯具の寿命を早めることにはなる。
見た限りでは、残っている古い防犯灯は、水銀灯か蛍光灯ばかりだった。
昔ながらの白熱電球の防犯灯は…
 これ?
これ?秋田市中心部のとある町内で、ボロボロのものを発見。おそらく電球だと思う。
複数個あったが、どれも配線が切られており、中には電球が外された状態のものもあり、使われていないようだ。
【10月15日追記】10月12日付けで、秋田市市民生活部生活総務課のホームページが更新され、LED防犯灯の不具合発生時の連絡方法が掲載された。(http://www.city.akita.akita.jp/city/copr/ctcm_new/light.htm)
「市と契約した事業者(ESCO事業者)が、平成34年9月30日までの10年間、自動点滅器の不良や不点灯などの故障、灯具が落下しそうであるなどといった不具合が発生した場合の対応を行います。」
契約先の「秋田電気工事協同組合」へ電話またはファクス(いずれも市外局番018の一般電話)で、不具合の内容と防犯灯に貼られている「7桁の番号」を伝えるようにとのこと。
連絡先が一元化されたのはいいことだと思うが、できればメールでも連絡できるようにしてほしい。メールなら通話料がかからないのだから。(善意で伝える人に10円とはいえ負担させるべきではないと僕は思う)
「7桁の番号」は灯具に貼ってある黄色いシールのことで、「灯具管理番号」と呼ぶそうだ。前4ケタが「町内会コード」で、後ろ3ケタが「灯具番号」。
※2020年度には、秋田県道の照明で類似の手法が導入。















