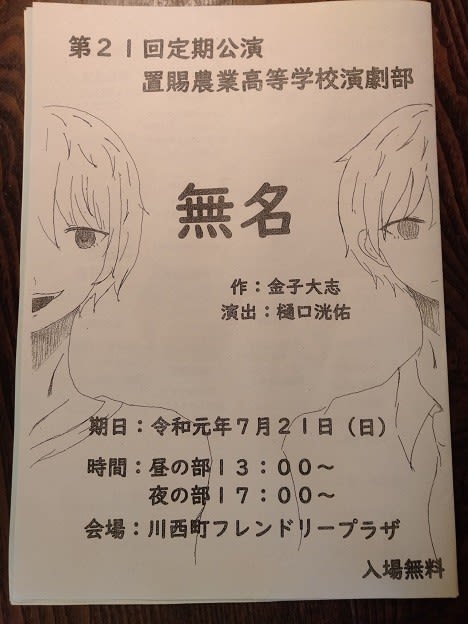えっ?!なに、これだけ???お客さん、100人足らず。実はそれも水増し、実は・・・。ま、まぁ、キャパ300弱の小さいホールだし、山間の小さな町だしなぁ、こんなもんなのか。
ほんと、何もない。いや、駅に温泉施設がある。物産館?もある。駅から5分、湯川温泉郷がある。ホール眼前には錦秋湖が広がっている。季節なら観光客も押しかけ大賑わい、・・って風情はほぼない。コンビニも一軒もなし。スーパーはあるようだけど、・・・。町、全体を見て回ったわけじゃないから、断定はできないが、はっきり言って、活気不足、よく言うば、昔の面影を今に残す、ってところ。
そんな町が27年間も演劇祭を続けている。これ、日本全国七不思議の一つだぜ。山の中ポツンと一軒家!ならぬ、山の中忽然と演劇祭!ってところだ。

2日間の入場者は、多分200人に届かなかっただろう。比較しちゃ悪いが、菜の花座の1回の公演の半分ってところだ。仮にチケットは入場者以上に捌けてたとしても、チケット収入で経費すべて賄えはしないだろう。我々の招集にかかった費用にだって、全然届かない。悪いねぇ、大枚はたいてもらって、ってそんな豪勢にもらったわけじゃないが。
これが川西での地元公演だったら、閑散とした客席見て青くなって震え上がってるよな。少ないお客さんの体温で、舞台の上も冷え冷えしちまうことだろうさ。で、はねた後は、大赤字のやり繰り算段に喧々諤々、青息吐息間違いなしだ。
なのに!泰然自若、動ずる気配まるでなし。入りが悪くてぇぇ、なんて弁解する様子もさらさらない。不可解と言えば不可解!不思議と言えば不思議!
だが、そんなこたぁとうに織り込み済みなんだろう。演劇祭発足当初はいざ知らず、ここ最近はきっとこんな調子で開かれ続けているんだろう。この山奥で、こんだけ集まりゃ大したもんだ、っておおらかに受け止めてるんだろう。大赤字?そんなことはどうってことない。これだけの人たちが舞台を楽しみに駆け付けた、ってことが素晴らしい!
うーん、その度量たるや良し!支える町行政の見識や見事!
それをがしっと支えているのが、ぶどう座の存在なのだろう。戦後の地域演劇活動を強力にリードした劇団、そしてそのリーダー川村光夫さん、その存在が今も光彩を放っているってことなんだ。全国に誇れる偉大な文化芸術活動、町の宝、その誇り!川西における井上ひさし、こまつ座のような存在。いや、創作活動が地域密着なだけ、もっともっと町民に根付いているに違いない。
かつては、そんなおらほの劇団、うちらの演劇祭へのリスペクトが確実にあった。だが、今じゃどこも風前の灯、時にゃ厄介者の烙印だって押されかねない。文化、芸術、そんなもんは中央のプロに任せておけ。いや、ゲームの方がよっぽど面白いぜ、の風潮だ。
そんな中、日本の最深部でこの演劇祭が気を吐いている。どっこい、文化も自前だぜ!それは、地域の心意気ってもんだろう。