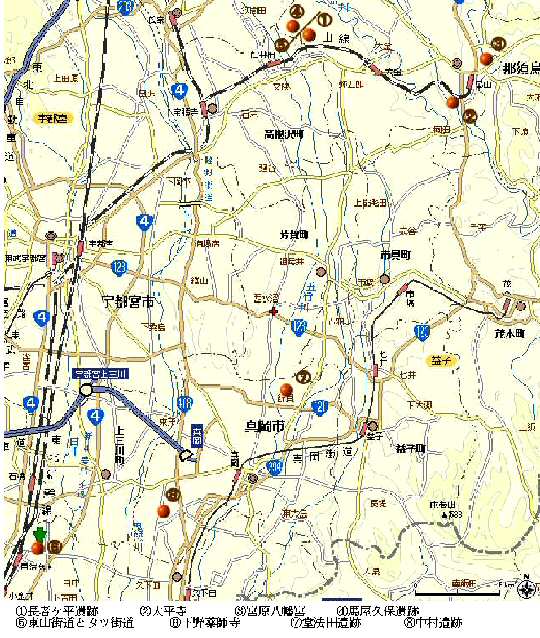新羅の山城で、洪水時に渓谷に一時に流れる水の圧力で城壁が崩壊するのを防ぐために、城壁内側に現代のダムと同じ巨大な防御壁を設置した跡が発掘調査で現れた。
国立文化財研究所は19日、韓国古代木簡の最大出土地の慶南咸安城山山城(6世紀中~後半築造)の第13次発掘調査で、東側渓谷を横切った石築城郭内側について幅15.2mに達する巨大な防御用「堤防」を積んだ跡を発見したことを明らかにした。この「堤防」は現在残っている規模からみて最大高さ2.4m、全長は27.2mに達する。この「堤防」は「敷葉工法(부엽공법)」により築かれた。
文字通り、「木の葉や草などを敷く方式」である敷葉工法は中国で始まり、韓半島を経て日本に伝えられた技術と評価され、水が流れる所に城壁や堤防などを積み重ねる時に適用された。
この工法は、日本の古代ダム式貯水池の狭山池(616年頃築造)の発掘調査で初めて確認されて以後、韓国ではソウル・風納土城と扶余羅城、唐津合徳堤、金堤、碧骨堤、利川雪峰山城などの地で部分的に確認されている。
城山山城城郭とこのダム式堤防は同時期に築造されたと判断されると調査団は話している。
今回の発掘成果は、現在まで合計246点が出土した城山山城新羅木簡の性格を解明するのにも決定的な役割をするものと見られる。
研究所は今回の発掘調査報告と諮問会議を20日午後咸安博物館と現場で開催する。
[参考:11/20聯合ニュース]
国立文化財研究所は19日、韓国古代木簡の最大出土地の慶南咸安城山山城(6世紀中~後半築造)の第13次発掘調査で、東側渓谷を横切った石築城郭内側について幅15.2mに達する巨大な防御用「堤防」を積んだ跡を発見したことを明らかにした。この「堤防」は現在残っている規模からみて最大高さ2.4m、全長は27.2mに達する。この「堤防」は「敷葉工法(부엽공법)」により築かれた。
文字通り、「木の葉や草などを敷く方式」である敷葉工法は中国で始まり、韓半島を経て日本に伝えられた技術と評価され、水が流れる所に城壁や堤防などを積み重ねる時に適用された。
この工法は、日本の古代ダム式貯水池の狭山池(616年頃築造)の発掘調査で初めて確認されて以後、韓国ではソウル・風納土城と扶余羅城、唐津合徳堤、金堤、碧骨堤、利川雪峰山城などの地で部分的に確認されている。
城山山城城郭とこのダム式堤防は同時期に築造されたと判断されると調査団は話している。
今回の発掘成果は、現在まで合計246点が出土した城山山城新羅木簡の性格を解明するのにも決定的な役割をするものと見られる。
研究所は今回の発掘調査報告と諮問会議を20日午後咸安博物館と現場で開催する。
[参考:11/20聯合ニュース]