Break down ― Je te donne la recherche

第66話 光望act.4―another,side story「陽はまた昇る」
父親の友人に勧められたから学問を棄て警察官になる、そんな選択を父がするだろうか?
洗い髪かき上げデスクに座り、ライトのスイッチ点ける。
そのまま抽斗を開錠すると周太は一冊の本を取出した。
『 La chronique de la maison 』
紺青色の布張表紙がライトに照らされる、これはフランス文学者だった祖父が記した。
全文がフランス語で綴られている舞台はパリ郊外、ある一家に起きた惨劇が描かれる。
ある「家」を廻らすミステリー小説、そのページを深呼吸ひとつで周太は捲りだした。
Mon visiteur 訪問客
La même période de l'université 大学時代の同期
L'agent de police du Département de la Police Métropolitain 警視庁の警察官
拾ってゆくフランス語の言葉たちは、第三者を指し示す。
惨劇に交錯する悲哀と憎悪、その中心に顕れる第三者が「誰」なのか?
それを物語から見つめた思考へと田嶋教授の言葉が映りこむ。
―…先輩は優秀な射撃の選手でな、それで湯原先生の友達で警察庁にいた方から勧められたんだ、
国家一種は締め切ってたけどな、警視庁の採用試験には間に合うからって受験したんだ。
祖父の教え子が語った過去の現実、それが祖父の著述にリンクする。
そしてフランス語に過去と真相は浮びあがって、鼓動が、息を呑む。
―まさか、でも、
もし「湯原先生の友達」が、あの老人だとしたら?
あの老人が今このページにある「La même période de l'université」なら?
そんな前提で見つめる「Mon visiteur」から、小説の語る焦点が輪郭に変貌する。
“大学時代の同期で警視庁の警察官だった男が、訪問客として現れた”
そして訪問客を迎えた「彼」は誰なのか?
その訪問客を迎えた「 maison 」は誰の家なのか、どこにある家なのか?
そんなふう現実世界と読み解くならば、たぶんリアルになる場所を自分は知っている。
「…でも、まだ一度だけしか読んでない、流し読みしただけ…」
つぶやき零れたフランス語のページには幾つかの単語が浮きあがる。
このどれもが過去の現実を示すと言うのなら、その全てが「keyword」過去を解く鍵だとしたら?
もしそうだとしたならば、今日、懸垂下降の訓練に想った疑問たちは全てフランス語に説かれている。
『 La chronique de la maison 』
パリ郊外の閑静な邸宅に響いた2発の銃声。
そして隠匿される罪と真相、生まれていく嘘と涙と束縛のリンク。
こうした物語を祖父が書き残した、その理由と意志と真相は、過去の現実は何だろう?
それを祖父に訊くことはもう出来ない、けれど祖父の肉筆が記したメッセージなら読める。
“Je te donne la recherche” 探し物を君に贈る
こんなメッセージを遺した想いは、どこにある?
そう考える前にもう今、こうして見つめるページ全てが「recherche」探し物に思えてくる。
けれど小説自体が「探し物」だとしたら、この言葉から生まれる意味をどう考えたら良いのだろう?
“ Mon pistolet ”
この小説は「小説」なのだろうか?
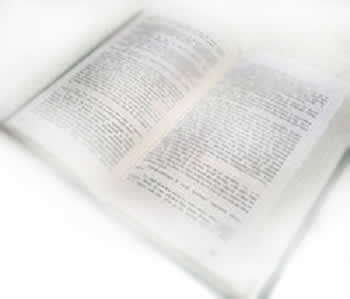
夕食の膳に箸を運ぶ、けれど想いが離れない。
いま隣には英二が座って笑う、前には箭野と黒木が笑っている。
そして自分も笑って会話しているのに、食事前の時間に独り、自室で見つめた推定が竦む。
―あの小説が贈る探し物は、真相って意味だとしたら、
真相、
たった2文字の熟語、けれど背負うものが今、重たい。
あの小説の内容が「真相」事実だとしたら、ならば祖父は「何の」事実をモデルに描いたのだろう?
祖父が訴えたかった真相は、事実は、いったい「誰の」現実だというのか?
―田嶋先生の話と一部が一致するからって即断することは出来ないけど、ね…
心つぶやく分析は、思ったより心は凪いだまま判断を廻らす。
もしかしたら、たぶん、あの小説は他人事ではないから祖父は「recherche」と語りかける。
そんな推定を抱きながらも落着いていられるのはきっと、もう現実が今すでに扉を開いたからだろう。
「来週から2週間、湯原にはSAT試験訓練が課されます。表向きは交番勤務の協力派遣となるが品川か術科センターに通ってもらう、」
午後15時すぎに聴いた台詞は「命令」だった。
本来ならSAT入隊は推薦を提案された者が熟考の上、志願して応じるはず。
けれど自分が告げられたのは提案でも志願の確認でも無い、あれは決定事項だった。
―言ってくれたとき佐藤小隊長の目、なんだか泣きそうで…申し訳ない、ね、
告げた佐藤の声は落着いていたけれど瞳は誤魔化しきれない。
あの目が告げられなかった沈黙は「疑問」を気付いてしまった苦しみがある。
それが解かるから申し訳なくて、その「疑問」への答えが祖父の小説である可能性は強まってゆく。
―お父さん、お父さんが異動する時もこんな感じだったの?…お父さんの上司は泣いてくれた?
心裡に語りかける俤は、ただ穏やかに微笑んで応えは無い。
けれど、たぶん、きっと祖父の小説は答えを贈ってくれるだろう。
“Je te donne la recherche” 探し物を君に贈る
祖父からの贈物を受けとめて、それから異動の扉を開きたい。
それが如何なる真相だとしても事実なら受けとめたい、その為に今ここに自分は居る。
そんな覚悟を嚙みしめるまま食事に箸を運んで、全てを体ひとつに呑みこむと周太は微笑んだ。
「黒木さん、大学の山岳部には他のクラブと掛持ちする人もいますか?」
(to be continued)
blogramランキング参加中!
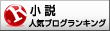
 にほんブログ村
にほんブログ村

第66話 光望act.4―another,side story「陽はまた昇る」
父親の友人に勧められたから学問を棄て警察官になる、そんな選択を父がするだろうか?
洗い髪かき上げデスクに座り、ライトのスイッチ点ける。
そのまま抽斗を開錠すると周太は一冊の本を取出した。
『 La chronique de la maison 』
紺青色の布張表紙がライトに照らされる、これはフランス文学者だった祖父が記した。
全文がフランス語で綴られている舞台はパリ郊外、ある一家に起きた惨劇が描かれる。
ある「家」を廻らすミステリー小説、そのページを深呼吸ひとつで周太は捲りだした。
Mon visiteur 訪問客
La même période de l'université 大学時代の同期
L'agent de police du Département de la Police Métropolitain 警視庁の警察官
拾ってゆくフランス語の言葉たちは、第三者を指し示す。
惨劇に交錯する悲哀と憎悪、その中心に顕れる第三者が「誰」なのか?
それを物語から見つめた思考へと田嶋教授の言葉が映りこむ。
―…先輩は優秀な射撃の選手でな、それで湯原先生の友達で警察庁にいた方から勧められたんだ、
国家一種は締め切ってたけどな、警視庁の採用試験には間に合うからって受験したんだ。
祖父の教え子が語った過去の現実、それが祖父の著述にリンクする。
そしてフランス語に過去と真相は浮びあがって、鼓動が、息を呑む。
―まさか、でも、
もし「湯原先生の友達」が、あの老人だとしたら?
あの老人が今このページにある「La même période de l'université」なら?
そんな前提で見つめる「Mon visiteur」から、小説の語る焦点が輪郭に変貌する。
“大学時代の同期で警視庁の警察官だった男が、訪問客として現れた”
そして訪問客を迎えた「彼」は誰なのか?
その訪問客を迎えた「 maison 」は誰の家なのか、どこにある家なのか?
そんなふう現実世界と読み解くならば、たぶんリアルになる場所を自分は知っている。
「…でも、まだ一度だけしか読んでない、流し読みしただけ…」
つぶやき零れたフランス語のページには幾つかの単語が浮きあがる。
このどれもが過去の現実を示すと言うのなら、その全てが「keyword」過去を解く鍵だとしたら?
もしそうだとしたならば、今日、懸垂下降の訓練に想った疑問たちは全てフランス語に説かれている。
『 La chronique de la maison 』
パリ郊外の閑静な邸宅に響いた2発の銃声。
そして隠匿される罪と真相、生まれていく嘘と涙と束縛のリンク。
こうした物語を祖父が書き残した、その理由と意志と真相は、過去の現実は何だろう?
それを祖父に訊くことはもう出来ない、けれど祖父の肉筆が記したメッセージなら読める。
“Je te donne la recherche” 探し物を君に贈る
こんなメッセージを遺した想いは、どこにある?
そう考える前にもう今、こうして見つめるページ全てが「recherche」探し物に思えてくる。
けれど小説自体が「探し物」だとしたら、この言葉から生まれる意味をどう考えたら良いのだろう?
“ Mon pistolet ”
この小説は「小説」なのだろうか?
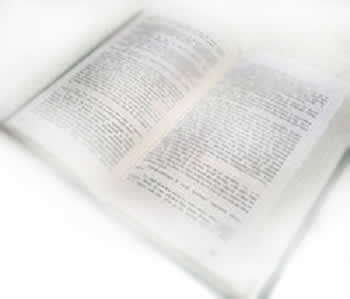
夕食の膳に箸を運ぶ、けれど想いが離れない。
いま隣には英二が座って笑う、前には箭野と黒木が笑っている。
そして自分も笑って会話しているのに、食事前の時間に独り、自室で見つめた推定が竦む。
―あの小説が贈る探し物は、真相って意味だとしたら、
真相、
たった2文字の熟語、けれど背負うものが今、重たい。
あの小説の内容が「真相」事実だとしたら、ならば祖父は「何の」事実をモデルに描いたのだろう?
祖父が訴えたかった真相は、事実は、いったい「誰の」現実だというのか?
―田嶋先生の話と一部が一致するからって即断することは出来ないけど、ね…
心つぶやく分析は、思ったより心は凪いだまま判断を廻らす。
もしかしたら、たぶん、あの小説は他人事ではないから祖父は「recherche」と語りかける。
そんな推定を抱きながらも落着いていられるのはきっと、もう現実が今すでに扉を開いたからだろう。
「来週から2週間、湯原にはSAT試験訓練が課されます。表向きは交番勤務の協力派遣となるが品川か術科センターに通ってもらう、」
午後15時すぎに聴いた台詞は「命令」だった。
本来ならSAT入隊は推薦を提案された者が熟考の上、志願して応じるはず。
けれど自分が告げられたのは提案でも志願の確認でも無い、あれは決定事項だった。
―言ってくれたとき佐藤小隊長の目、なんだか泣きそうで…申し訳ない、ね、
告げた佐藤の声は落着いていたけれど瞳は誤魔化しきれない。
あの目が告げられなかった沈黙は「疑問」を気付いてしまった苦しみがある。
それが解かるから申し訳なくて、その「疑問」への答えが祖父の小説である可能性は強まってゆく。
―お父さん、お父さんが異動する時もこんな感じだったの?…お父さんの上司は泣いてくれた?
心裡に語りかける俤は、ただ穏やかに微笑んで応えは無い。
けれど、たぶん、きっと祖父の小説は答えを贈ってくれるだろう。
“Je te donne la recherche” 探し物を君に贈る
祖父からの贈物を受けとめて、それから異動の扉を開きたい。
それが如何なる真相だとしても事実なら受けとめたい、その為に今ここに自分は居る。
そんな覚悟を嚙みしめるまま食事に箸を運んで、全てを体ひとつに呑みこむと周太は微笑んだ。
「黒木さん、大学の山岳部には他のクラブと掛持ちする人もいますか?」
(to be continued)
blogramランキング参加中!


















