今年のノーベル文学賞について、エラげバカの記事を見かけたのでナントナク書きます、笑
まず・作詞家が受賞することは、
イギリス文学ならシェークスピアにワーズワス、フランス文学ならロンサール、
を文学史の巨人に讃えるヨーロッパ文学界ってことを知っていれば、納得できるだろな・ってことです。
↑
で・イキナリ毒舌ですけど、ロンサールがワカラナイってヒトは作詞家の受賞アレコレ批評する資格ありません、笑
ノーベル文学賞ってドンナのが受賞するのか?
って言うと「文学のアイデンティティ」にあるかなって思います。
どーゆーことかって言うと・これまでの受賞者×創作にある傾向性は、
①民族母国&母語のアイデンティティ
②その時代性の反映
③世界平和への貢献
④不変性×普遍性
とくに①は重要視されているのかなって思います。
アイデンティティ=オリジナリティ・個性につながるとこですから、ポイントたりえてアタリマエなんでしょうけど。
その国に生まれ、その言語を母語として世界を感じ・考え、そうして培った思考フィルターを通して生まれてくるものが文学。
ようするに「自分がいる世界と向きあっているのか?」が問われるのが文学です、だからこそ①と②が重要視されることはアタリマエ。
母語と母国への誇り、そこから伝統を追求して生まれる「その人にしか描けない文学」が文学のアイデンティティってコトです。
たとえば川端康成、
彼の有名なヤツといえば『伊豆の踊子』『雪国』など教科書にも載ってるアレですが、
彼の作品はどれも物語性は冒険活劇でもナンもなく、イワユル思想性も何もありません。
ただしココ↓はすごいかなと、
A.情景描写と心理描写は再現度が高い
B.日本の文化・風景を描ききっている
C.なんでもない人間のアリキタリ=「あるある」感=普遍性
Aは文学にあるべき要素です、
Bは①+②に該当します、
Cは人間だれにも該当する=④普遍性になるわけです、
って考えると③に該当するとこは彼に無いんですけど、笑
大江健三郎も同様です、
語り部=口承文芸の家系に生まれた特性が大江さんの文章は滲んでいる=①や④、
障害のあるお子さんとの対話から生まれたものが②や③ともなっています。
ここまで書くと気づかれた方もいると思いますが、
毎年バカ騒ぎされる日本人某氏はノーベル文学賞にちょっと遠いんじゃないかってことです。
日本人ならではのアイデンティティ×母国風土の美しさを描く、っていう①が希薄だからひっかかりっこない。
ちょっとキツイ言い方すれば・日本人が西洋文学のサルマネして翻訳版も出して欧米で著名になっても無理だよってことです。
日本人にしか描けない文学がある。
作詞家の受賞についても少し掘ると、そもそも歌謡が口承文芸に属する文学です。
口承文芸は「口伝=言い伝えられてきた文学」文字化されない文芸なんですけど、
いわゆる昔話・伝説など物語=散文もあり、たとえば祝詞・民謡など韻文もあります。
こうした口承文芸は文学研究テーマの一つなワケですが、歌謡いわゆる「ウタ」詩歌の原型もコレになります。
歌謡・詩歌で有名どころなら、
日本でたとえるなら『万葉集』にも詠う柿本人麻呂、遺した歌の文学性が讃えられる歌聖です。
短歌・長歌どちらも伝説や恋の物語など詠みこまれた物語性があり、当時は朗詠=節をつけて唄われていました。
アルチュール・ランボオ、早逝の天才と謳われるフランス詩人は解かりやすい例だと思います。
作詩当時のランボオは十代~二十代前半の青少年期まっただ中、その年齢と当時のフランス世相が現れた詩ばかりです。
日本では堀口大學が翻訳を紹介して有名になりましたが詩集『地獄の季節』などベストセラーになっています。
ランボオの作詩を上の①~④に当てはめると、
①フランス風土・伝説②フランス当時の倦怠感・退廃的空気③退廃から静穏への希求④青年期の煩悶→永遠性を太陽・海へ希求
ランボオの詩は反骨×繊細+聡明です、
イマドキの青少年にも受けるだろうし、どの時代の青少年にも受ける普遍性があります。
たぶんフランス文学を志す人だったら一度はランボオは通っているってくらいウケています、笑
詩は「くちずさむ」人麻呂もランボオも当時を生きた人々は口ずさみ親しんでいました。
それはシェークスピアも同じで戯曲の作中歌は流行歌となり歌われていたワケです、
この「くちずさむ」ために詩はくちずさみやすい「韻」を踏んで作ることが求められています。
漢詩の五言絶句・七言律詩などもコレと同じこと、語数をそろえ・音をそろえ・くちずさみ易く作られたものが「詩ウタ歌」です。
ようするに「旋律つき文学」が「ウタ」歌・詩、という定義になります。
「あなたのお国のシェークスピアは?」
ていう初対面挨拶が欧米ではあるくらい文学代表=シェークスピアです。
そんなシェークスピアは小説家ではありません、戯曲家&詩人としてイギリス文学を築いた巨人です。
それくらい戯曲や詩は文学としての地位が高いヨーロッパで授与されるノーベル文学賞が、詩人や作詞家に授与されても不思議はありません。
ノーベル文学賞「文学のアイデンティティ」+文学の一つ「ウタ」
ってコトらを解かっていると今回の作詞家受賞はナンも不思議はなく、おおいにありってコトです。
今回の受賞に「歌手がー」とか言うヤツはソコラヘン無知なクセにアレコレ言ってるだけなんだろうと、笑
ボブ・ディランの作詞は母国アメリカのアイデンティティを謳っている+①~④シッカリ踏襲、納得だと思うんですけども。
で、日本でノーベル文学賞を受賞する可能性ないの?っていうと研究者ならいます。
物理学賞は宇宙飛行士ではなく研究者、医学賞も臨床医ではなく研究者に与えられています。
それなら文学賞も研究者に与えられてしかるべきだと思うんですよね。
小説も作詞も研究時間から創作が生まれます、その過程に道しるべを建てる研究者も評価されるべきだろうと。
文学は分析力必須、ある意味で数学的・統計的だし数列思考を利用して創作される合理的客観的視点がナイとできません。
足し算ができても掛け算すっとばして因数分解は出来ない、それは文学も同じです。
詩歌なら韻をふむ技術が音律をつくります、それには名詩から言葉や文字の遣い方あれこれに作詩当時の社会文化を知る。
それは散文も同様だし外国文学の翻訳も同じこと、その創作物当時の言語から生活・事件・時代性など知るほど、作品世界を伝えてもらえる。
古典文学も・原文から読まず翻訳から読んだダケでは描かれる空気が解かりません、だから古文法や変体仮名を学ぶ必要もある。
小説も詩歌も漠然と生まれてくるものではない、その作り手が「書きたい」と綴った向こうの世界を受けとることが「読む」です。
そこらに「いんすぴれーしょんがー」とか言ってるヤツもいますけど、ソレダケで書いたモンは普遍性も不変性も生まれません。
だからこそ文学も学問研究の一環、その学問たる尊厳を知らない軽佻浮薄人が「いんすぴれーしょんがー」強調ぶろがーなわけですが、笑
学ぶ努力経験ないコンビニエント論は狭い了見バカにしかなれません、くだらない虚栄心で貶めたがる批評屋って多いけど。
努力しよーともせず論じたら・努力に生まれた作品に失礼だ。
前にも書いたことだけれど・
文学の定義もその文学賞の意味も知らない考えたことない無知が厚顔無恥しているブログ記事って多いです。
とことん突詰めてナイくせにエラソー批評とか公開すべきじゃない。
言いたい放題 Part3ブログトーナメント
 にほんブログ村
にほんブログ村
blogramランキング参加中!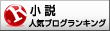


まず・作詞家が受賞することは、
イギリス文学ならシェークスピアにワーズワス、フランス文学ならロンサール、
を文学史の巨人に讃えるヨーロッパ文学界ってことを知っていれば、納得できるだろな・ってことです。
↑
で・イキナリ毒舌ですけど、ロンサールがワカラナイってヒトは作詞家の受賞アレコレ批評する資格ありません、笑
ノーベル文学賞ってドンナのが受賞するのか?
って言うと「文学のアイデンティティ」にあるかなって思います。
どーゆーことかって言うと・これまでの受賞者×創作にある傾向性は、
①民族母国&母語のアイデンティティ
②その時代性の反映
③世界平和への貢献
④不変性×普遍性
とくに①は重要視されているのかなって思います。
アイデンティティ=オリジナリティ・個性につながるとこですから、ポイントたりえてアタリマエなんでしょうけど。
その国に生まれ、その言語を母語として世界を感じ・考え、そうして培った思考フィルターを通して生まれてくるものが文学。
ようするに「自分がいる世界と向きあっているのか?」が問われるのが文学です、だからこそ①と②が重要視されることはアタリマエ。
母語と母国への誇り、そこから伝統を追求して生まれる「その人にしか描けない文学」が文学のアイデンティティってコトです。
たとえば川端康成、
彼の有名なヤツといえば『伊豆の踊子』『雪国』など教科書にも載ってるアレですが、
彼の作品はどれも物語性は冒険活劇でもナンもなく、イワユル思想性も何もありません。
ただしココ↓はすごいかなと、
A.情景描写と心理描写は再現度が高い
B.日本の文化・風景を描ききっている
C.なんでもない人間のアリキタリ=「あるある」感=普遍性
Aは文学にあるべき要素です、
Bは①+②に該当します、
Cは人間だれにも該当する=④普遍性になるわけです、
って考えると③に該当するとこは彼に無いんですけど、笑
大江健三郎も同様です、
語り部=口承文芸の家系に生まれた特性が大江さんの文章は滲んでいる=①や④、
障害のあるお子さんとの対話から生まれたものが②や③ともなっています。
ここまで書くと気づかれた方もいると思いますが、
毎年バカ騒ぎされる日本人某氏はノーベル文学賞にちょっと遠いんじゃないかってことです。
日本人ならではのアイデンティティ×母国風土の美しさを描く、っていう①が希薄だからひっかかりっこない。
ちょっとキツイ言い方すれば・日本人が西洋文学のサルマネして翻訳版も出して欧米で著名になっても無理だよってことです。
日本人にしか描けない文学がある。
作詞家の受賞についても少し掘ると、そもそも歌謡が口承文芸に属する文学です。
口承文芸は「口伝=言い伝えられてきた文学」文字化されない文芸なんですけど、
いわゆる昔話・伝説など物語=散文もあり、たとえば祝詞・民謡など韻文もあります。
こうした口承文芸は文学研究テーマの一つなワケですが、歌謡いわゆる「ウタ」詩歌の原型もコレになります。
歌謡・詩歌で有名どころなら、
日本でたとえるなら『万葉集』にも詠う柿本人麻呂、遺した歌の文学性が讃えられる歌聖です。
短歌・長歌どちらも伝説や恋の物語など詠みこまれた物語性があり、当時は朗詠=節をつけて唄われていました。
アルチュール・ランボオ、早逝の天才と謳われるフランス詩人は解かりやすい例だと思います。
作詩当時のランボオは十代~二十代前半の青少年期まっただ中、その年齢と当時のフランス世相が現れた詩ばかりです。
日本では堀口大學が翻訳を紹介して有名になりましたが詩集『地獄の季節』などベストセラーになっています。
ランボオの作詩を上の①~④に当てはめると、
①フランス風土・伝説②フランス当時の倦怠感・退廃的空気③退廃から静穏への希求④青年期の煩悶→永遠性を太陽・海へ希求
ランボオの詩は反骨×繊細+聡明です、
イマドキの青少年にも受けるだろうし、どの時代の青少年にも受ける普遍性があります。
たぶんフランス文学を志す人だったら一度はランボオは通っているってくらいウケています、笑
詩は「くちずさむ」人麻呂もランボオも当時を生きた人々は口ずさみ親しんでいました。
それはシェークスピアも同じで戯曲の作中歌は流行歌となり歌われていたワケです、
この「くちずさむ」ために詩はくちずさみやすい「韻」を踏んで作ることが求められています。
漢詩の五言絶句・七言律詩などもコレと同じこと、語数をそろえ・音をそろえ・くちずさみ易く作られたものが「詩ウタ歌」です。
ようするに「旋律つき文学」が「ウタ」歌・詩、という定義になります。
「あなたのお国のシェークスピアは?」
ていう初対面挨拶が欧米ではあるくらい文学代表=シェークスピアです。
そんなシェークスピアは小説家ではありません、戯曲家&詩人としてイギリス文学を築いた巨人です。
それくらい戯曲や詩は文学としての地位が高いヨーロッパで授与されるノーベル文学賞が、詩人や作詞家に授与されても不思議はありません。
ノーベル文学賞「文学のアイデンティティ」+文学の一つ「ウタ」
ってコトらを解かっていると今回の作詞家受賞はナンも不思議はなく、おおいにありってコトです。
今回の受賞に「歌手がー」とか言うヤツはソコラヘン無知なクセにアレコレ言ってるだけなんだろうと、笑
ボブ・ディランの作詞は母国アメリカのアイデンティティを謳っている+①~④シッカリ踏襲、納得だと思うんですけども。
で、日本でノーベル文学賞を受賞する可能性ないの?っていうと研究者ならいます。
物理学賞は宇宙飛行士ではなく研究者、医学賞も臨床医ではなく研究者に与えられています。
それなら文学賞も研究者に与えられてしかるべきだと思うんですよね。
小説も作詞も研究時間から創作が生まれます、その過程に道しるべを建てる研究者も評価されるべきだろうと。
文学は分析力必須、ある意味で数学的・統計的だし数列思考を利用して創作される合理的客観的視点がナイとできません。
足し算ができても掛け算すっとばして因数分解は出来ない、それは文学も同じです。
詩歌なら韻をふむ技術が音律をつくります、それには名詩から言葉や文字の遣い方あれこれに作詩当時の社会文化を知る。
それは散文も同様だし外国文学の翻訳も同じこと、その創作物当時の言語から生活・事件・時代性など知るほど、作品世界を伝えてもらえる。
古典文学も・原文から読まず翻訳から読んだダケでは描かれる空気が解かりません、だから古文法や変体仮名を学ぶ必要もある。
小説も詩歌も漠然と生まれてくるものではない、その作り手が「書きたい」と綴った向こうの世界を受けとることが「読む」です。
そこらに「いんすぴれーしょんがー」とか言ってるヤツもいますけど、ソレダケで書いたモンは普遍性も不変性も生まれません。
だからこそ文学も学問研究の一環、その学問たる尊厳を知らない軽佻浮薄人が「いんすぴれーしょんがー」強調ぶろがーなわけですが、笑
学ぶ努力経験ないコンビニエント論は狭い了見バカにしかなれません、くだらない虚栄心で貶めたがる批評屋って多いけど。
努力しよーともせず論じたら・努力に生まれた作品に失礼だ。
前にも書いたことだけれど・
文学の定義もその文学賞の意味も知らない考えたことない無知が厚顔無恥しているブログ記事って多いです。
とことん突詰めてナイくせにエラソー批評とか公開すべきじゃない。
言いたい放題 Part3ブログトーナメント
blogramランキング参加中!


著作権法より無断利用転載ほか禁じます




























