3月12日
桜三里の入り口にある桜はまだつぼみばかりで写真にもとらなかったのです。
そこから少し走って信号待ちをしていると、向こうにピンクの塊が見えました。ここには桜が数本植えてあるのですが、個人のお家のようなので詳しく見ることができません。まだつぼみが多いようでした。

そうか、そろそろ早咲きの桜が咲き始めるころでしたね。 今年は高知県の雪割桜を見に行こうと計画していたのですが、開花が遅れているようで、予定していた日にはほどんど咲いてなかったのです。ああ、今週末だったら見ごろだったのになあ、三月の土、日はすべて予定で埋まっており、とうとう行くことができませんでした。
雪割桜はツバキカンザクラという種類の桜だそうです。
なのでいつものツバキカンザクラを見て来ようと、市内の工場にあるツバキカンザクラを見に行きました。
3月13日
塀からあふれるように咲いていました。

この時期、工場は敷地を解放してくれています。
この大木を見ると懐かしい。 トラオとウマオがまだ小さいとき、アイスをおごるからと連れてきたら、花を見ずこの木の下に座り込んでアイスをなめていたっけ。トラオと父とで来たこともあります。元気いっぱい父のもとに駆け寄るトラオ。父のひ孫の中でトラオは一番交流を深めた孫でした。

ヒヨドリが数羽飛び交っていました。



華やかですね。

手前の白い花はサクランボのようです。

雄蕊がたくましい。

まだまだ咲いているサザンカ。

別の一角には河津桜もありますが、こちらは少しだけ咲くのが早いのです。椿寒桜よりすっきりとした印象です。どちらも好き。

その中にこんな枝を付けた木があったのですが、これは何かしら。つぼみのようでもあり、葉っぱのようでもあり、この木だけにあるのも不思議でした。

帰りに川の土手に咲いていた桜を、車から降りて見てみました。散歩中の人が立ち止まって見ていたので、ここに桜があったことに気が付いたのです。

これがなんという桜なのかさっぱりわかりません。河津桜よりは色が薄いように思えるし・・・


サクラってある時期が来るまで全然気が付かないのに、木が大きくなって花がたくさん咲いてはじめてそこにあったことに気が付くことがありますね。
我が家のサクランボも花が咲いています。



そこから少し離れたところに小さな芽が出て、バラかしらと思っていたらなんとサクラでした。親木から根っこが伸びてきたのだと思いますが

これはちょっと困る。 家のすぐ傍ですから。
3月14日
桜三里入り口のサクラ

2日前はつぼみばかりだったのに、はや5分咲きくらいになっていてびっくりしました。 相変わらず、大きな看板が邪魔。


これも河津桜なのでしょうか。少し山際にあるとはいえ、工場の河津桜と比べると咲くのが遅いので、どうなのかなあと思っています。

そして2日前に見た交差点の向こうのサクラは


最初の写真 ↓ と比べてみると

大分花が開いていました。たった2日で。
春を呼ぶ椿祭りが早かった今年ですが、春は立ち止まり足踏みしてなかなかやってきませんでしたが、やっとここに来て一気に駆け足になったようです。






























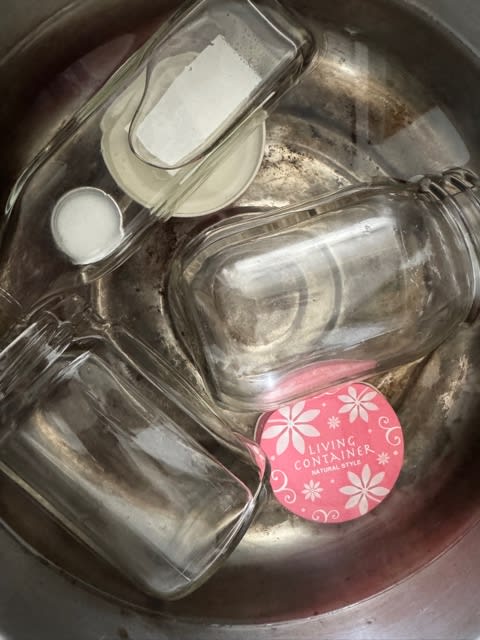








































 心の中には一足早く春が来ました。
心の中には一足早く春が来ました。





