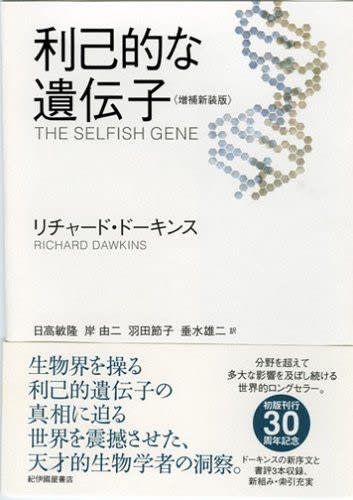
本書の第一版は1976年にイギリスで出版され、日本語版は1980年に「生物=生存機械論」という書名で出版された。日本語第三版(30周年記念版)は2006年、日本語第四版(40周年記念版)は2018年に出版された。いまや、科学史に燦然と輝く不朽の名著と言われているが、私が生物学科の学生だった1980年代は、「生物=生存機械論」という書名にあざとさやいかがわしさすら感じていたので、読むことはなかった。あれから30年以上たってようやく本書を読むことにしたのである(私が買ったのは第三版)。もともと当時の動物行動学や進化学の理論的な研究の考察をもとに書かれた本であるので、この本の内容が出版から40年たってどこまで実証されたのかはこの分野の専門家でないとわからない。しかし、目の覚めるような論理展開とたくさんの考えるヒントが提供されていることは確かだ。この本の主張を一言でいえば、遺伝子の利己性がすべての進化の原動力だと考えることで、生物の増殖や社会活動など様々な生物現象がうまく説明できるようになるということだろう。なお、遺伝子の利己性そのものはどこからやってくるのか、何を原動力としてそのような働きをするのかという疑問も湧いてくるが、それについてはまったく無視されているように感じた。それから、訳のせいもあるのかもしれないが、文章が平易でないので、読みにくさのある本である。
以下は私なりのポイントの記録である。
[30周年記念版への序文]
・自然淘汰が作用する必然的に「利己的な」生命の階層構造のレベルは、種でもなく、集団(群)でもなく、個体でもなく、生態系でもなく、遺伝子である。
[1989年版へのまえがき]
・利己的遺伝子説は、ネオ・ダーウィニズムの論理的な発展である。
2.自己複製子
・今でこそ遺伝子と呼ばれるようになった自己複製子は、以前は海中を気ままに漂っていた。この40億年の間に、彼らはその自由を放棄し、外界から遮断された巨大なロボットに中に巨大な集団となって群がり、曲がりくねった間接的な道を通じて外界と連絡をとっている。われわれは彼らの存在機械である。
3.不滅のコイル
・遺伝子レベルでは、利他主義は悪であり、利己主義が善である。遺伝子は生存中その対立遺伝子と直接競いあっている。対立遺伝子の犠牲のうえに、遺伝子プール内で自己の生存のチャンスをふやすようにふるまう遺伝子は、その定義からして、生きのびる傾向がある。
・無性生殖に対立するものとしての有性生殖が、有性生殖の遺伝子を有利にするのであれば、これによって有性生殖の存在は十分に説明できる。その遺伝子が個体の残りの遺伝子すべてに役立つか否かということはあまり関係がない。
5.攻撃―安定性と利己的機械
・個体間の攻撃や戦いについて、おおくの議論がされている。コンラート・ローレンツは自著の「攻撃」の中で、動物の戦いは抑制のきいた形式的なものであるとしているが、その考えには反対している。ドーキンスは、数学のゲーム理論を利用した、J・メイナード=スミスが提唱している概念である、進化的に安定な戦略(ESS;evolutionarily stable strategy)の考え方に依拠している。この考え方によると、攻撃的なタカ派と逃げるだけで攻撃はしないハト派を設定すると、それら単独の戦略自体はどちらも進化的に安定ではない。それより、タカ派が12分の7、ハト派が12分の5の数になるとその個体群は安定な平衡状態になるという。
6.遺伝子道
・生存機械が利他的にふるまうかどうかは、ある個体の自分に対する近縁度をかけて危険(マイナス)と利益(プラス)について計算することでシミュレーションできる。何もしないことが正味の利益の得点を最高にする「行動」であるならば、モデル動物は何もしないだろう。
・溺れかかっている人間が野生のイルカに助けられたという話がよくある。これは、群れの溺れかけているメンバーを救うための規則の誤用だと考える。つまり、イルカは困っている近縁の個体を助けるようにプログラムされているのだが、そのプログラムが誤用されて、つまり対象を正確に認識できずに間違って人間を救ってしまうという解釈をしている。
8.世代間の争い
・人間の女性が中年期に唐突にその生殖能力を失ってしまう現象、つなわち月経停止の進化に関して考えうる一つの説明として、遺伝的に意図されたもの、すなわち何らかの適応である可能性を指摘している。高齢の母から産まれた子どもの平均寿命は、若い母親の子どもの寿命にくらべて短いことが予想される。そうなると子どもよりむしろ孫に投資したほうが有利になる。そのため、中年期に繁殖能力を喪失させるように仕向ける遺伝子が次第に増加したと考えられる。
・カッコウと里親の間にみられる争いなどを観察すると、子どもに詐欺行為をおこなわせる傾向をもつ遺伝子が、遺伝子プール内で有利さを示すことが考えられる。これは「子どもはごまかし行為をすべきだ」と表現されることになるが、人間的なモラルを引き出すとすれば、「私たちは子どもに利他主義を教えこまねばならない」ということになる。つまり、子どもたちの生物学的本性の一部に利他主義が組み込まれていると期待することはできないとしている。
9.雄と雌の争い
・雄と雌では遺伝子を残すために異なる戦略を取ることが多い。人間の女性は、たくましい雄を選ぶ戦略ではなく、家庭第一の雄を選ぶ戦略を採用していることが示唆される。一方、人間の男性には一般的に乱婚的傾向がある。ほとんどの人間社会は、一夫一妻制をとっているが、乱婚的な社会もあるし、ハーレム制にもとづいたような社会もある。この二つの傾向のいずれが他を圧倒するかは、遺伝子ではなくむしろ文化によって決定されていると考えられる。
10.ぼくの背中を掻いておくれ、お返しに背中をふみつけてやろう
・R・L・トリヴァースは、人間において他者をだます能力や、詐欺を見破る能力、だまし屋だと思われるのを回避する能力などを強化する方向にはたらいた自然淘汰が、人間に備わる各種の心理的特性-ねたみ、罪悪感、感謝の念、同情そのほか-を形成したのだと主張している。人間の肥大した大脳や、数学的にものを考えることのできる素質は、より込み入った詐欺行為をおこない、同時に他人の詐欺行為をより徹底的に見破るためのメカニズムとして進化した可能性も考えられる。
11.ミーム―新登場の自己複製子
・これまで、自己複製子として遺伝子について述べてきたが、新たな自己複製子として人間の文化をミームと命名している。それはまだ未発達な状態にあるが、すでにかなりの速度で進化的変化を達成しており、遺伝子という古参の自己複製子ははるかに後方に遅れているとしている。
・ミームと遺伝子は、しばしば互いに強化しあうが、ときには相対立することもある。たとえば、独身主義の習慣などは、遺伝子によって伝わるものではないだろう。宗教、とくに聖職者の中のミームとして説明されている。
・ドーキンスは、人間が自己の存在を利己的遺伝子に全面的に委ねるべきだと言っているわけではない。むしろ、純粋で、私欲のない利他主義は、自然界、そして世界の全史を通じて存在したためしがないが、私たちはそれを計画的に育成し、教育する方法を論じることができる、と述べている。
・本書の主要なアイデアは、W・D・ハミルトンの血縁淘汰理論からきている。彼の1964年の論文の被引用数を調べると年々増加していて、その科学的なアイデアはミームとして拡大しているといえる。
12.気のいい奴が一番になる
・政治学者のロバート・アクセルロッドは、気がいいか意地悪か、寛容か非寛容か、妬み深いかそうでないかといった戦略をコンピューター上で戦わせると、気のいい、寛容な、妬み深くない戦略が勝利することを示した。これは自然界にも適用できるという。
・人間の行う献血は、純粋な、利害にかかわりのない利他行動かもしれない。動物でも、チスイコウモリは似たような行動、つまり血にありつけなかった仲間に自分が吸った血を吐いて与えるという行動があるという。利己的な遺伝子に支配されていても、気のいい奴が一番になることができる例として挙げている。
13.遺伝子の長い腕
・ある遺伝子が、その生物自身の表現型効果を示すのと同様に、寄生した寄主の行動に影響を及ぼすことを「延長された表現型」効果とよんでいる。「延長された表現型」を示す激烈な例は、昆虫で見られる。例えば、コヌカアリ属の仲間は、ほかの種類のアリに寄生する。この寄生者のアリは、女王がたった一匹で別の種類のアリの巣に忍び込む。そして、寄主の女王を捜し出すと、その背中に馬乗りになって、頭を切り落とす。そのあと、孤児になったワーカーたちはなんの疑いも感じずに、彼女の卵や幼虫の世話をする。このワーカーの行動は寄生者にとって延長された表現型である。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます