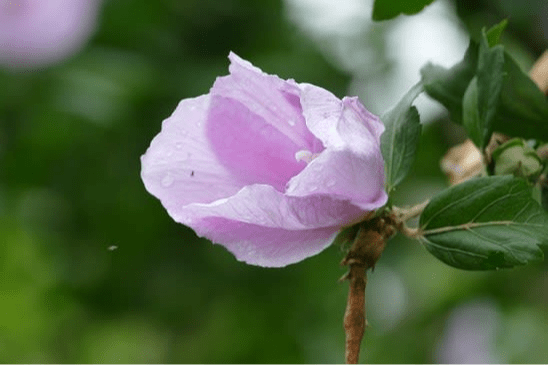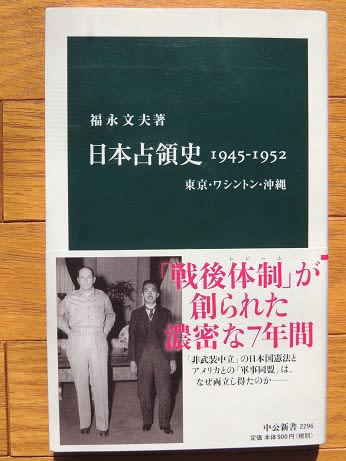私は東京の調布市に住んでいる年金生活の75歳の身であるが、
先程、ときおり愛読している公式サイトの【 介護ポストセブン 】の『健康』を見たりしていた。
こうした中で、病院や薬に頼らず、放っておいたほうがいい病気があると主張する専門医に、
病気を治すための生活や健康法を聞いた。
病気に負けない9つの免疫力アップ術をお伝えする。
このような首記文を見たりした。私は何かと無知なことが多く、遅ればせながら学ぼうと思い、こっそりと読んで、多々教示され、やがて微笑んだりした・・。この記事の原文は、『女性セブン』の2020年7月30日・8月6日号に掲載された記事のひとつで、関連の公式サイトの【 介護ポストセブン 】で8月5日に配信され、記事の要点を転載させて頂く。《・・病気に負けない9つの免疫力アップ術
1.体を温めて回復力を向上させる
風邪やインフルエンザ、高血圧、膀胱炎など、
多くの病気が放っておいた方がいい経過を辿ることが、
専門家への取材で明らかになった。
→放っておいた方がいい病気リスト|風邪、膀胱炎、高血圧…治療や薬をやめて治った!?
しかし、一口に「放っておく」といっても、
何に気をつけてどんな生活をすればいいのか。
青山・まだらめクリニック院長の班目健夫さんが解説する。
「病気を治そうとするなら、体を思いやった生活をすることが大事です。
たとえ病気にかかって治療を受けるにしても、
体の回復力を充分に発揮できる状態にしておかなければ、効果が期待できません」
体の回復力を発揮するために班目さんが重要視するのは、
「体温を上げる」ことだ。
「名古屋の小学校で調査したところ、
体温が低い子供は、欠席が多いことがわかりました。
白血球の中でもリンパ球は、体に入ってくる異物を排除する働きがありますが、
体温が低い人は、血液中のリンパ球が少ない。
体が冷えていると、リンパ球の数が少なくなり内臓の機能も悪くなります。
肩や首のこりや痛みに悩む人が多いのも、
体が冷えて、内臓に血液がきちんと流れていない状態だからです。
体を温めれば回復力は向上します」(班目さん)
 2.湯たんぽ健康法で体温を上げる
2.湯たんぽ健康法で体温を上げる
体を温めるために班目さんがおすすめするのが、「湯たんぽ健康法」だ。
「容量が2Lの湯たんぽを使って、中に沸騰したお湯を入れます。
温めるのは一か所につき3~10分。
お腹→太ももの前面→お尻→二の腕の順番で、湯たんぽを移動させて、
体を温めます。
やけどをしないように気をつけて、あと5分くらいしたら
汗をかきそうと感じた時点で、次の部位に湯たんぽを移動させましょう」(班目さん)
不調を治す「湯たんぽ健康法」のやり方
【1】お腹を温める
あお向けになり、下腹部に湯たんぽをのせ、少しずつ位置をずらしながらお腹全体を温める。
【2】太ももを温める
あお向け、または椅子に座った状態で太ももの前面に湯たんぽをのせる。
足の付け根からひざまで、まんべんなく温めることを意識するとよい。
【3】お尻を温める
湯たんぽを椅子の背もたれに置き、背中をくっつけて腰からお尻にかけてを温める。
椅子がない場合はあお向けになって、お尻の下に湯たんぽを置く。
【4】二の腕を温める
机の上に湯たんぽを置き、その上に二の腕をのせる。
二の腕の内側にある「伸筋」が充分に温まるように意識する。
 3.昼冷たいものを飲んだら夜は温かい紅茶
3.昼冷たいものを飲んだら夜は温かい紅茶冷たい飲み物が欲しくなる季節だが、飲みすぎないようにする工夫も必要だ。
「炎天下を歩いて体温が上がったときは、
温かいものを飲んでも吸収されないので、冷たいものを飲んだ方がいい。
ただし、冷たいものばかり飲んでいると、胃が疲弊します。
胃の温度は約38℃ですが、冷蔵庫から出してすぐの飲み物は4℃ぐらいしかありません。
飲み続けると胃の温度が下がって、疲労を感じやすくなるのです」(班目さん)
昼間冷たいものを口にしたら、夜は温かい紅茶を飲むといい。
一日の中で帳尻を合わせれば、体温が下がらないし、夏バテ防止にもなる。
「胃に負担をかけないよう、食べるときはよく噛んで唾液の分泌を盛んにし、
消化吸収しやすいような状態で飲み込むことも大事です」(班目さん)
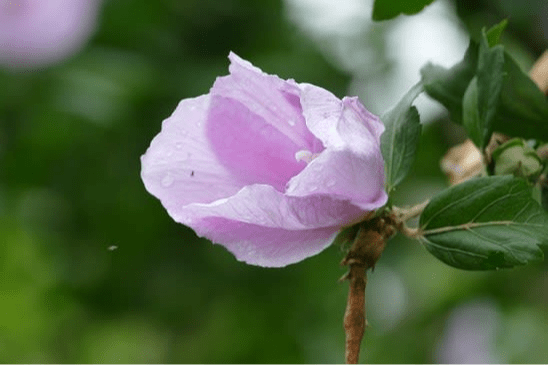 4.手首をそらせるストレッチ
4.手首をそらせるストレッチ体を温めるには、手首をそらせるストレッチもいいという。
「親指以外の4本の指先を反対側の手でつかんで、
手首を思いっきりそらします。
前腕の筋肉が張って、痛いと感じるくらい何度も強くそらすと、
血流がよくなっていきます。
個人差があるので、腕が温まるのを感じるまで続けてください」(班目さん)
 5.免疫の7割は腸内環境にある
5.免疫の7割は腸内環境にある
順天堂大学医学部教授・小林弘幸さんは、体が健康な状態を保つためには、
「腸内環境」、「自律神経」、「ストレス解消」のトライアングルが重要だと指摘する。
「自律神経がよくなると腸内環境が整い、腸内環境が整うとストレスも軽減するといったように、
3つはそれぞれが影響しあっています。
例えば、腸内環境が良好であれば、
幸せホルモンと呼ばれるセロトニンやオキシトシンが増えて、
ストレスが軽減されます。
ストレスが減ると自律神経のバランスが改善され、
体の抵抗力も上がります。
相互に関係しているので、どれか1つでも悪化すると、免疫が低下します。
特に、免疫の7割は腸内環境が影響しているといわれており、
まずは腸内環境を整えるといいでしょう。
腸にあるTレグ細胞と呼ばれる免疫の恒常性を維持するうえで、重要な役割を果たす細胞が少ない人は、新型コロナウイルスに感染しやすく、重症化しやすいという報告もあります」
6.食べすぎ厳禁! 腹七分目
小林さんによれば、腸内環境を整えるいちばんの方法は、
「バランスよく食べるが、決して食べすぎない」ことだという。
「腸内環境を整えるには、食物繊維や発酵食品を意識して、
3食きっちり食べるようにしましょう。
ただし食べすぎは禁物。
腹八分目という言葉がありますが、理想は『腹七分目』。八分目だと満腹感がありますが、満腹な状態というのは体が消化にエネルギーを費やすので、腸にストレスをかけてしまうのです。 毎食、腹七分目を意識するといいでしょう」
7.「吸う1:吐く2」呼吸で自律神経を整える
腸内環境がケアできたら、次は自律神経を整えたい。
小林さんは、「自律神経を整えるいちばんの方法は、呼吸」だとつけ加える。
「ストレスがかかると呼吸が浅くなり、体内に取り込む酸素の量が減るため、
免疫力は大幅に下がってしまう。
理想は、吸う息よりも、吐く息が倍の長さになる“1対2の呼吸”です。
特に、長くゆっくり息を吐くことで、自律神経が安定します。
ただし、普段の呼吸から常にゆっくり吐く必要はありません。
朝昼晩や寝る前など、1日3回程度、
数分間でいいので呼吸を整える時間を作ってください」(小林さん)
「ストレス解消」については、コロナ禍のいま、多くの人が難しい状況に直面しているだろう。
「気分転換もできずに不安なニュースばかりで、
ストレスを強く感じている人は多いと思います。
しかし長引くストレスは免疫力にとって悪い影響を及ぼして、
ほかの病気を引き寄せる可能性すらあります。
さまざまな情報を集めたくなりますが、
例えば眠る前2時間はスマートフォンやテレビを見ないなど
意図的に暗いニュースをシャットアウトする工夫をしてみてほしい」(小林さん)
 9.早歩きを10分で免疫力アップ
9.早歩きを10分で免疫力アップ
「トライアングル」を意識した生活で免疫を上げたら、
今度は下がらないように留意したい。
新潟大学名誉教授 医師・岡田正彦さんは、
免疫力を下げてしまう要因として、5つの生活習慣を挙げる。
「免疫を低下させる生活習慣は、
運動不足、喫煙、肥満、お酒の飲みすぎ、栄養バランスの偏りの5つです。
これらの生活習慣を続けると、本来持っている免疫力を下げてしまいます。
特に高血圧の人は、私の経験や欧米の論文から見ると、
運動が最も病気を治す力を高めると考えられます」
芝大門いまづクリニック院長の今津嘉宏さんも
「運動は免疫力を下げないようにするうえで重要」と声を揃える。
「運動はまったくしなくても、激しすぎても免疫力を下げてしまいます。
脈拍数が100前後になるくらいの、体に少し負担がかかる内容がおすすめです。
目安は汗ばむ程度の早歩きを10分程度。
気温が高くない早朝や夕方以降に行うのがいいでしょう」
ほどよい食と運動がいちばんのクスリと言えそうだ。・・》注)記事の原文に、あえて改行を多くした。

私は記事を読みながら多々教示させられたりした。
私は年金生活の中で、熱い夏でも原則として散策し、
私の夏模様として、容姿は制服のようになった半袖のスポーツシャツ、或いはアロハシャツ、
長ズボン、そして夏の帽子を深くかぶり、サングラスを掛け、ウォーキング・シューズで足元を固め、
そして紳士バックを園児のように斜め掛けにして、颯爽と歩いたりしている。
しかしながら陽射しが燦燦と照らす青空の中、歩いたりすると汗ばみ、
ハンドタオルで顔をふいたりし、ときおり扇子を取りだして扇(あお)いだりしているが、
汗がひたたり落り、微苦笑したりしている。
やむなくハンドタオルで顔などを拭いながら、できる限り樹の下にある歩道を歩いているが、
炎天下の道もあるので、高齢者の私でも、人生は気合いだ、と自身を叱咤激励をしたり、
或いは冬の寒さを思い浮かべて、 足早に歩いているのが実情である。

やがて休憩ねぇ、と思いながら、小公園に寄り、幾重か大きな樹の下にあるベンチに座り、
コンビニで買い求めたペットボドルの煎茶を飲み、水分補給をしたりしている。
こうした根底には、高齢者は、脱水を起こしやすい要素をいくつも持っていて、
放置すると、寝たきりや認知症を招く結果になりかねない、と学んだりしてきた。
そして脱水にならないことは、やはり喉の渇きを感じる前に、
こまめに水分補給は大切だ、 と思いながら実施してきた。

こうした中、暑い32度前後を超えた熱い時の場合は、我が家の平素の買物専任者の私、
やむなく利便性の良い路線バスに乗り、バスの車内の冷気に甘えて、帰宅することもある。
或いは自宅の3キロ範囲にある遊歩道、公園、住宅街の歩道を少なくとも一時間以上は散策しているが、
熱い中は近回りして、30分ぐらいとなっている。
もとより高齢者の私が、熱中症で倒れて救急車で搬送されて、
気が付いたら病院のベットの上だったことは、 私も困苦するし、
世の中の多く御方にご迷惑するので、私なりに自己防衛策としている。

このように私は過ごすことが多いが、もとより健康でなければ、自身の日頃のささやかな願いも叶わないので、
歩くことが何より健康体の源(みなもと)と思い、そして適度な熟睡する睡眠、或いは程ほどの食事が、
セカンドライフの私なりの健康体の三種の神器として思い、年金生活丸16年近く過ごしてきた。
今回、病気に負けない9つの免疫力アップ術を学び、
私の昨今の欠点である食べ過ぎに注意すれば、もしかしたら健康寿命の身で、
あと4年後に80歳のお誕生日を迎えられるかしら、と微笑んだりしている。