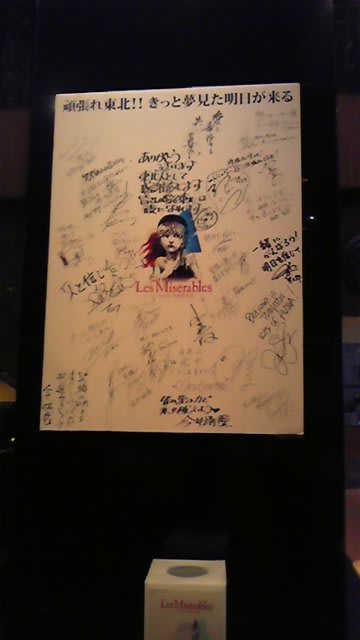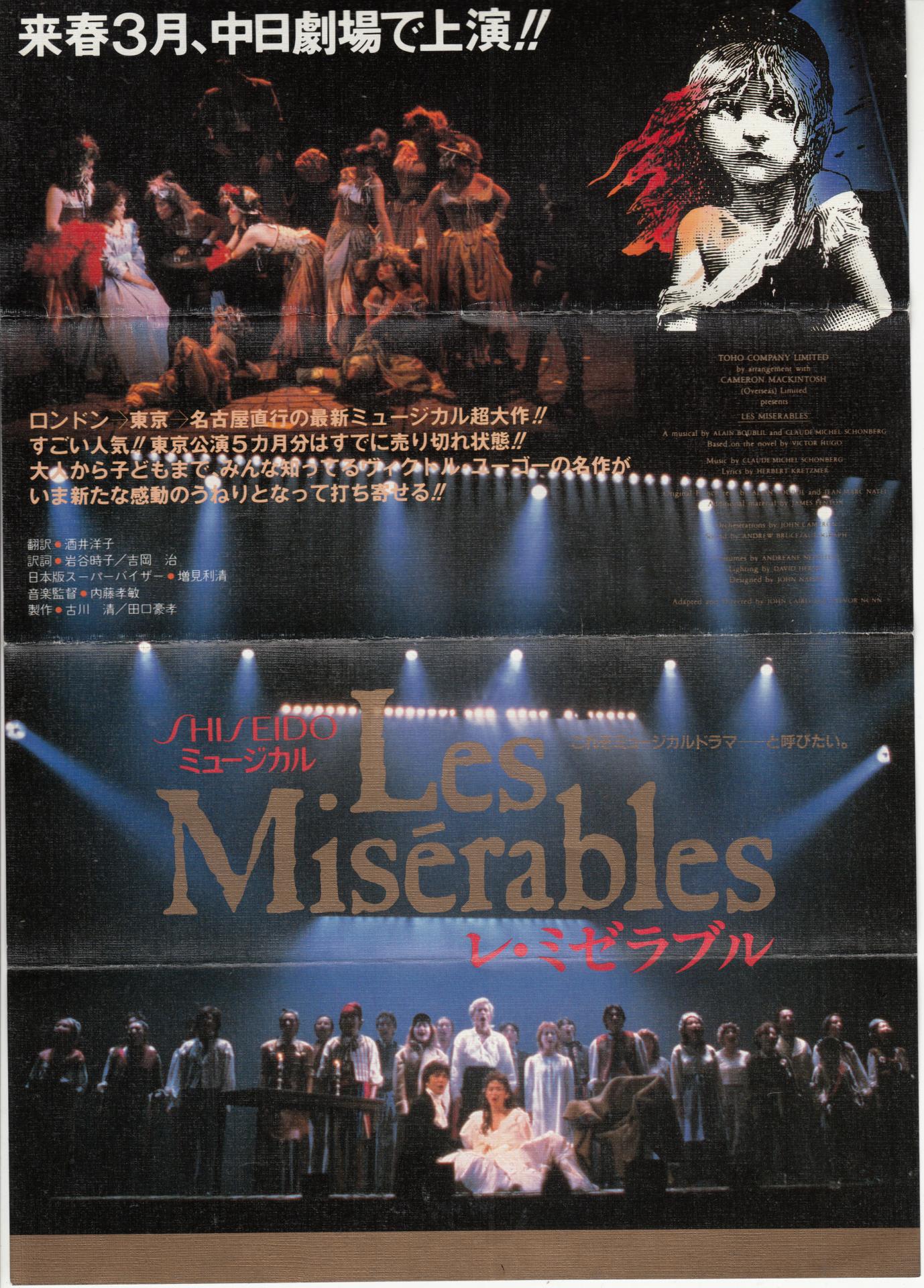「1815年、ツーロン。ジャン・バルジャンは19年の刑期を終え、仮釈放されます。
住むところも働き口もないバルジャンは、司教から銀の食器を盗み警察に捕まりそうになりますが、司教に救われ改心を誓います。
1823年モントルイユ・シュール・メール。バルジャンは過去を隠して市長になり、
工場を経営しています。バルジャンは、騒ぎを起こしてジャベールに逮捕されそうになっていたファンティーヌに出会いますが、彼女はほどなくして病に倒れます。バルジャンは病床で、彼女の一人娘のコゼットを育てていく決心をし、ファンティーヌを看取ります。バルジャンの過去を知るジャベールは彼を執拗に追いかけますが、バルジャンはファンティーヌとの約束を果たすため、ジャベールから逃げ続けます。
1832年、パリ。街は混沌とし、テナルディエ夫妻が悪事を働いています。
娘のエポニーヌは学生マリウスに恋をしていますが、マリウスはテナルディエに襲われそうになっていたコゼットに一目ぼれします。その頃、学生たちはアンジョルラスをリーダーに集会を開き、政府軍に立ち向かうことを決心していました。
動き始めたそれぞれの運命。バルジャンはジャベールから逃げ続けられるか?」
「『レ・ミゼラブル』の舞台は19世紀前半のフランス。フランス革命後の政情は非常に不安定なものであり、共和政(国民主権)→帝政(ナポレオン)→第一次王政(ルイ18世)→第二次王政(ルイ=フィリップ)と、次々と国の主権が入れ替わっていきました。
ルイ18世の王政は、貴族や聖職者を優遇した、まったく民衆の生活を無視したものでした。
貧しい家に生まれた者の暮らしは厳しく、18世紀末の肉体労働者の平均時給は2スー(100円)。パンの値段は5スー(250円)ですから、失業は即、飢えを意味していました。経済面での市民の不満が高まると他国へ戦争を仕掛けるのは今も昔も変わったことではなく、ルイの後を継いだシャルルは、1830年にアルジェリアを侵略。これが更に市民の不満を高め、「七月革命」が起きます。
これは、『レ・ミゼラブル』第二幕最大の見せ場となる1832年の「六月暴動」へと繋がっていきます。ちなみに、ドラクロワ作『民衆を導く自由の女神』の絵で銃を持った少年は、子供ながら自ら革命に参加するガブローシュのモデルになったと言われています。」
(「レ・ミゼラブルを5分で10倍楽しむガイド」より引用しました。)
オリジナル版最終公演を観劇した時のキャストを振り返ってみるとこんな感じでした。
いろいろと思い出しますが、また別の機会にします。
別所さんと今井さん、それぞれ舞台の上で生き抜いたバルジャン、
KENTAROさんジャベールの執拗さと冷徹さなど心に残っています。
三波さんのティナルディエはどうして今までやっていなかったの?と不思議なぐらいのいやらしさでした。マダム・ティナルディエは阿知波さんでした。
エミリちゃんのコゼットは可愛らしく、上原さんのアンジョルラスはあまりにも似合いすぎていてかっこよかった・・・などきりがありません。
2011年5月14日帝国劇場夜の部
バルジャン:別所哲也
ジャベール:KENTARO
エポニーヌ:笹本玲奈
ファンテーヌ:新妻聖子
コゼット:中山エミリ
マリウス:野島直人
テナルディエ:三波豊和
テナルディエの妻:阿知波悟美
アンジョルラス:上原理生
2011年6月7日帝国劇場夜の部
バルジャン:今井清隆
ジャベール:今拓哉
エポニーヌ:笹本玲奈
ファンティーヌ:新妻聖子
コゼット:中山エミリ
マリウス:山崎育三郎
テナルディエ:駒田一
テナルディエの妻:阿知波悟美
アンジョルラス:上原理生
写真は2013年新演出版の清史郎君ガブローシュ。
(東宝の公式ツィッターより転用しています。)
子役ながら役者魂を感じさせてくれます。帝劇凱旋公演のチラシにも使われました。
2011年の初舞台の時は、小さい体で精一杯すばしっこくパリの街を駆け回るガブローシュを体現している感じでしたが、2013年の舞台では、『エリザベート』の子ルドルフを経て、歌がすごく上手になり、「パリの街はガブローシュに任せておけよ」とすごく大人なガブローシュでした。もう観ることができなくて少しさびしいです。大きくなってまた戻ってきてほしいな。
今年の春の公演に向けてキャストが発表になっていることもあり、すごくまたレミゼに心が戻っているこの頃です。

住むところも働き口もないバルジャンは、司教から銀の食器を盗み警察に捕まりそうになりますが、司教に救われ改心を誓います。
1823年モントルイユ・シュール・メール。バルジャンは過去を隠して市長になり、
工場を経営しています。バルジャンは、騒ぎを起こしてジャベールに逮捕されそうになっていたファンティーヌに出会いますが、彼女はほどなくして病に倒れます。バルジャンは病床で、彼女の一人娘のコゼットを育てていく決心をし、ファンティーヌを看取ります。バルジャンの過去を知るジャベールは彼を執拗に追いかけますが、バルジャンはファンティーヌとの約束を果たすため、ジャベールから逃げ続けます。
1832年、パリ。街は混沌とし、テナルディエ夫妻が悪事を働いています。
娘のエポニーヌは学生マリウスに恋をしていますが、マリウスはテナルディエに襲われそうになっていたコゼットに一目ぼれします。その頃、学生たちはアンジョルラスをリーダーに集会を開き、政府軍に立ち向かうことを決心していました。
動き始めたそれぞれの運命。バルジャンはジャベールから逃げ続けられるか?」
「『レ・ミゼラブル』の舞台は19世紀前半のフランス。フランス革命後の政情は非常に不安定なものであり、共和政(国民主権)→帝政(ナポレオン)→第一次王政(ルイ18世)→第二次王政(ルイ=フィリップ)と、次々と国の主権が入れ替わっていきました。
ルイ18世の王政は、貴族や聖職者を優遇した、まったく民衆の生活を無視したものでした。
貧しい家に生まれた者の暮らしは厳しく、18世紀末の肉体労働者の平均時給は2スー(100円)。パンの値段は5スー(250円)ですから、失業は即、飢えを意味していました。経済面での市民の不満が高まると他国へ戦争を仕掛けるのは今も昔も変わったことではなく、ルイの後を継いだシャルルは、1830年にアルジェリアを侵略。これが更に市民の不満を高め、「七月革命」が起きます。
これは、『レ・ミゼラブル』第二幕最大の見せ場となる1832年の「六月暴動」へと繋がっていきます。ちなみに、ドラクロワ作『民衆を導く自由の女神』の絵で銃を持った少年は、子供ながら自ら革命に参加するガブローシュのモデルになったと言われています。」
(「レ・ミゼラブルを5分で10倍楽しむガイド」より引用しました。)
オリジナル版最終公演を観劇した時のキャストを振り返ってみるとこんな感じでした。
いろいろと思い出しますが、また別の機会にします。
別所さんと今井さん、それぞれ舞台の上で生き抜いたバルジャン、
KENTAROさんジャベールの執拗さと冷徹さなど心に残っています。
三波さんのティナルディエはどうして今までやっていなかったの?と不思議なぐらいのいやらしさでした。マダム・ティナルディエは阿知波さんでした。
エミリちゃんのコゼットは可愛らしく、上原さんのアンジョルラスはあまりにも似合いすぎていてかっこよかった・・・などきりがありません。
2011年5月14日帝国劇場夜の部
バルジャン:別所哲也
ジャベール:KENTARO
エポニーヌ:笹本玲奈
ファンテーヌ:新妻聖子
コゼット:中山エミリ
マリウス:野島直人
テナルディエ:三波豊和
テナルディエの妻:阿知波悟美
アンジョルラス:上原理生
2011年6月7日帝国劇場夜の部
バルジャン:今井清隆
ジャベール:今拓哉
エポニーヌ:笹本玲奈
ファンティーヌ:新妻聖子
コゼット:中山エミリ
マリウス:山崎育三郎
テナルディエ:駒田一
テナルディエの妻:阿知波悟美
アンジョルラス:上原理生
写真は2013年新演出版の清史郎君ガブローシュ。
(東宝の公式ツィッターより転用しています。)
子役ながら役者魂を感じさせてくれます。帝劇凱旋公演のチラシにも使われました。
2011年の初舞台の時は、小さい体で精一杯すばしっこくパリの街を駆け回るガブローシュを体現している感じでしたが、2013年の舞台では、『エリザベート』の子ルドルフを経て、歌がすごく上手になり、「パリの街はガブローシュに任せておけよ」とすごく大人なガブローシュでした。もう観ることができなくて少しさびしいです。大きくなってまた戻ってきてほしいな。
今年の春の公演に向けてキャストが発表になっていることもあり、すごくまたレミゼに心が戻っているこの頃です。