えーまだ引っ張るの、って…
だって書きたいことが終わんないんだもん。
 ←遅いからってやめなくてもよかったんだよね
←遅いからってやめなくてもよかったんだよね
で、そのように「昭和なピアノ教室」…つまり、
決まったカリキュラムがあって
(バイエル→ブルグミュラー→ツェルニー30番、というような)
先生が指定したものを練習して持って行く、
先生からマルもらって先に進む、
たまたま近所に住んでるふつうの子が通う。
というような教室を想定してください。
モデルは便宜的に、私の母がやっていた教室とさせていただきます。
今の世の中においては不人気な教室となりそうですが、よいところもありました。
乱暴な音を出してる子とか、リズムがぐだぐだな子とかはいなくて、「きれいに」「きちんと」弾けてたと思います。
譜面も読めるようになります。
要するに、身に着けるべき技能をしっかり練習しつつ、古典中心に曲を進めていくんですよね。
別にスパルタとか体育会ノリじゃなかったんで、
・○時間練習してこいと言われた
・○回弾けと言われた
・メトロノームいくつまで上げてこいと言われた
みたいなトラウマっちゃった人はいないと思います。
それでも、音楽の道に進んだ人はけっこういました。演奏家として身を立ててるわけじゃなくて、いわゆる「ピアノ科を出て自宅でピアノ教室」という路線が多いようですが。
ということで、ちゃんとそれなりの存在意義がある教室だったと思います。
一方、こういうピアノ教室の弱点はというと、
まずは、きちんとしてるけどつまんない演奏が多かったことかな?
曲をとりあえず丁寧に正しく弾くということについてはしっかり教えていたと思いますが、それプラス何を考えて弾けば聞く人にサムシングが伝わる演奏になるのかという…そこ。
それは、教えるようなものではないと思われていたような気がするんです。
もちろん、全員が正確で平板な演奏をしていたのではなくて、なんかおもしろい、魅力的な演奏をする子もいるんです。でもそれは、その子がたまたま持っていた才能というかセンスというか。つまり、「きちんと」弾くことは教えられること、それ以外の「音楽する」部分は本人次第。という考え方があったのではないでしょうか。
もうひとつ、決定的な弱点は、落ちこぼれを作るということです。
一本の物差しに従って、早い遅いで進んでいきますから、遅い子はやめていきます。
別にただの習い事なんで、向いてない、好きでない子が途中でやめちゃうのは当然で、それでいいんですが、でも考えてみてください。
私みたいに「才能」豊かな…つまり、音楽をこんなに長きにわたって楽しめる資質をもった子を(笑)「向いてないからもうやめる」と思わせてふるい落としちゃう教育だったんですよ!!
それってもったいないじゃないですか。
遅くてもいいんだよ。
一本の道から外れてもいいんだよ。
と今なら思う。でもその発想はなかった。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)
だって書きたいことが終わんないんだもん。
で、そのように「昭和なピアノ教室」…つまり、
決まったカリキュラムがあって
(バイエル→ブルグミュラー→ツェルニー30番、というような)
先生が指定したものを練習して持って行く、
先生からマルもらって先に進む、
たまたま近所に住んでるふつうの子が通う。
というような教室を想定してください。
モデルは便宜的に、私の母がやっていた教室とさせていただきます。
今の世の中においては不人気な教室となりそうですが、よいところもありました。
乱暴な音を出してる子とか、リズムがぐだぐだな子とかはいなくて、「きれいに」「きちんと」弾けてたと思います。
譜面も読めるようになります。
要するに、身に着けるべき技能をしっかり練習しつつ、古典中心に曲を進めていくんですよね。
別にスパルタとか体育会ノリじゃなかったんで、
・○時間練習してこいと言われた
・○回弾けと言われた
・メトロノームいくつまで上げてこいと言われた
みたいなトラウマっちゃった人はいないと思います。
それでも、音楽の道に進んだ人はけっこういました。演奏家として身を立ててるわけじゃなくて、いわゆる「ピアノ科を出て自宅でピアノ教室」という路線が多いようですが。
ということで、ちゃんとそれなりの存在意義がある教室だったと思います。
一方、こういうピアノ教室の弱点はというと、
まずは、きちんとしてるけどつまんない演奏が多かったことかな?
曲をとりあえず丁寧に正しく弾くということについてはしっかり教えていたと思いますが、それプラス何を考えて弾けば聞く人にサムシングが伝わる演奏になるのかという…そこ。
それは、教えるようなものではないと思われていたような気がするんです。
もちろん、全員が正確で平板な演奏をしていたのではなくて、なんかおもしろい、魅力的な演奏をする子もいるんです。でもそれは、その子がたまたま持っていた才能というかセンスというか。つまり、「きちんと」弾くことは教えられること、それ以外の「音楽する」部分は本人次第。という考え方があったのではないでしょうか。
もうひとつ、決定的な弱点は、落ちこぼれを作るということです。
一本の物差しに従って、早い遅いで進んでいきますから、遅い子はやめていきます。
別にただの習い事なんで、向いてない、好きでない子が途中でやめちゃうのは当然で、それでいいんですが、でも考えてみてください。
私みたいに「才能」豊かな…つまり、音楽をこんなに長きにわたって楽しめる資質をもった子を(笑)「向いてないからもうやめる」と思わせてふるい落としちゃう教育だったんですよ!!
それってもったいないじゃないですか。
遅くてもいいんだよ。
一本の道から外れてもいいんだよ。
と今なら思う。でもその発想はなかった。
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)










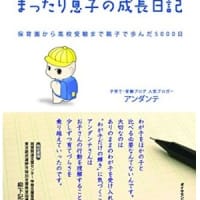












楽しそうな曲が多かったけど、息子たちはあまりうまくならないうちに先生がお嫁に行かれてそのままやめてしまいました。長男は大学に入って軽音に入り、「楽譜が読めない。ピアノを続けさせてほしかった、とこぼしました。小 中 高と学校の音楽の授業を考えると、昭和のピアノ教室も悪くなかったと思います。
一本の道から外れて落ちこぼれになり小学生でやめたわたしも、今では、下手でもとても楽しくピアノを弾いています。
昭和の教育を受けた先生も、考え方を柔軟にする必要があっただろうし、教師側の意見も知りたくなりました。
個人レッスンでは昭和なカリキュラムでバイエルとかツェルニー30番とかもやるんですけど、グループレッスンで適当にコードつけてアンサンブルとか即興演奏とかやるのが楽しかったです。
中にはそんなレッスンでもピアノがかなり上達して、音大を目指すためにオーソドックスなピアノ教室に変わる子もいましたが(うちの妹はそうでした。結局音大には行きませんでしたが)、ヤマハ出身の子は音楽遊びばっかりやってて基礎がなってない!ということで、スパルタ式で叩き直されて大変そうでした。
私は結局ピアノ演奏の基礎がなってないまま卒業しちゃいましたが、音楽を楽しむ基礎はしっかりできたので、ヤマハで良かったのかなと思ってます。
今はヤマハにもマスタークラスとかできていて、ヤマハの中で音大を目指すようなレッスンも受けられるようになってるみたいですね。
感覚的には「いまどき」ですけど、そうやって教則本に従って丁寧にやろうとするのは、対立する二つのメソッド的にいうと「伝統的」側です(笑)
楽譜が読めないのは、バスティンのせいっていうかお嫁に行っちゃったせいっていうかそのあと別の先生でいいから続けなかったせいっていうか、まぁよくわかんないですけど、とにかく軽音やってるからには音楽は好きになったのよね(^^) そしたらまぁ8割くらいは成功かな(?)
なんとなく迷走してますがまだ書きたいことあるんですよこれが。ほかの話題も順次挟みますが…
昔の一本道を挫折した人の中から、たくさんの音楽好きはちゃんと育ってますよね。ブランクはだいぶ長かったかもしれないけれど。
ピアノ演奏の基礎としてはあんまりうまく立ち上がらないことが多いと思いますが、みっちりやりたい人は個人レッスンと組み合わせてやりますよね。