なんか「くもん」って打つと苦悶しちゃうんだよね(^^;;
 ←またろうの数学ピンチ!?
←またろうの数学ピンチ!?
高専生(の数学)と公文っていうのは、ある意味では相性がいいと思う。高二とかで塾にいったらそこはもうまっしぐらに大学受験に向かっているわけで、空気が違いすぎる。
個別塾に行く手はあるけど、別にべったり説明してほしいというわけではなくて、自分の「ちょうど」のところを演習するペースを作りたいだけだから、お値段からいっても公文という選択はリーズナブルだ。
実際、数学で進級が危なくなった子が、公文するようになって助かったという話もあるし、趣旨としてはかなり馴染みがよいと思う。ただ…
「ちょうど」をやるというのはあまり実際問題簡単ではなく、なにしろ並び順がえらく違うので、よほど余裕を持って下のレベルをやっておかないと、ふと未修分野が出てくることになる。
先取りで有名な公文だけれど、小学校レベルの四則計算ならいざ知らず、高校数学の未修分野自習教材としてはぜんぜん公文はうまくできてない。ついこの間やった私が言うんだから間違いない(^-^) 私は、いくら苦手といっても昔一度は通った道なので、「はぁー、あれのことかい」と太古の記憶を呼び覚ますことができて、それはそれで楽しい。それでもときどき「???」と思う問題はあるし、そういう場合何を頼るかというと難しい。
普通の場合、公文の先生は高校数学に詳しいわけではないし、先生が説明するようには(そういう時間を取るようには)設定されていない。またろうの通う教室で行われているのは、どうしてもわからないと、丸付け用の解説書を貸してくれるという対応なのだが、これは家に持ち帰ることができない。それに自習用の解説でもないのでピントは少しずれる。
公文の高進度者は、もっと若いというか幼くして高校教材に突入するわけで、いったいその場合どうしているのか知らないが、そういう子は第一ものすごい集中力と粘りがあって(^^;; 凡百の子たちの直接の参考にはならない。実際のところ、チャート式など別教材も併用して乗り切っているとも聞くが。
またろうの場合、N教材に突入したら非常に頻繁にわからない問題に当たることが増え、一時期はよく母を呼びつけたりしてたもんだけど、そのうちあまりそういう問題の密度が増えると、呼ばなくなった。
どうするかというと、宿題はやらずにほっておいて、公文に行ったときに解説書を見て進めるわけだ。現状、週一回しか通ってないのにすごい贅沢な使い方ですこと。
昨日は、公文をやらずにこじろうとカードバトルをしていて、母が聞いたら「公文は済んだ」といい、実際のところ手付かず。母が実物を見せてもらって言い訳が効かなくなると、「できないんだよ!!」「無理だよ!!」逆ギレ。
見ると無限級数のところで、ちょいとコツをつかめばどうってことないし計算量もたいしたことないのだが、なんか感触がつかめなかったらしい。そこで速やかに挫折するのがまたろうのまたろうたるゆえんなのだが。とりあえず昨日は、母がつきっきりになってヒントを適宜出してがしがし進めると、数ページぱたぱたと先へ行った。
しかしいつもこんなことをしているわけにはいかないし…第一、母の予習はもうすぐ尽きることになっている(公文をやめてしまったので)。
それで話し合って、いくつかの方針案を。
・戻す。M教材またはN教材の最初に。
・飛ばす。年明けの微分積分テストに合うところに飛んで、演習。
・解説書を貸してもらう。←たぶん貸すほどないからダメ
・公文をやめて、代わりに学校教材で日々の演習をする。
四つ目は、一番根本的な解決ともいえるが、またろうは公文の場が好きなようで、あの空間で課題に取り組むことが週のリズムとして入っていることや、馴染みの先生に声をかけてもらったりということをやめたくないようだ。公文はある意味、またろうの大きな成功体験の場でもあったので、気持ちはわからなくないけど。
にほんブログ村 ヴァイオリン ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ピアノ ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育
今日の弁当

↑またろう

↑こじろう
微妙に中身が違うのは、具材が人数分なかったため。面倒。
高専生(の数学)と公文っていうのは、ある意味では相性がいいと思う。高二とかで塾にいったらそこはもうまっしぐらに大学受験に向かっているわけで、空気が違いすぎる。
個別塾に行く手はあるけど、別にべったり説明してほしいというわけではなくて、自分の「ちょうど」のところを演習するペースを作りたいだけだから、お値段からいっても公文という選択はリーズナブルだ。
実際、数学で進級が危なくなった子が、公文するようになって助かったという話もあるし、趣旨としてはかなり馴染みがよいと思う。ただ…
「ちょうど」をやるというのはあまり実際問題簡単ではなく、なにしろ並び順がえらく違うので、よほど余裕を持って下のレベルをやっておかないと、ふと未修分野が出てくることになる。
先取りで有名な公文だけれど、小学校レベルの四則計算ならいざ知らず、高校数学の未修分野自習教材としてはぜんぜん公文はうまくできてない。ついこの間やった私が言うんだから間違いない(^-^) 私は、いくら苦手といっても昔一度は通った道なので、「はぁー、あれのことかい」と太古の記憶を呼び覚ますことができて、それはそれで楽しい。それでもときどき「???」と思う問題はあるし、そういう場合何を頼るかというと難しい。
普通の場合、公文の先生は高校数学に詳しいわけではないし、先生が説明するようには(そういう時間を取るようには)設定されていない。またろうの通う教室で行われているのは、どうしてもわからないと、丸付け用の解説書を貸してくれるという対応なのだが、これは家に持ち帰ることができない。それに自習用の解説でもないのでピントは少しずれる。
公文の高進度者は、もっと若いというか幼くして高校教材に突入するわけで、いったいその場合どうしているのか知らないが、そういう子は第一ものすごい集中力と粘りがあって(^^;; 凡百の子たちの直接の参考にはならない。実際のところ、チャート式など別教材も併用して乗り切っているとも聞くが。
またろうの場合、N教材に突入したら非常に頻繁にわからない問題に当たることが増え、一時期はよく母を呼びつけたりしてたもんだけど、そのうちあまりそういう問題の密度が増えると、呼ばなくなった。
どうするかというと、宿題はやらずにほっておいて、公文に行ったときに解説書を見て進めるわけだ。現状、週一回しか通ってないのにすごい贅沢な使い方ですこと。
昨日は、公文をやらずにこじろうとカードバトルをしていて、母が聞いたら「公文は済んだ」といい、実際のところ手付かず。母が実物を見せてもらって言い訳が効かなくなると、「できないんだよ!!」「無理だよ!!」逆ギレ。
見ると無限級数のところで、ちょいとコツをつかめばどうってことないし計算量もたいしたことないのだが、なんか感触がつかめなかったらしい。そこで速やかに挫折するのがまたろうのまたろうたるゆえんなのだが。とりあえず昨日は、母がつきっきりになってヒントを適宜出してがしがし進めると、数ページぱたぱたと先へ行った。
しかしいつもこんなことをしているわけにはいかないし…第一、母の予習はもうすぐ尽きることになっている(公文をやめてしまったので)。
それで話し合って、いくつかの方針案を。
・戻す。M教材またはN教材の最初に。
・飛ばす。年明けの微分積分テストに合うところに飛んで、演習。
・解説書を貸してもらう。←たぶん貸すほどないからダメ
・公文をやめて、代わりに学校教材で日々の演習をする。
四つ目は、一番根本的な解決ともいえるが、またろうは公文の場が好きなようで、あの空間で課題に取り組むことが週のリズムとして入っていることや、馴染みの先生に声をかけてもらったりということをやめたくないようだ。公文はある意味、またろうの大きな成功体験の場でもあったので、気持ちはわからなくないけど。
にほんブログ村 ヴァイオリン ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ピアノ ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育
今日の弁当

↑またろう

↑こじろう
微妙に中身が違うのは、具材が人数分なかったため。面倒。










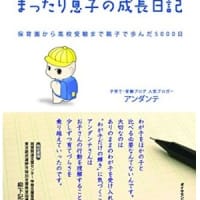












毎日楽しく読ませていただいてます。
うちにもN教材をやっている息子がいますがLの終わり位から自分ですすめるのが困難になり親がヒントを小出しにしつつ二人三脚で進みましたがあまりに時間をとられるので親が挫折。
今は解説書(解法の手引き)を見ながら一人でやってます。(解説書は貸してくれて持ち帰りも可)実は私自身も昔の修了生なのですが先生が全く教えられなかったので手引きをもらっていました。でも高校生位になるときちんとしているのでしょうが、私も含めて小中学生はついつい”写して終わり、、”になりがちで今公文を続けるかどうか悩んでいます。
またろう君は手引きを読んでちゃんと自分で進められるのなら手引きを一部購入されたらどうでしょうか?私の先生および息子の先生は”教えられないから””同じ教材をやっている子がいなく他に使う子はいないから”と教室の予算で購入して貸してくれました(くれています)が、他の教室の方によると自分で持ち帰る分は自費で購入(先生を通して)されている方が多いみたいですよ。
>公文はある意味、
>またろうの大きな成功体験の場でもあったので
こういう奥の奥まで読んであげられるアンダンテさんはやっぱりすごいと思いますよ。
やっぱり「習い事」って、成果が目に見えない(ように見える)と資金を出している方はアレコレ言いたいものですし、
「もう辞めよう」「別の方法を考えよう」と言う方が親もよっぽどラクだったりしますもの。
息子は中3で受験生ですが 学校でトップレベルの子が公文高進度なのに触発され 小学生の時にやっていた公文を 中2後半から数学のみ再開しています(本人の意思)
今は学校の進度と関係ないところ Jを進んでいるので 私は趣味の公文と呼んでいますが 計算に向き合う時間が増えたせいかミスが減り 学校の定期試験の成績等が安定しました
一時期МMをやっておくと受験に役立つとのことで 解説書をいただいてやってました
解説書が手元にあれば いいかもしれないです
計算が早くなった程度で終わらせればよかったと後悔しています。
4番の選択肢が一番理想的ですよね。
高専の先生は、「試験の時に一番頼れるのは友達だ」と言っていました。
教科書の演習問題には答えしか載っていませんが、ネット上で途中式などが公開されているので、みなそれを活用していますよね。
あとは友達同士でSkypeなども使って教えあっているようです。パソコンにカメラがあれば、顔も見れるし、ノートに解法の手順を書いて教えてもらうことができます。うちはもっぱら教わるほうばかりですが。
手引き書を見て、自分の身になるように勉強できるかどうかが鍵ですね。見て写すのも悪くはないですが、それから見ないで解けるかどうか確認していかないとね。
ほら、「毎日こつこつと」からは一番遠いところに生息するまたろうでしょ。そのまたろうに、公文は、何事かをしてくれたんですよね。
自分は勉強がたいしてできないと思っていた中一、中ニのときから、公文を始めて数学ごぼうぬきで脅威の偏差値アップしていった経験は、本人も自信になったと思うんです。で、今、本人が、公文という形で続けたほうがいいような気がする、といっているので、それでうまくいく方法があれば合わせてやったほうがいいのかもしれないと思ってます。
進んでくると、解説書つきで取り組むのって、わりとあることのようですね。とりあえずその手でいくかな…
あんずさんの息子さんは、高専生活が軌道に乗っているようですね。
> あとは友達同士でSkypeなども使って教えあっているようです。
すごい!!(o_o)
随分前にセシールの靴下のお話をさせていただいたものです。
公文の解説書、130円ですよ。
私は毎回購入してます。
おぉ、130円なら即買いですね。私も見たいところがあったんだ~