The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
安倍政権の“言葉の使い方”について
日本の自衛権については、従来から歴代の政権は“個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は憲法の容認する自衛権の限界を超える”との見解を示して来た。安倍政権は、その集団的自衛権を行使するために憲法解釈を変えると言いだしていて、着々と歩を進めている。それに対して、多くの識者は懸念を表明している。何よりも連立与党の公明党が難色を示している。
さて、その“集団的自衛権”とは一体 どういうものなのだろう。
当初、自民党(確か石破現幹事長だった?)のたとえ話で聞いていたのは、公海上で日本の防衛に協力する同盟軍つまり米軍の艦船が、自衛隊の艦艇と行動を共にしていたのが日本の敵対国から攻撃された場合、集団的自衛権を行使できない自衛隊は、この米軍の艦船を守るべく攻撃できない。こういう奇妙な状況を打破するためには、集団的自衛権を行使できるようにしなければならない、というものだったと了解していた。したがい、私は 集団的自衛権に関し それほど問題のあるものとは考えていなかった。
ところが、そういう先入観で先日“朝まで生テレビ”を見ていたところ、議論について行けず、面食らったのだった。
そこで、改めて“集団的自衛権”について、ネットで調べてみた。すると、“英語:ではright of collective self-defense、と言い、他の国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある。”とある。また国連憲章第51条により、個別的、集団的自衛権は日本も持てるものとあった。
*国連憲章第51条では次のように規定。“この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。”
どうやら、“集団的自衛権”が想定している事態は、具体的には米国が“9・11での敵”とするアルカイーダの拠点のアフガニスタンのある地域を一部の親米国と共同で攻撃する権利があるということになるらしい。ならば、英語を直訳すればなるほど、“集団的自衛権”となるのかも知れないが、実際は“集団的攻撃権”と称した方が本来のイメージには近いのではないかと思うのだ。
つまり、“集団的自衛権”とは、誰かにいきなり殴られた男が、今度は仲間を引き連れて殴ってきた相手に逆襲する、その場合の仲間の参加を正当化するための法的権利ということになる。そんなことに、憲法で“交戦権を放棄”した日本が参加する合理性・合法性はあるのだろうか。否、憲法解釈の変更で“集団的自衛権”が持てることになるのだろうか。
先述した自民党(石破現幹事長?)が挙げていた“集団的自衛権”の説明事例での“公海”についてのイメージを、“日本近海の公海上”と私が勝手に想像していたのが、どうやら間違っていたようである。確かに最近、自民党側から“集団的自衛権行使のために‘地球の裏側まで行く’というようなことはない”と言明したというのは、そういうことに対応しているものと理解できる。
私が誤解したのは、一つには言葉の使い方にも惑わされたのではないかと思うのだ。それは、英訳では、“集団的自衛権”となるのだが、内実は“集団的攻撃権”であり、そのように言われていれば注意するはずの政策だったのだ。
そういう理解の後、ビデオに撮っていた“朝まで生テレビ”を改めて見直してみると、驚くほど議論の内容にすんなりと入って行けたのだ。“集団的自衛権”の内実は“集団的攻撃権”であるというのは、識者の間では常識だったのだ。
となると日本の“集団的自衛権”とは、米国が敵と見做した相手については、地球上のどの地点に居ても、これを日本の“敵でもあると見做すことができる”ことになる。この敵と認定する部分が、“権利”であるのか“義務”となるのかで、日本の立ち位置はさらに大きく変化する。“権利”であるのならば、“敵と見做すことができる”でのんきに構える余裕はあるが、同盟関係の中で“義務”となると必ず米軍に協力しなければならなくなる、という恐ろしい事態に巻き込まれることになる。つまりそれが密約であっても契約があれば日本は、直接関わりのない相手とも積極的に交戦しなければならなくなり、それに背けば反米的となるのだ。
だからこそ、交戦権を放棄した現憲法の下にあって、これまで日本の歴代の政権は、米国の戦争に巻き込まれないように、憲法を尊重遵守し、“個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は憲法の容認する自衛権の限界を超える”と言って来たのだと、ようやく合点したのであった。そこで今では、自民党(石破現幹事長?)の巧みなたとえ話に、安易に乗ってしまい、非常にうかつであった、と猛省している。
ここまで考えを進めると、現政権の常套句である“積極的平和主義”も“集団的自衛権の行使”を補強する概念であると合点が行く。“積極的平和主義”とは、私の解釈では“平和を維持、もしくは固守するためには、武力行使も辞さない”、“積極的に武力行使する”と言うことだと理解している。
現憲法では“問題を解決する手段としての戦争”を否定しているが、“平和のためには積極的に戦争する”というものだ。つまりは、ボスの米国に逆らい問題を引き起こす輩には、日本も積極的に戦争を仕掛けて黙らせよう、というのが安倍政権の目指すところではないか。
憲法は日本の“交戦権を否定”しているが、これを何とか解釈の変更で否認しようとするのが“集団的自衛権の行使”と“積極的平和主義”なのだ。どう考えても、これらを解釈で合憲へ変更することは論理的に不可能だ。赤を白だと言いくるめるに等しい。司法判断を問えば違憲となるのが当然の論理的帰結ではないか。
しかもネットを見ると“ノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥングは消極的平和を「戦争のない状態」、積極的平和を戦争がないだけではなく「貧困、差別など社会的構造から発生する暴力がない状態」と定義した。この定義が「積極的平和(主義)」の世界での一般的な解釈となっている。”とある。つまり、現政権の使っている“積極的平和主義”とは全く異なった概念であり、それは日本の中でしか通用しないその場限りのローカルな概念のようだ。どう見ても、ヨハン・ガルトゥングの言葉遣いの方が思想的・政治学的に深さを持っているように感じる。そういう意味で、安倍政権は欺瞞的言葉遊びしていると思える。
国家防衛を、どうして無理をしてでも“集団的自衛権の行使”から入ろうとするのだろう。どうして、“個別的自衛権”の解釈から入れないのだろうか、不思議でならない。今、政権側が指摘する“グレーゾーン事態”もほとんど全ては、“個別的自衛権の行使”で法整備が可能なのではないか。現に公明党は、そう主張している。
例えば、冒頭に挙げた事態も日本近海での日本の主権防衛のための一連の活動の中で起きた事態であるとすれば、“個別的自衛権の行使”の範囲内での自衛艦の反撃は可能との解釈は成り立つのではないか。何も わざわざ“集団的自衛権”を持ち出さなくても済む話だ。
“グレーゾーン事態”の最大の問題は、海外の邦人救出を どの程度まで現行憲法下の自衛隊で可能なのか、だろう。例えば、2013年のアルジェリア南東部のイナメナスにある日揮のプラントでイスラム武装勢力により日揮の日本人スタッフを含む多数の人質が犠牲となった事件では、自衛隊は全く関与することなく終わったが、それで良かったかの議論が当時一部であった。さらに、イラン・イラク戦争の1985年、イラク軍によるイランの首都テヘランに対する空襲が始まった時、日本政府は日本人の手で邦人救出ができず、親日トルコのエアラインによるボランティア的救出に頼ったことがあった。当時は、自衛隊の海外派遣はできないものとのことになっていたが、今でもこのような場合の自衛隊派遣の明確な法的根拠は、ないのではないか。
現在、最も懸念される事態は朝鮮半島や中国大陸での戦乱や騒乱の有事発生であり、多数の居留邦人をどのように救出するのか、反日の地へ自衛隊を出せるのかという問題も含まれる。米海兵隊に頼むことも考えられるが、彼らの規範では救出対象の優先順位では邦人は第4位の類型*1)とされ、特に厚意によらなければ、満足な結果は期待できない。彼らには日本は便宜を図って来たつもりだが、肝心な時には当てにならないのが現実となっている。しかし、これも“個別的自衛権”の解釈から入るべき課題であって、“集団的自衛権”とは何の関係もないのではないか。
*1:1位-米合衆国の市民権保有者、2位-米合衆国の永住権保有者、3位-アングロサクソン4ヶ国民(英、加、豪、新)、4位-その他(日本人はその他)
首相の私的諮問機関安保法制懇(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)の北岡氏が挙げた集団的自衛権行使の条件は、“①日本と密接な関係にある国が不当な攻撃を受ける②放置すれば日本の安全に大きな影響が及ぶ③攻撃を受けた国から明示的に要請がある、の3事態が重なり、行使の手続きとして④首相が総合的に判断する⑤国会の承認を受けることを、必要条件とし、⑥第三国の領海・領土を通過するにはその国の許可を要することを加える”の6条件とされるが、“日本の安全に大きな影響”というのも拡大解釈できる曖昧な概念だ。やはり日本の防衛とはかけはなれた“集団的攻撃権”を何とか正当化しようとするための条件付けのように思える。
それよりも、国際的に認められた日本政府の管理権が及ぶ範囲(領土、領海、領空、EEZとその上空域または防空識別圏*2)での、地理的空間的制約下での個別的自衛権の行使可能性を検討する方が客観的な制約となり合憲性を確保しやすいのではないか。
このように限定すると、ペルシャ湾からの日本のシーレーン防衛*3)をどのように考えるのかの非難があるかもしれない。だが、それを言い始めると、そこには南シナ海での領有権争いも絡んで来るし、インド洋、ペルシャ湾の洋上からその沿岸の安全と際限が無くなる。現に“グレーゾーン事態”には、ペルシャ湾での機雷掃海も含まれているらしい。
しかし、それこそ戦前の境界安全の不安を外部へ際限なく延伸して行く愚を繰り返し、現憲法の平和主義の原点を犯すものとなる。むしろ それはエネルギー安保として国家戦略の全体像の中での外交努力が必要で、それこそが世界標準の思考ではないか。しかし、この実現こそが安倍政権の本来目的なのかもしれない。
*2:現状の日本の防空識別圏は、かつて米軍が恣意的に設定したものを自衛隊が引き継いでいるもので、近隣諸国との協定に基づいていないので、関係国と整理する必要はあるようだが。
*3:遠隔地での海上自衛隊の運用には航空母艦が必須となる。孤立した洋上部隊は航空攻撃に弱いからだ。また海自はその発足当初より航空母艦の保有を期したようで、以前にこのブログでシミュレーションしたように、既に保有するへリコプター空母にスティルス戦闘機F35Bを搭載すれば、十分に小型空母としての運用は可能な状態にある。だが、日本近海での運用では無用の長物である。(ひゅうが型[全長197m]は2隻保有し、さらに大型のいづも型[全長248m]は1隻を建造中。いづも型は戦前の海軍空母“飛龍”を上回る規模。)
思わず話が長くなってしまったが、“集団的自衛権”は その内実は“集団的攻撃権”であり、“積極的平和主義”が実は“平和の名の下での積極的戦争主義”であるように、安倍政権の使う言葉には、その表面とは異なる裏に隠された意図があることに注意するべきである。“戦後レジームからの脱却”も“戦前レジームへの回帰”と読み替えるべきで、それが真意となると米国の信頼を失う。つまりはサンフランシスコ体制の否定へとつながるからだ。
安倍首相は昨年暮れ靖国参拝を果たしたが、“国のために戦い、尊い命を犠牲にされた御英霊に対して、哀悼の誠を捧げるとともに、尊崇の念を表し、御霊安らかなれとご冥福をお祈りしました。”とコメントしているが、彼は実は、将来予想される自衛官の犠牲者を祀るための参拝であると考えているのではないか。彼の言動には巧みに計算された裏があるのだ。そう考えた場合、安倍氏は死を呼ぶ司祭に見えてしまう。おぞましい限りだ。そう言えば彼は この度の欧州外遊で、原発と武器を売り込んでいて、まさに死の商人へと成り下がった印象があるが・・・。
今のところ、以上のように自分の考えを独自に整理してみたが、今後も考察は深めて行きたいと思っている。書を読むにしても、自分の視点がなければどんな本が良いのか選択の基準がなく混乱するだけなのでこれが 先ず一歩である。
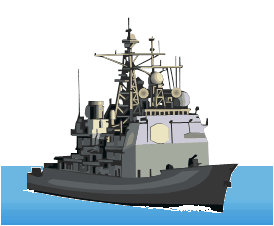
さて、その“集団的自衛権”とは一体 どういうものなのだろう。
当初、自民党(確か石破現幹事長だった?)のたとえ話で聞いていたのは、公海上で日本の防衛に協力する同盟軍つまり米軍の艦船が、自衛隊の艦艇と行動を共にしていたのが日本の敵対国から攻撃された場合、集団的自衛権を行使できない自衛隊は、この米軍の艦船を守るべく攻撃できない。こういう奇妙な状況を打破するためには、集団的自衛権を行使できるようにしなければならない、というものだったと了解していた。したがい、私は 集団的自衛権に関し それほど問題のあるものとは考えていなかった。
ところが、そういう先入観で先日“朝まで生テレビ”を見ていたところ、議論について行けず、面食らったのだった。
そこで、改めて“集団的自衛権”について、ネットで調べてみた。すると、“英語:ではright of collective self-defense、と言い、他の国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある。”とある。また国連憲章第51条により、個別的、集団的自衛権は日本も持てるものとあった。
*国連憲章第51条では次のように規定。“この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。”
どうやら、“集団的自衛権”が想定している事態は、具体的には米国が“9・11での敵”とするアルカイーダの拠点のアフガニスタンのある地域を一部の親米国と共同で攻撃する権利があるということになるらしい。ならば、英語を直訳すればなるほど、“集団的自衛権”となるのかも知れないが、実際は“集団的攻撃権”と称した方が本来のイメージには近いのではないかと思うのだ。
つまり、“集団的自衛権”とは、誰かにいきなり殴られた男が、今度は仲間を引き連れて殴ってきた相手に逆襲する、その場合の仲間の参加を正当化するための法的権利ということになる。そんなことに、憲法で“交戦権を放棄”した日本が参加する合理性・合法性はあるのだろうか。否、憲法解釈の変更で“集団的自衛権”が持てることになるのだろうか。
先述した自民党(石破現幹事長?)が挙げていた“集団的自衛権”の説明事例での“公海”についてのイメージを、“日本近海の公海上”と私が勝手に想像していたのが、どうやら間違っていたようである。確かに最近、自民党側から“集団的自衛権行使のために‘地球の裏側まで行く’というようなことはない”と言明したというのは、そういうことに対応しているものと理解できる。
私が誤解したのは、一つには言葉の使い方にも惑わされたのではないかと思うのだ。それは、英訳では、“集団的自衛権”となるのだが、内実は“集団的攻撃権”であり、そのように言われていれば注意するはずの政策だったのだ。
そういう理解の後、ビデオに撮っていた“朝まで生テレビ”を改めて見直してみると、驚くほど議論の内容にすんなりと入って行けたのだ。“集団的自衛権”の内実は“集団的攻撃権”であるというのは、識者の間では常識だったのだ。
となると日本の“集団的自衛権”とは、米国が敵と見做した相手については、地球上のどの地点に居ても、これを日本の“敵でもあると見做すことができる”ことになる。この敵と認定する部分が、“権利”であるのか“義務”となるのかで、日本の立ち位置はさらに大きく変化する。“権利”であるのならば、“敵と見做すことができる”でのんきに構える余裕はあるが、同盟関係の中で“義務”となると必ず米軍に協力しなければならなくなる、という恐ろしい事態に巻き込まれることになる。つまりそれが密約であっても契約があれば日本は、直接関わりのない相手とも積極的に交戦しなければならなくなり、それに背けば反米的となるのだ。
だからこそ、交戦権を放棄した現憲法の下にあって、これまで日本の歴代の政権は、米国の戦争に巻き込まれないように、憲法を尊重遵守し、“個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は憲法の容認する自衛権の限界を超える”と言って来たのだと、ようやく合点したのであった。そこで今では、自民党(石破現幹事長?)の巧みなたとえ話に、安易に乗ってしまい、非常にうかつであった、と猛省している。
ここまで考えを進めると、現政権の常套句である“積極的平和主義”も“集団的自衛権の行使”を補強する概念であると合点が行く。“積極的平和主義”とは、私の解釈では“平和を維持、もしくは固守するためには、武力行使も辞さない”、“積極的に武力行使する”と言うことだと理解している。
現憲法では“問題を解決する手段としての戦争”を否定しているが、“平和のためには積極的に戦争する”というものだ。つまりは、ボスの米国に逆らい問題を引き起こす輩には、日本も積極的に戦争を仕掛けて黙らせよう、というのが安倍政権の目指すところではないか。
憲法は日本の“交戦権を否定”しているが、これを何とか解釈の変更で否認しようとするのが“集団的自衛権の行使”と“積極的平和主義”なのだ。どう考えても、これらを解釈で合憲へ変更することは論理的に不可能だ。赤を白だと言いくるめるに等しい。司法判断を問えば違憲となるのが当然の論理的帰結ではないか。
しかもネットを見ると“ノルウェーの平和学者ヨハン・ガルトゥングは消極的平和を「戦争のない状態」、積極的平和を戦争がないだけではなく「貧困、差別など社会的構造から発生する暴力がない状態」と定義した。この定義が「積極的平和(主義)」の世界での一般的な解釈となっている。”とある。つまり、現政権の使っている“積極的平和主義”とは全く異なった概念であり、それは日本の中でしか通用しないその場限りのローカルな概念のようだ。どう見ても、ヨハン・ガルトゥングの言葉遣いの方が思想的・政治学的に深さを持っているように感じる。そういう意味で、安倍政権は欺瞞的言葉遊びしていると思える。
国家防衛を、どうして無理をしてでも“集団的自衛権の行使”から入ろうとするのだろう。どうして、“個別的自衛権”の解釈から入れないのだろうか、不思議でならない。今、政権側が指摘する“グレーゾーン事態”もほとんど全ては、“個別的自衛権の行使”で法整備が可能なのではないか。現に公明党は、そう主張している。
例えば、冒頭に挙げた事態も日本近海での日本の主権防衛のための一連の活動の中で起きた事態であるとすれば、“個別的自衛権の行使”の範囲内での自衛艦の反撃は可能との解釈は成り立つのではないか。何も わざわざ“集団的自衛権”を持ち出さなくても済む話だ。
“グレーゾーン事態”の最大の問題は、海外の邦人救出を どの程度まで現行憲法下の自衛隊で可能なのか、だろう。例えば、2013年のアルジェリア南東部のイナメナスにある日揮のプラントでイスラム武装勢力により日揮の日本人スタッフを含む多数の人質が犠牲となった事件では、自衛隊は全く関与することなく終わったが、それで良かったかの議論が当時一部であった。さらに、イラン・イラク戦争の1985年、イラク軍によるイランの首都テヘランに対する空襲が始まった時、日本政府は日本人の手で邦人救出ができず、親日トルコのエアラインによるボランティア的救出に頼ったことがあった。当時は、自衛隊の海外派遣はできないものとのことになっていたが、今でもこのような場合の自衛隊派遣の明確な法的根拠は、ないのではないか。
現在、最も懸念される事態は朝鮮半島や中国大陸での戦乱や騒乱の有事発生であり、多数の居留邦人をどのように救出するのか、反日の地へ自衛隊を出せるのかという問題も含まれる。米海兵隊に頼むことも考えられるが、彼らの規範では救出対象の優先順位では邦人は第4位の類型*1)とされ、特に厚意によらなければ、満足な結果は期待できない。彼らには日本は便宜を図って来たつもりだが、肝心な時には当てにならないのが現実となっている。しかし、これも“個別的自衛権”の解釈から入るべき課題であって、“集団的自衛権”とは何の関係もないのではないか。
*1:1位-米合衆国の市民権保有者、2位-米合衆国の永住権保有者、3位-アングロサクソン4ヶ国民(英、加、豪、新)、4位-その他(日本人はその他)
首相の私的諮問機関安保法制懇(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)の北岡氏が挙げた集団的自衛権行使の条件は、“①日本と密接な関係にある国が不当な攻撃を受ける②放置すれば日本の安全に大きな影響が及ぶ③攻撃を受けた国から明示的に要請がある、の3事態が重なり、行使の手続きとして④首相が総合的に判断する⑤国会の承認を受けることを、必要条件とし、⑥第三国の領海・領土を通過するにはその国の許可を要することを加える”の6条件とされるが、“日本の安全に大きな影響”というのも拡大解釈できる曖昧な概念だ。やはり日本の防衛とはかけはなれた“集団的攻撃権”を何とか正当化しようとするための条件付けのように思える。
それよりも、国際的に認められた日本政府の管理権が及ぶ範囲(領土、領海、領空、EEZとその上空域または防空識別圏*2)での、地理的空間的制約下での個別的自衛権の行使可能性を検討する方が客観的な制約となり合憲性を確保しやすいのではないか。
このように限定すると、ペルシャ湾からの日本のシーレーン防衛*3)をどのように考えるのかの非難があるかもしれない。だが、それを言い始めると、そこには南シナ海での領有権争いも絡んで来るし、インド洋、ペルシャ湾の洋上からその沿岸の安全と際限が無くなる。現に“グレーゾーン事態”には、ペルシャ湾での機雷掃海も含まれているらしい。
しかし、それこそ戦前の境界安全の不安を外部へ際限なく延伸して行く愚を繰り返し、現憲法の平和主義の原点を犯すものとなる。むしろ それはエネルギー安保として国家戦略の全体像の中での外交努力が必要で、それこそが世界標準の思考ではないか。しかし、この実現こそが安倍政権の本来目的なのかもしれない。
*2:現状の日本の防空識別圏は、かつて米軍が恣意的に設定したものを自衛隊が引き継いでいるもので、近隣諸国との協定に基づいていないので、関係国と整理する必要はあるようだが。
*3:遠隔地での海上自衛隊の運用には航空母艦が必須となる。孤立した洋上部隊は航空攻撃に弱いからだ。また海自はその発足当初より航空母艦の保有を期したようで、以前にこのブログでシミュレーションしたように、既に保有するへリコプター空母にスティルス戦闘機F35Bを搭載すれば、十分に小型空母としての運用は可能な状態にある。だが、日本近海での運用では無用の長物である。(ひゅうが型[全長197m]は2隻保有し、さらに大型のいづも型[全長248m]は1隻を建造中。いづも型は戦前の海軍空母“飛龍”を上回る規模。)
思わず話が長くなってしまったが、“集団的自衛権”は その内実は“集団的攻撃権”であり、“積極的平和主義”が実は“平和の名の下での積極的戦争主義”であるように、安倍政権の使う言葉には、その表面とは異なる裏に隠された意図があることに注意するべきである。“戦後レジームからの脱却”も“戦前レジームへの回帰”と読み替えるべきで、それが真意となると米国の信頼を失う。つまりはサンフランシスコ体制の否定へとつながるからだ。
安倍首相は昨年暮れ靖国参拝を果たしたが、“国のために戦い、尊い命を犠牲にされた御英霊に対して、哀悼の誠を捧げるとともに、尊崇の念を表し、御霊安らかなれとご冥福をお祈りしました。”とコメントしているが、彼は実は、将来予想される自衛官の犠牲者を祀るための参拝であると考えているのではないか。彼の言動には巧みに計算された裏があるのだ。そう考えた場合、安倍氏は死を呼ぶ司祭に見えてしまう。おぞましい限りだ。そう言えば彼は この度の欧州外遊で、原発と武器を売り込んでいて、まさに死の商人へと成り下がった印象があるが・・・。
今のところ、以上のように自分の考えを独自に整理してみたが、今後も考察は深めて行きたいと思っている。書を読むにしても、自分の視点がなければどんな本が良いのか選択の基準がなく混乱するだけなのでこれが 先ず一歩である。
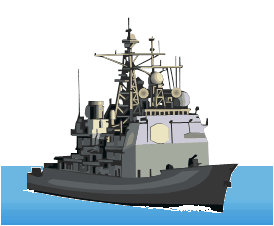
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « “福島の原発事... | 野口悠紀雄教... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |





