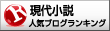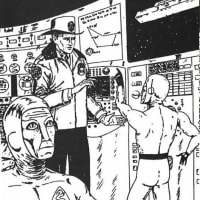日々の出来事 11月21日 気球
今日は、モンゴルフィエ兄弟が、パリで初めて気球による有人飛行に成功した日です。(1783年11月21日)
モンゴルフィエ兄弟は、焚き火の煙を紙袋に溜めると、紙袋が浮かび上がることに気が付きます。
1782年ごろから、モンゴルフィエ兄弟は気球の実験を重ね、1782年12月14日には絹製の袋を使い、高度250mまで上昇させることに成功します。
この時、気球は風に飛ばされ、飛んできた気球を見た村人は、“空からお化けが落ちてきた”とビックリしました。
1783年6月5日には、アノネーでリンネル製の袋を使って実験を行い、気球を高度2000mまで上昇させました。
この当時、“どうして煙を集めると気球が上昇するのか”は分からず、モンゴルフィエ兄弟はこれを煙の中に上昇させる成分が入っているものと考えていたので、この上昇成分を“モンゴルフィエのガス”と言っていました。
1783年9月19日には、ルイ16世の見学のもと、モンゴルフィエ兄弟は、気球に吊り下げた籠にアヒル・ニワトリ・ヒツジを入れ、気球を上昇させても上空に酸素があることを示し、勲章を与えられます。
そして、動物実験に成功したモンゴルフィエ兄弟は、1783年11月21日、初めての気球の有人飛行に成功します。
この実験はパリで行われ、フランソワ・ダルランドとピラトール・ド・ロジェを乗せた気球は100mまで上昇、パリ上空の9kmの距離を25分間に渡って飛行しました。
現在、遊園地などで見られる熱気球の原型が、このとき初めて出来上がったのです。

気球
☆今日の壺々話
ジョーク1 “経済学者とビジネスマン”
二人の男が気球に乗っていました。
風向きが悪く、気球はどんどん流されて、二人の知らない土地にきました。
彼らは高度を下げ、道を行く一人の男に声をかけました。
「 すいませーん。
私たちは今、何という場所にいるんでしょうか?」
「 あなたたちは気球の中にいますよ~。」
それを聞いて一人が言いました。
「 あいつは経済学者に違いない。
言っていることは正しいが、何の役にも立たない。」
それを聞いた地上の男は言いました。
「 そう言うあなたたちはビジネスマンに違いない。
私より見通しのいいところにいながら、自分がどこにいるのかも分からない。」
ジョーク2 “気球”
「 うわ~っ、大変だ、バーナーが壊れたァ~。」
「 落ちるゥ~~!!」
二人の男を乗せた気球は、深い谷底に落ちて行きました。
そして、谷底に落ちた二人は、脱出する方法を考え始めました。
「 ここは、何処なんだろう?」
「 分からないな・・。」
「 大声で助けを呼べば、谷にこだまして誰かに声が届くかも知れない。」
「 そうだな、取り敢えずやって見よう!」
二人は大声で叫びました。
「 お~~~い、ここは何処だァ~~~?」
「 お~~~い、助けてくれェ~~~~!!」
しかし、しばらく待っても、何の返答もありません。
「 やっぱりダメかな・・・。」
「 そうだなァ、もう、叫んでから15分も経っている・・・・。」
その時、返事が返って来ました。
「 君らは、谷底だァ~~~~~~!!」
一人の男は喜びました。
「 やったァ~、これで助かる・・。」
でも、もう一人の男は諦め顔をしていました。
不審に思った男は尋ねます。
「 どうしたんだ?
もう直ぐ助かると言うのに・・・・。」
「 いや、もう、最悪だ。
あいつは、数学者に違いない。」
「 どうして?」
「 理由は、3つある。
一つ目は、ヤツは答えるまで長い間考えていた。
二つ目は、ヤツは与えられた条件から論理を正しく組み立てた。
三つ目は、ヤツはそれが絶対正しいと確信したから答えを言ったんだ。」
「 じゃ、大丈夫だろ?」
「 いや、数学者だからなァ・・・。
もう、答えに満足して家に帰っただろうな・・・。」
ジョーク3 “分析”
ある女が、気球飛行中に風で地図を飛ばされてしまった。
目視では進むべき方向がわからなかったため、仕方なく、眼下を歩いていた男に呼びかけた。
「 すみません、ここがどこだか教えていただけませんか。
一時間前には戻っている約束をしているのですが、迷ってしまって・・・。」
男は、こう答えた。
「 あなたがいる場所は、ざっと見て地上三十メートルほどの上空です。
位置としては、北緯三十六度三十分と三十五分の間、東経百三十九度四十五分と五十分の
間というところでしょう。」
これを聞いて、女は尋ねた。
「 失礼ですが、ご職業はエンジニアでいらっしゃいませんか?」
「 そうです、なぜわかったのですか?」
「 今いただいた情報はきっと理論的には正しいのでしょうけれど、数字は解釈の仕方がわからないと役に立ちません。
現に私は相変わらず迷っていて、問題は何も解決されていないからです。」
すると、男はこう言った。
「 あなたは、プロジェクトマネージャーでいらっしゃいませんか?」
「 ええ、そうですが、なぜおわかりに?」
「 まず、あなたは自分が今いる位置も、自分が向かっている方向もわかっていない。
さらに、守れもしない約束を自分でしておきながら、私に問題解決を求めている。
要するに、置かれている状況は私と会う前とまったく変わっていないのにもかかわらず、あなたは、さりげなく全部私のせいにしているからです。」
ブタの丸焼き
幼稚園の頃、庭でみんなが鬼ごっこや砂遊びをしているのに、私はいつも一人で隅っこの鉄棒にぶらさがっていた。
両手両足で鉄棒にしがみつき、空を見ながらゆらゆら揺れていた。
先生に「何をしてるの?」と聞かれて、「ブタの丸焼き」と答えた私。
きっと他の子みたいに子供っぽく騒いだりせず、ブタになりきって青い空を切なく見上げる自分に酔っていたんだと思う。
今、考えると意味不明。
なんであれがかっこいいと思っていたんだろう。
消し去りたい過去のひとつ。
チクワ
完全に鬱なとき、あんま考え込まないほうがいいよ。
天気いいから、嫌なこと忘れて屋上とかで寝転がってチクワ咥えて深呼吸とかするといいよ。
空気がチクワの味になる。
チクワを食べてないのにチクワ味が楽しめる。
15分くらいで全体的に乾燥してきて味しなくなるけど、唾でぬらせばまたチクワ味の空気が復活する。
チクワを咥えながら、チクワ味の空気のようにお金も増えたらいいなって、青い空と雲を見ながら考える。
きっと、すごいアイディアが浮かぶ。
もし浮かばなくても、チクワ味が楽しめるし嫌なこともちょっと忘れられる。
空飛ぶ目玉
空を飛ぶ巨大な目玉というイメージの源泉は、19世紀フランスの画家オディロン・ルドンの “眼は奇妙な気球のように無限に向かう”という版画にある。
水木しげるのバックベアードをはじめ、 多くの目玉モンスターがこの作品を発想の原点として生まれている。
日本では、文豪芥川龍之介の妖怪画巻、化物帖の一目怪がやはり強烈な影響を与えている。
だが目玉モンスターの源泉はもっと古く、西洋で古代から信じられていた、
毒を持った視線“邪眼(邪視)” を避けるために家の庇や船体などに描かれる“魔除けの目”が独立したものと考えられる。
この場合、モンスターの属性は“邪眼”、外観は“魔除けの目”というかたちを取ることが多く、 ファンタジーに登場するビホルダー等の怪物に、その現代的な姿を見出すことができる。
古代より世界中で、一つ目の怪物の存在が信じられていたが、これは“隻眼の神”が零落して恐れられるようになった姿と考えられている。
隻眼の神とは鍛冶の神であり、鍛冶職人が火を見つめ続けるために片目を潰してしまう職業病を患うことが多かったことの反映である。
日本の一つ目妖怪“一本ダタラ(たたら=鍛冶場)”、“山ン爺”、“雪入道”などがこれに相当する。
ギリシア神話の単眼巨人キクロプス(サイクロプス)も元々は神々の鍛冶師であり、かつ宝の守護者であった。
なお単眼の怪物の多くは鼻がなく、額に一本角を持っているが、これは単眼症という。
奇形児の顔には鼻がなく、額に突起(本来なら鼻になるはずだった部分)があることと関係すると見られている。
また民族学者・柳田国男は一つ目小僧を、古代の日本で神に捧げる生け贄の人間の逃亡を防ぐために片目を潰す習慣があったことと関連付け、生け贄にされる代わりに、その日までは犯罪を犯すことを許された
人身御供を、一般の人々が鬼として恐れたことの名残りだと説明している。
神話に登場する巨人や龍などの巨大な怪物は、多くの場合、暴風雨など天災の形象化と考えられている。
それでは単眼巨人の一つ目は台風の目を現わしているのではないかとも考えられるが、実際に地上から台風の目がはっきり円形に捉えられることは少なく、これは単なる偶然である可能性が高い。
昔の記憶
小学校低学年くらいの時の話
近所の同学年の友達数人が隣のアパートの外階段で何やら騒いでいるのでそこへ行ってみた。
皆が指差す方を見ると、向こうの空にビルの給水タンクみたいなものが浮かんでいるのが見えた。
誰かが双眼鏡を持ち出してきて、自分もそれを覗いたが、やっぱり給水タンクみたいだった。
でも空に浮かんでる。
一人が「あれは○○帝国の円盤だよ」なんて言ってた(○○の部分は憶えてない)
後になって母親に「アレ何だったんだろうなー」と言うと母親は、「あれ気球だったでしょ。あんたを自転車の後ろに乗せて見せに行ったじゃない」と言うが、おれには母親のチャリでそんなもんを見に行った記憶は無い。
風の神さんの落し物
明治十年(1877年)5月23日のお昼過ぎ、千葉県東葛飾郡堀江村(浦安市)の小さな漁村で、それは起こります。
朝からの漁も終わり、船や網の手入れなどしながら、村の漁師たちが浜辺でおしゃべりをしてる・・・そんな、のどかな、いつもと変わらぬ風景の中、ふと、空を見上げると、北西の方角から、何やら巨大な物体が近づいてきます。
「 何じゃ?アリャ。」
「 クラゲのバケモンか?」
それは、空から落ちてくる・・・というよりは、ふわりふわりといった感じで、ゆっくりと降りてきます。
やがて、それは、浜辺にストンと・・・。
近づいてみると、いやはや、思った以上に大きい。
その物体の高さは九間(約16m)、幅五間(約9m)、周囲十七間(約30m)。
大きな球形の物体で、全体に太い綱が張り巡らされていて、その綱の内部には、綱に沿うような形で、猫の皮のようなヌメっとした白い物が納まっています。
しかも、その綱の内側の物は、クラゲのようにブヨブヨ・・・。
おりからの風にあおられ、物体は、浜辺の上を回転しながら、あるいは、ズルズルと引きずられるように動き回ります。
知らせを聞いた村人が続々と集まってきて、浜辺は大騒ぎです。
「 なんや、ラッキョウの化け物みたいやな。」
「 いや、デッカイ袋のようやで。」
「 ひょっとしたら、風の神さんの落し物やないかい?」
そう言いながら、はじめは遠巻きに見ていた漁師たちも、やがては、そのヌメヌメした皮の部分をさわりはじめる者、船の櫂(かい)でつっつきはじめる者・・・イロイロです。
しかし、コチラをつっつけば、アチラがポコンと膨れあがり、アチラをつっつけば、またコチラがポコンを膨れあがり・・・やがて、力自慢の若者が、「オリャ~」とばかりに力任せに蹴りあげると、鈍い音とともに、皮が破れたかと思うと・・・プシュ~ッ!!!
その裂け目から、大量の臭いにおいの空気が、風のように吹き出しました。
「 うわぁ!毒吐きよった!」
「 逃げろ!逃げろ!」
もう、腰を抜かす者。
あわてて転ぶ者。
毒気をあびて倒れる者。
あたりは騒然となります。
で、後に判明するのですが・・・。
実は、この明治十年という年・・・そう、頃は、ご存知、西南戦争の真っ只中であります。
その西南戦争が始まったばかりの3月に、西郷軍に包囲された熊本城は、何とか籠城作戦で守りきり、その後の田原坂での勝利によって無事だったもの、50日間という長きわたって、城は孤立状態となり、中と外でまったく連絡が取れないという、とても危険な状態となっていました。
そこで、新政府軍は、緊急時の連絡用の新兵器の開発を馬場新八に依頼していたのです。
それは、奉書紙(ほうしょがみ・キメの細かい厚手の和紙)、130反(1反=約11m)をミシンで縫い合わせ、表面にゴムを塗った風船状の物で、中に蒸気ポンプで瓦斯(ガス)を送り込み、綱を編んだ物をかぶせて、その綱から伸びた先に、籠を取り付け、そこに人間が乗って、空を飛ぼうというシロモノでした。
つまり、軍事用の気球だったという事です。
明治十年(1877年)5月23日、築地の海軍兵学校で行われた実験では、海軍はもちろん陸軍の軍人・関係者が多数見守る中、金杉の瓦斯会社から運ばれた瓦斯を注入された2個の気球が、空高く舞い上がる・・・予定だったのですが、残念ながら、一つの気球は、飛行直前に破裂。
で、もう一つが、上記の大騒ぎの気球だったわけです。
コチラは、飛ぶには飛んだものの、つないでいた綱が切れ、あれよあれよという間に、風に乗り、東南の空へと消えてしまっていたのでした。
これが、日本初の気球の実験でした。
結局、この西南戦争で、実際に気球が使用される事はありませんでしたが、その後、気球は、イベント用の見世物として、一般の人々の知るところとなります。
やがて訪れた暗い時代には、日露戦争で偵察用に使用されたり、太平洋戦争の風船爆弾として、その技術が、軍事用に引き継がれていく事になりますが、現在は、ご存知のように、夢あふれる乗り物として、その飛距離を競うスポーツとしてもお馴染みですね。
それにしても、何も知らされていなかった明治の頃の一般庶民は、さぞかし驚いた事でしょうね。
「風の神さんの落し物」、なんだかわかる気がします。
童話・恐怖小説・写真絵画MAINページに戻る。
大峰正楓の童話・恐怖小説・写真絵画MAINページ