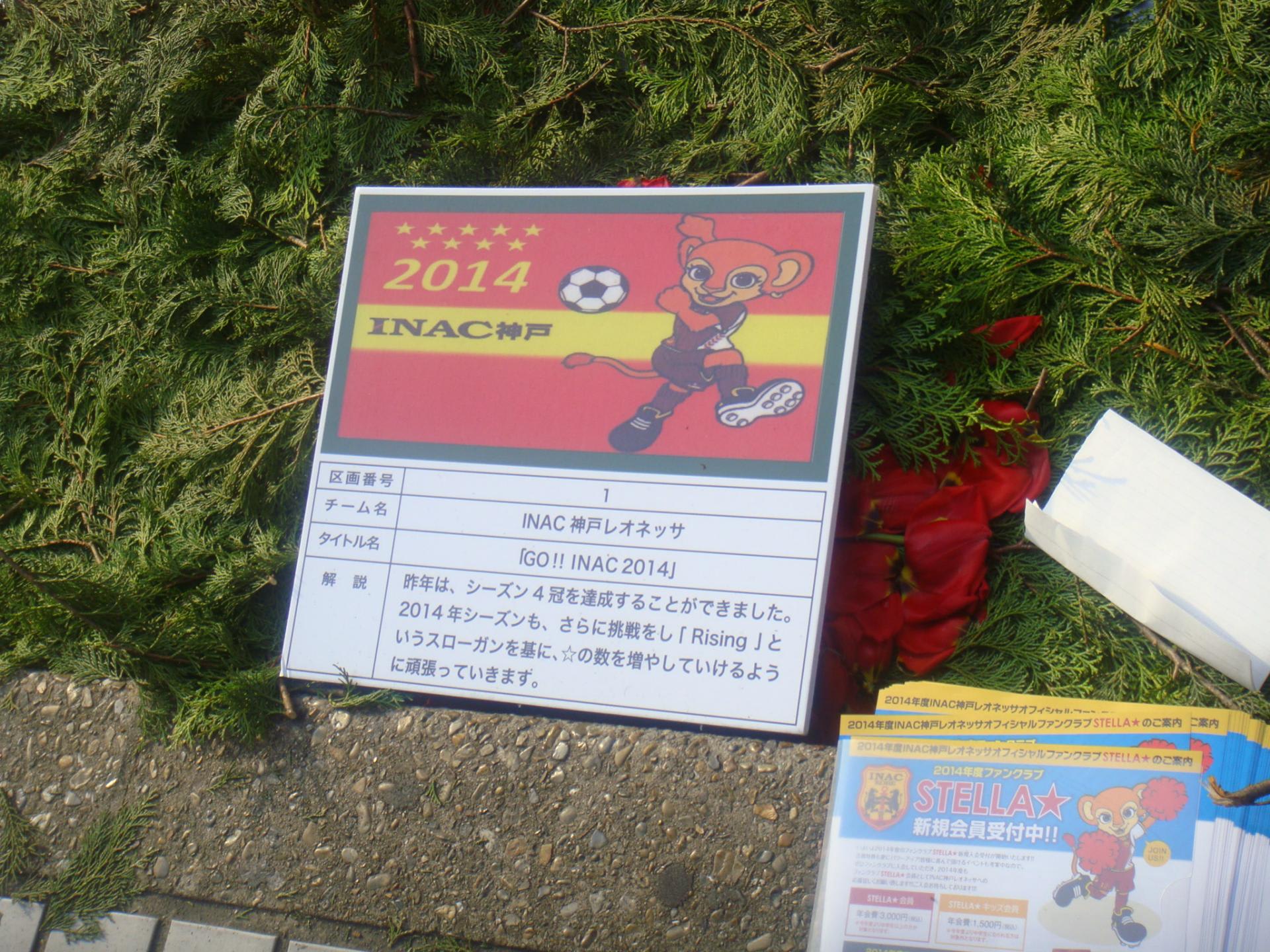2014年4月25日
真光寺は、仁明天皇(833年~850年)のころ、恵萼が唐より観世音を持ち帰り、和田岬で船が動かなくなったので、堂を建てて祀ったのが始まりという。
真光寺は、もと兵庫輪田の崎島「光明福寺」に創まり宗祖一遍上人が念仏勧進の全国遊行の旅の途中、この地に立ちより正応二年(1289)八月二十三日観音堂に於いてご入寂、その後兵庫の信者達によって荼毘(火葬)に付され、霊骨を五輪塔に納められ、お木像を御影堂に祀り御遺徳を崇めました。
御影堂において二祖真教上人が一遍上人の13回忌の法要を営んだと「遊行縁起(真光寺所蔵)」に記されていそうです。その頃二祖真教上人は、伏見天皇に奏して「真光寺」の寺名を拝受し、播州守護職赤松円心より寺領を寄進され、七堂伽藍は荘厳を極め、寺地三十八町四方に及んだといわれています。
次いで後醍醐天皇より「西月山」の山号を勅賜され、南朝の皇族「尊観法親王」が住持されてより更に念仏の大道場として繁栄しました。
兵庫区松原通1丁目1-62
map


門前の右です。

門前の左に「 一遍上人示寂之地」の石碑があります。

鐘楼

旅行柳
謡曲「遊行柳」によって知られている遊行十九代尊皓(そんこう)上人が、南無阿弥陀仏の名号をもって柳の精霊を済度された。安永3年(1744)10月、浪華の俳人佐々木泉明がその因縁をたどり、その柳の一枝を一遍上人示寂の地真光寺に移し植えたもの(今は枯れてしまってありません)で、この句碑を建てています。

一遍上人御廟
兵庫県指定記念物(史跡)(昭和46年4月1日指定)鎌倉時代後期
遺体は敬慕する沙弥教信のように野に捨てて獣に施せとの一遍の遺言であったが、在地の人々の結縁により観音堂前の松の根元で荼毘に付し、廟を設けたという。


五輪塔
花崗岩製石造五輪塔 兵庫県指定重要文化財(建造物)(昭和46年4月1日指定)鎌倉時代後期~南北朝時代
高さ1.95cm、阪神・淡路大震災で倒壊した時、中から骨灰が現れたという。


地蔵さん

六地蔵

平清盛公の御膳水の井戸
平清盛公が当寺に弁財天を勧進した時に、僧がこの井戸の水でお茶をたてて献上したと伝えられています。

境内にいくつかの句碑があります。
河野静雲先生句碑
「白露や永久に聖の御跡ど」
明治20年~昭和49年(1887~1947)
大正13年俳誌木犀発行、同9年ホトトギス同人、同16年冬野を発行。その生涯は虚子門下の俳僧として終始しました。

望月華山句碑
「菊剪ってわれ一介の祖廟守」
明治30年~昭和48年(1897~1973)
大正3年藤沢時宗宗学林に入り寮監河野静雲に俳句を習う。昭和21年神戸大檀林真光寺住職、同29年5月選挙によって法主候補に任じ、同45年1月多年の労作である『時衆年表』(角川書店)刊行しました。

境内にある熊野権現社
文永11年の夏(1274)、一遍上人が熊野証誠殿に参篭し、御神示を感得され、御託宣を受け、念仏勧進の遊行の旅を続けられたといわれています。以来、時宗にては熊野権現を守護神として尊崇しているとのことです。

和田の笠松の歌碑
寺の北側の須佐野公園にありました。
和田の笠松は、須佐の入江に聳え、入港船の目標となり、東西往還の目印となっていた。鎌倉時代初期の歌人、藤原為家の歌に「秋風の吹き来る峯の村雨に、さして宿かる和田の笠松」と歌われており、古くから有名な松であった。戦災で焼失したが、神戸史談会の記念事業としてこの地に植えた。

真光寺は、仁明天皇(833年~850年)のころ、恵萼が唐より観世音を持ち帰り、和田岬で船が動かなくなったので、堂を建てて祀ったのが始まりという。
真光寺は、もと兵庫輪田の崎島「光明福寺」に創まり宗祖一遍上人が念仏勧進の全国遊行の旅の途中、この地に立ちより正応二年(1289)八月二十三日観音堂に於いてご入寂、その後兵庫の信者達によって荼毘(火葬)に付され、霊骨を五輪塔に納められ、お木像を御影堂に祀り御遺徳を崇めました。
御影堂において二祖真教上人が一遍上人の13回忌の法要を営んだと「遊行縁起(真光寺所蔵)」に記されていそうです。その頃二祖真教上人は、伏見天皇に奏して「真光寺」の寺名を拝受し、播州守護職赤松円心より寺領を寄進され、七堂伽藍は荘厳を極め、寺地三十八町四方に及んだといわれています。
次いで後醍醐天皇より「西月山」の山号を勅賜され、南朝の皇族「尊観法親王」が住持されてより更に念仏の大道場として繁栄しました。
兵庫区松原通1丁目1-62
map


門前の右です。

門前の左に「 一遍上人示寂之地」の石碑があります。

鐘楼

旅行柳
謡曲「遊行柳」によって知られている遊行十九代尊皓(そんこう)上人が、南無阿弥陀仏の名号をもって柳の精霊を済度された。安永3年(1744)10月、浪華の俳人佐々木泉明がその因縁をたどり、その柳の一枝を一遍上人示寂の地真光寺に移し植えたもの(今は枯れてしまってありません)で、この句碑を建てています。

一遍上人御廟
兵庫県指定記念物(史跡)(昭和46年4月1日指定)鎌倉時代後期
遺体は敬慕する沙弥教信のように野に捨てて獣に施せとの一遍の遺言であったが、在地の人々の結縁により観音堂前の松の根元で荼毘に付し、廟を設けたという。


五輪塔
花崗岩製石造五輪塔 兵庫県指定重要文化財(建造物)(昭和46年4月1日指定)鎌倉時代後期~南北朝時代
高さ1.95cm、阪神・淡路大震災で倒壊した時、中から骨灰が現れたという。


地蔵さん

六地蔵

平清盛公の御膳水の井戸
平清盛公が当寺に弁財天を勧進した時に、僧がこの井戸の水でお茶をたてて献上したと伝えられています。

境内にいくつかの句碑があります。
河野静雲先生句碑
「白露や永久に聖の御跡ど」
明治20年~昭和49年(1887~1947)
大正13年俳誌木犀発行、同9年ホトトギス同人、同16年冬野を発行。その生涯は虚子門下の俳僧として終始しました。

望月華山句碑
「菊剪ってわれ一介の祖廟守」
明治30年~昭和48年(1897~1973)
大正3年藤沢時宗宗学林に入り寮監河野静雲に俳句を習う。昭和21年神戸大檀林真光寺住職、同29年5月選挙によって法主候補に任じ、同45年1月多年の労作である『時衆年表』(角川書店)刊行しました。

境内にある熊野権現社
文永11年の夏(1274)、一遍上人が熊野証誠殿に参篭し、御神示を感得され、御託宣を受け、念仏勧進の遊行の旅を続けられたといわれています。以来、時宗にては熊野権現を守護神として尊崇しているとのことです。

和田の笠松の歌碑
寺の北側の須佐野公園にありました。
和田の笠松は、須佐の入江に聳え、入港船の目標となり、東西往還の目印となっていた。鎌倉時代初期の歌人、藤原為家の歌に「秋風の吹き来る峯の村雨に、さして宿かる和田の笠松」と歌われており、古くから有名な松であった。戦災で焼失したが、神戸史談会の記念事業としてこの地に植えた。