2017年9月24日、加賀観光で、大聖寺の町並み散策の後、加賀市の橋立地区を散策しました。日本遺産に認定されています。
橋立は、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。江戸後期から明治中期にかけて活躍した北前船の船主や船頭が多く居住した集落です。保存地区には往時の様子を伝える船主屋敷が起伏に富む地形に展開しています。敷石や石垣には淡緑青色の笏谷石(しゃくだにいし)が使われ、集落に柔らかな質感を与えています。
日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定し、様々な文化財を総合的に活用する取り組み支援する制度です。
日本海岸には、山を風景の一部に取り込む港町が点々とみられます。そこには、港に通じる小路が随所に走り、通りには広大な商家や豪壮な船主屋敷が建っています。また、社寺には奉納された船の絵馬や模型が残り、京など遠方に起源がる祭礼が行われ、節回しの似た民謡が唄われています。これらの港町は、各地の繁栄をもたらした北前船の寄港地・船主集落を形成してきました。
北前船は、江戸時代から明治時代にかけて繁栄した商売の形態のことで、大阪と北海道を往復し、莫大な富を得ました。北前船の商売の特徴は、他人の荷物を運んで運賃を稼ぐのではなく、船主が荷主として各地で物を売り買いしながら航海するという点にあります。そのため、うまく行けば大儲けできますが、失敗すれば大損、それどころか遭難すれば、命の危険にさらされることもありました。まさに「板子一枚下は地獄」といった状況だったのです。
加賀市橋立町には特に北前船主が多く、寛政8年(1796)の記録では、42名の船主の名がみえます。加賀市は船主のふる里と呼ぶにふさわしく、他にも瀬越町、塩屋町など船主が多く出た地域があります。
map


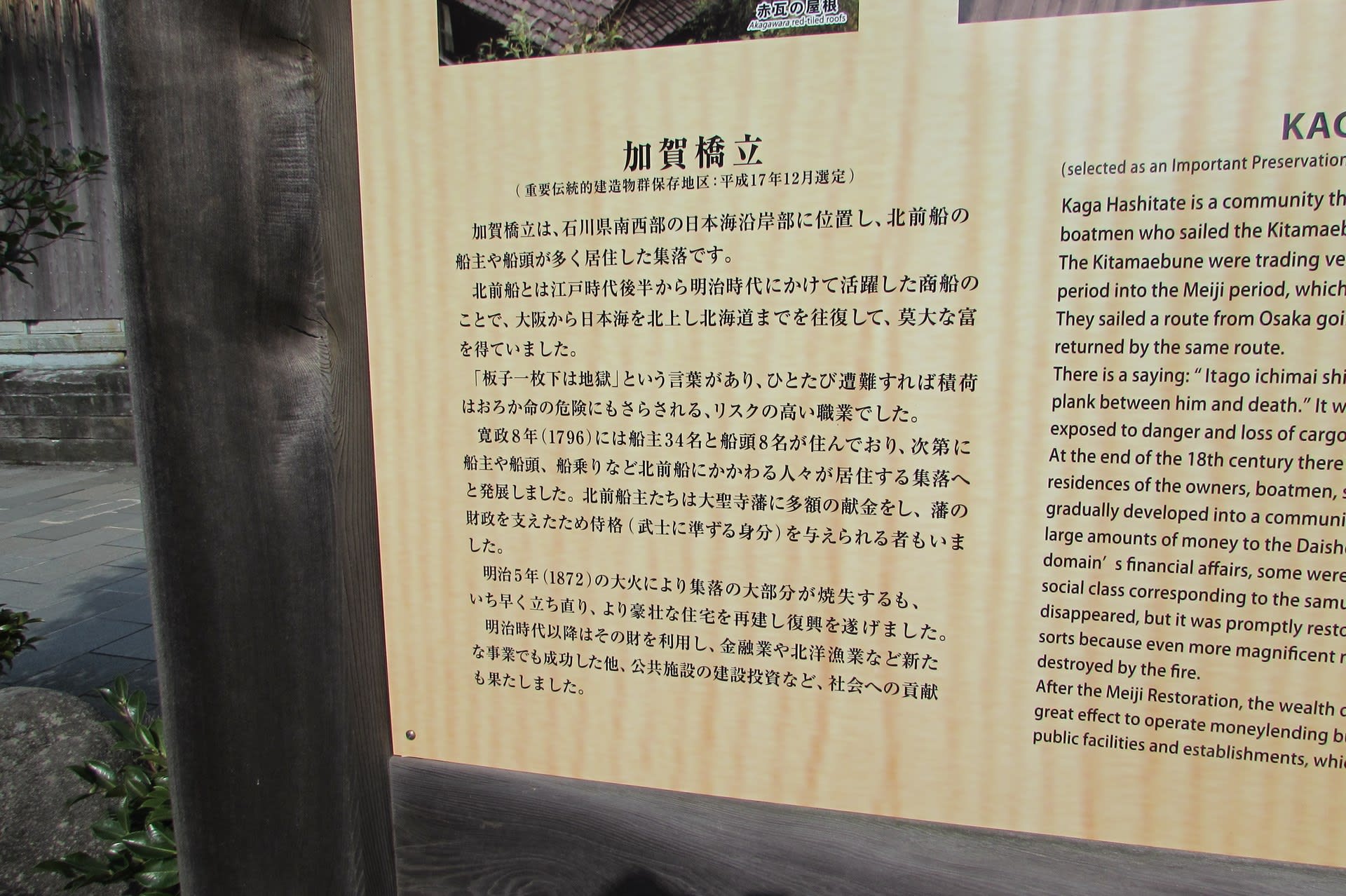
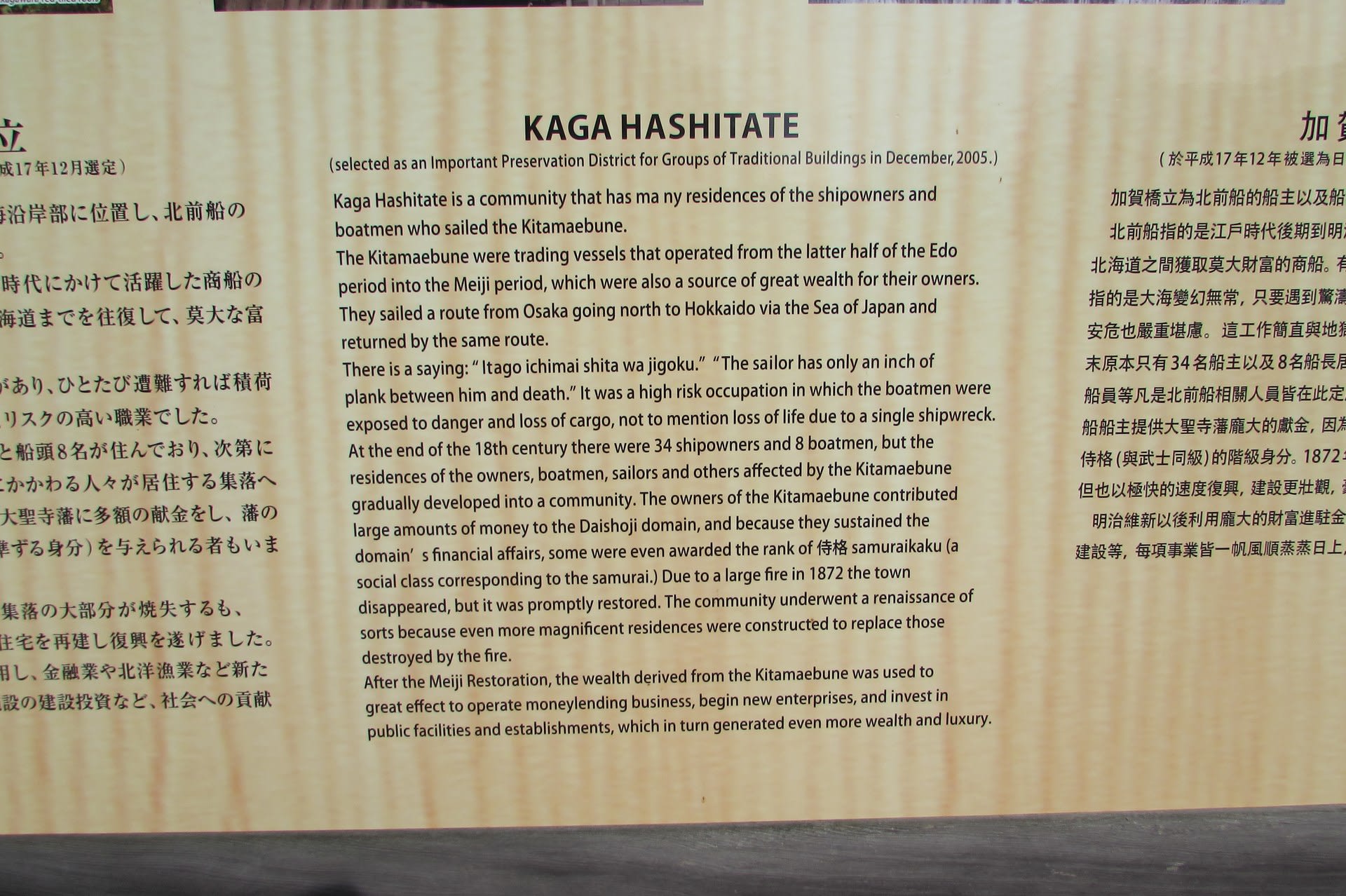
























北前船主屋敷蔵六園(旧酒谷長一郎家住宅)・登録有形文化財





雑感として、蔵が土塀ではなく、板張りであったことが印象的です。
橋立は、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。江戸後期から明治中期にかけて活躍した北前船の船主や船頭が多く居住した集落です。保存地区には往時の様子を伝える船主屋敷が起伏に富む地形に展開しています。敷石や石垣には淡緑青色の笏谷石(しゃくだにいし)が使われ、集落に柔らかな質感を与えています。
日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が認定し、様々な文化財を総合的に活用する取り組み支援する制度です。
日本海岸には、山を風景の一部に取り込む港町が点々とみられます。そこには、港に通じる小路が随所に走り、通りには広大な商家や豪壮な船主屋敷が建っています。また、社寺には奉納された船の絵馬や模型が残り、京など遠方に起源がる祭礼が行われ、節回しの似た民謡が唄われています。これらの港町は、各地の繁栄をもたらした北前船の寄港地・船主集落を形成してきました。
北前船は、江戸時代から明治時代にかけて繁栄した商売の形態のことで、大阪と北海道を往復し、莫大な富を得ました。北前船の商売の特徴は、他人の荷物を運んで運賃を稼ぐのではなく、船主が荷主として各地で物を売り買いしながら航海するという点にあります。そのため、うまく行けば大儲けできますが、失敗すれば大損、それどころか遭難すれば、命の危険にさらされることもありました。まさに「板子一枚下は地獄」といった状況だったのです。
加賀市橋立町には特に北前船主が多く、寛政8年(1796)の記録では、42名の船主の名がみえます。加賀市は船主のふる里と呼ぶにふさわしく、他にも瀬越町、塩屋町など船主が多く出た地域があります。
map


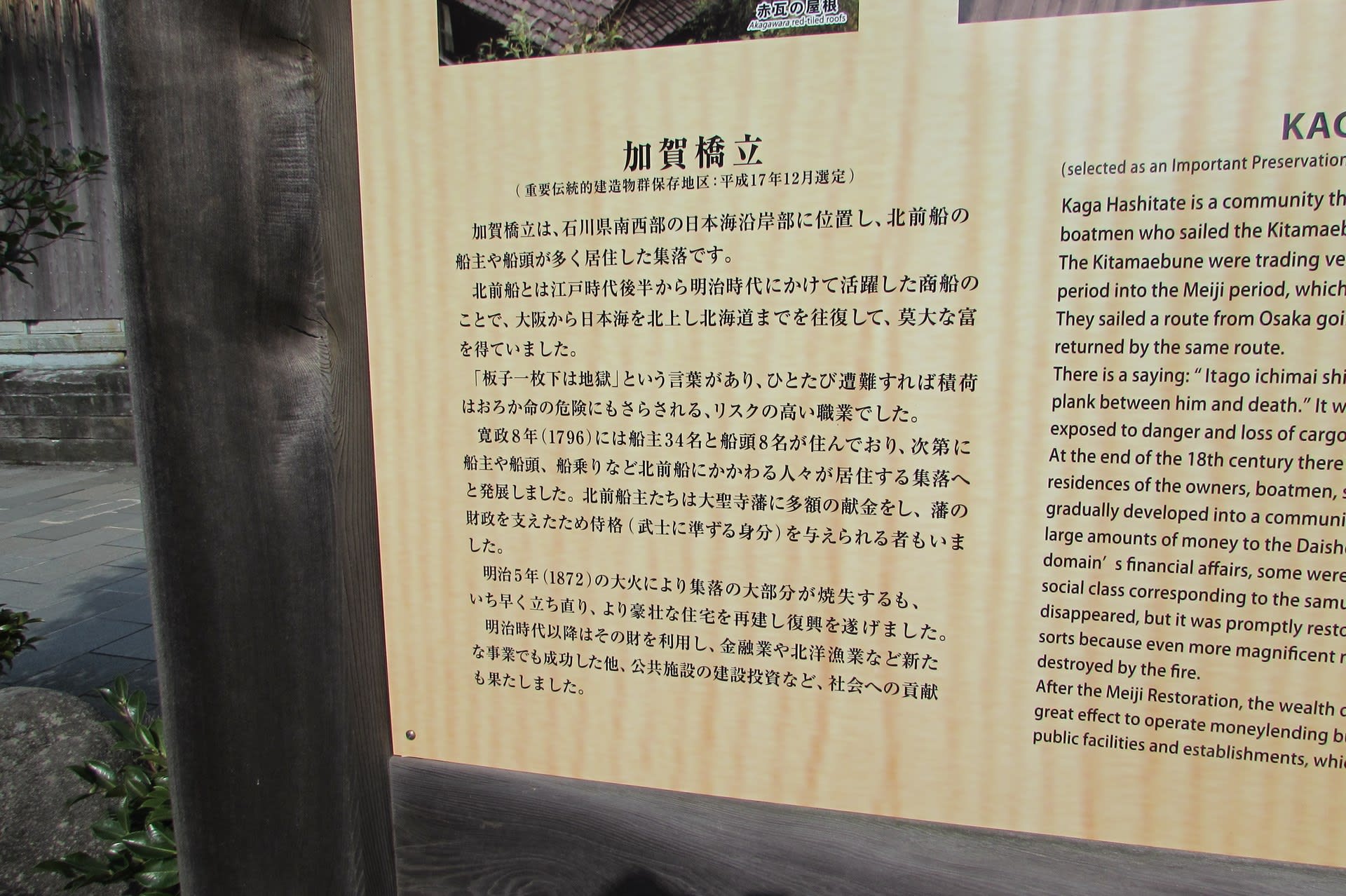
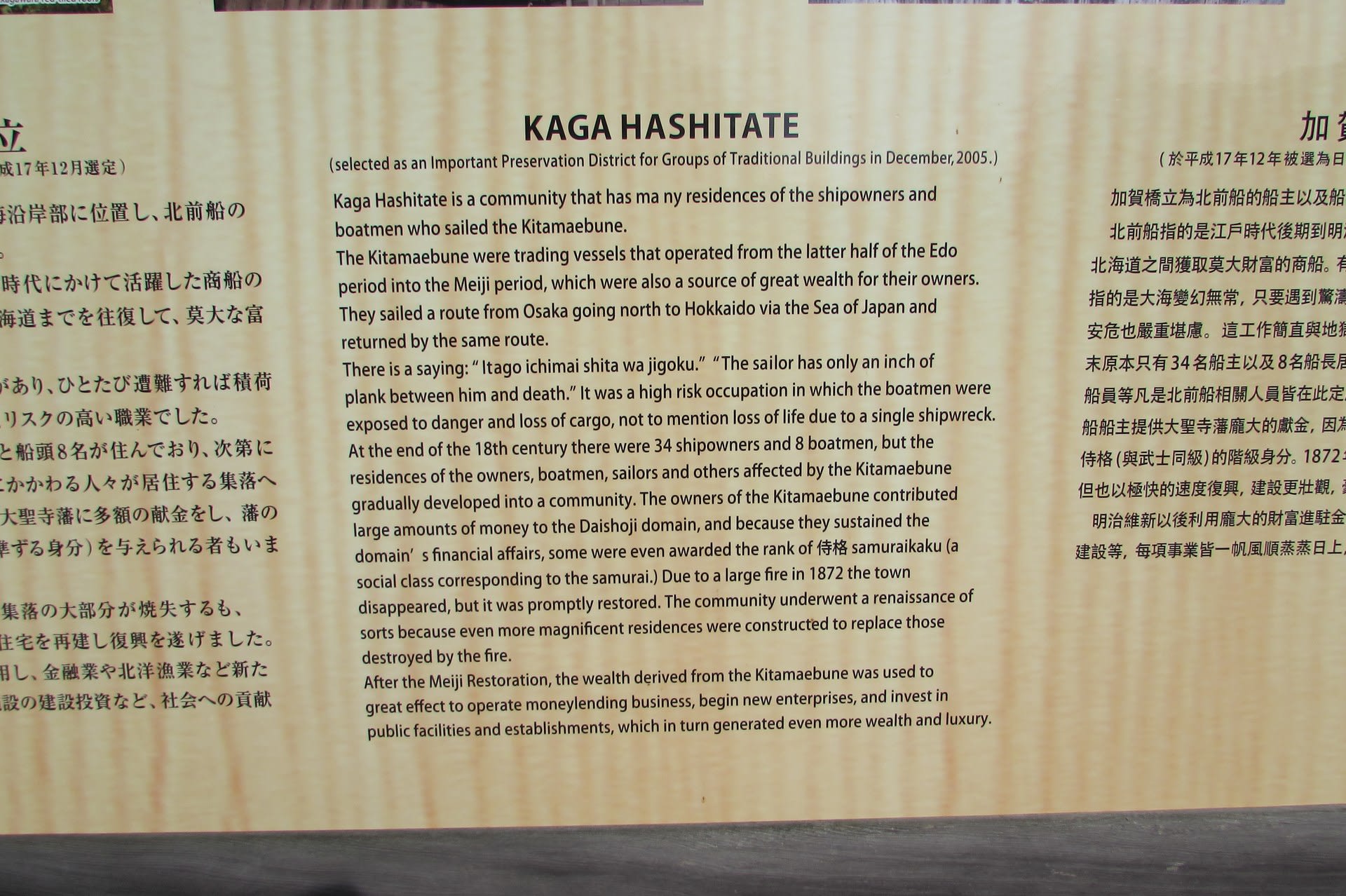
























北前船主屋敷蔵六園(旧酒谷長一郎家住宅)・登録有形文化財





雑感として、蔵が土塀ではなく、板張りであったことが印象的です。



























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます