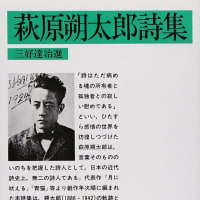LGBTの議論はトイレや浴場の問題にとどまらない。それ以上に重要なのはエロチシズムをどう考えるかなのである。性を慎しみ深い世界にとどめて置くのか、それとも社会の根幹を否定する革命運動と結び付け、自由なエロチシズムを謳歌する世界を目指すのかといった岐路に、私たちは立たされているような気がしてならない。
エロチシズムに対する足枷をなくせば、それで本当に全てが解決するのだろうか。あらゆる性的な行為が白昼の下にさらされれば、人間としての性の歓びを手にできるのだろうか。
性が秘め事であることで、人間は過剰な生をコントロールしてきたのではないか。人間には昼と夜との二つの顔があり、そこを往復して生きているのが人間ではないのか。それすらも偽善として許されないのだろうか。性を解放するカーニバルは、あくまでもハレの日のイベントである。それ以外はたわいもない日常であることで、ハレの日が大事になってくるのである。
あけっぴろげな性は逆にエロチシズムを衰退させることになりはしないか。LGBTの人たちが無理に自分を変える必要はないが、権力を振りかざす側に回ろうとするのには抵抗がある。禁制をなくした世界においては、逆に自分たちの居場所をなくすのではと危惧してしまうからだ。
だからこそ、何度でもG・バタイユの言葉を引用したくなるのである。これは人間への根源的な問いかけを含んでいる。全てが認められてしまえば、エロチシズムは生息する場を失うことになるというのだ。
「エロチシズムは禁制から生れ、禁制によっていきます。そしてもし自らのうちに禁制を持たなければ、もしエロチシズムの本質にたいしてこの禁制の感情を残していなければ、私のいったような意味で、すなわと侵犯を含む意味で私たちはエロチックであることはできないでしょう。動物とおなじかたちでしかエロチックでありえず、そして私たちにとって本質的なものに到達することはできないでありましょう」『マダム・エドワルダ』(生田耕作訳)
バタイユにとっての禁制とは、法的なレベルとともに個々人の感情までも含んでいる。マイノリティーの人権は保護されなくてはならないとしても、権力とは一定の距離を保つべきではないだろうか。プロレタリアートの名において行われた革命が、全体主義をもたらしたと同じ悲劇をもたらしかねないからである。