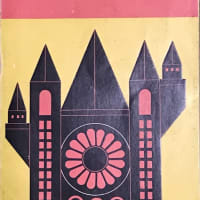2024年6月14日(金)
> 1910年(明治43年)6月14日、民俗学者、柳田国男の『遠野物語』が聚精堂から出版された。発行部数は350、定価は50銭だった。
遠野物語の冒頭は「この話はすべて遠野の人佐々木鏡石君より聞きたり」という一文で始まる。
柳田が話を聞き出した佐々木鏡石は、本名は佐々木喜善(きぜん)という。鏡石は雅号で、敬愛する泉鏡花から一字を取り、釜石の石と組み合わせたらしい。岩手県上閉伊(かみへい)郡土淵村に生まれ、文学を志して二十歳の時に上京し、哲学館に通った後、早稲田大学師範部の聴講生となった。その頃交友のあった水野葉舟が柳田と親しかった関係で柳田と出会うのである。
佐々木が訥々と語る話に興味を持った柳田は、毎月二日の夜に彼を家に招き、遠野に伝わる昔話や伝説、世間話を丹念に聞き書きしていく。その記録を整理して出来上がったのが『遠野物語』である。
『遠野物語』は、公刊時は知人・友人に寄贈されたに過ぎず反響も少なかったが、現在では日本民族学の古典として高い評価を得、多くの読者を獲得している。
晴山陽一『365日物語』(創英社/三省堂書店)P.171

柳田 國男(やなぎた くにお)
1875年(明治8年)7月31日 - 1962年(昭和37年)8月8日)
写真:https://ja.wikipedia.org/wiki/柳田國男
「冒頭」とは、初版序文のことである。
この話はすべて遠野の人佐々木鏡石君より聞きたり。昨明治四十二年の二月頃より始めて夜分をりをろ訪ね来たり。この話をせられしを筆記せしなり。鏡石君は話し上手にはあらざれども誠実なる人なり。自分もまた一字一句をも加減せず感じたるままを書きたり。思ふに遠野郷にはこの類の物語なほ数百件あるならん。わえわれはより多くを聞かんことを切望す。国内の山村にして遠野よりさらに物深き所には、また無数の山神山人の伝説あるべし。願はくはこれを語りて平地人を戦慄せしめよ。この書のごときは陳勝呉広のみ。
「陳勝呉広のみ」には驚いた。「王侯将相寧有種也(王侯将相いずくんぞ種あらんや)」、 「平地人」のおさまりかえった学堂を一撃せんとする意気の軒昂たること。そして実際、『遠野物語』は恐ろしく面白いのである。
山々の奥には山人住めり。栃内村和野の佐々木嘉兵衛といふ人は今も七十余にて生存せり。この翁若かりし頃猟をして山奥に入りしに、はるかなる岩の上に美しき女一人ありて、長き黒髪を梳りてゐたり。顔の色きはめて白し。不敵の男なれば直に銃を差し向けて打ち放せしに弾に応じて倒れたり。そこに馳け付けて見れば、身のたけ高き女にて、解きたる黒髪はまたそのたけよりも長かりき。後の験にせばやと思ひてその髪をいささか切り取り、これを綰(わが)ねて懐に入れ、やがて家路に向かひしに、道の程にて耐へがたく睡眠を催しければ、しばらく物蔭に立ち寄りてまどろみたり。その間夢と現との境のやうなる時に、これも丈の高き男一人近よりて懐中に手を差し入れ、かの綰ねたる黒髪を取り返し立ち去ると見ればたちまち眠りは覚めたり。山男なるべしといへり。
たとえば芥川は『遠野物語』を知っていただろうか。彼が『宇治拾遺物語』や『今昔物語』に取材したように、『遠野物語』に想を求めるということは成り立つものだっただろうか。
Ω