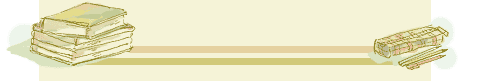立春の今日も、こちらは快晴に恵まれました。
昨日も、そして今日もその晴天は1日中続き、
太陽燦々の空の下(もと)は、まるで春が来たかのよう。
本来でしたら・・。「立春とは名のみの厳しい寒さが続いています」
~なんて書き出しが常だったと思うのです。
一方、豪雪に見舞われた方々や、
火山灰の被害に遭われた方々のご苦労を思います。
雪は春が来れば解けますが、火山の噴火の終息は
予測がつきませんものね。1日も早い終息を願ってやみません。
さて、今日のタイトルとは似ても似つかない、この世の花である優雅な薔薇。
この季節ですから、ゆっくり、ゆっくり・・と開花してくれています。
開花するに従って、凛とした姿から小首を傾げ、
もの想う風情になって来たようです。
庭からの付き合いですから、もう何か月も。
こうなれば、1日も長く傍にいてくれる事を願うばかりです。
ところで、昨日も触れた 「鬼」 の事。
絵本の中の鬼は、なぜかユーモラスと記しましたね。
民俗学専門の小松和彦著 『酒天童子の首』 によれば、鬼とは・・。
「人間が抱く人間の否定形、つまり反社会的、
反道徳的人間として造形されたもの」 と定義されています。
つまり鬼とは、『かくあるべき人間』 を否定した一種の鏡像なのだとか。
「人を殺してはいけない」 「ものを盗んではいけない」
「真面目に働かなければいけない」 等など。
これらを否定した存在が 「鬼」 という訳です。
ですから、働かず、夜ごと宴会を開いて酒を飲み、盗み、殺すのが 「鬼」。
これらは本来、人間がしてはならない事だったのですね。
という事は、いつの間にか人間が 「鬼」 になってしまったという事でしょう。
特に現代は、恐れの感覚が薄くなったと言います。
しかしながら、日本各地に残る数々の鬼伝説。
その事からも、鬼に恐れ、おののき律して来た日本人だった筈。
その原因には様々な事が挙げられるでしょう。
戦後60有余年、「拝金主義」 と 「無神論」 が世の中を席巻(せっけん)。
宗教的な恐れが全くなくなってしまったからかも知れません。
不夜城と言われて久しい昨今ですが、昼も夜もなくなった現代の都市。
鬼などを持ち出すまでもなく、恐怖すら消費される時代となったようです。
折しも今、読んでいる三浦綾子著 『泥流地帯』。
冒頭から今ではあまり見る事のなくなった、暗闇の世界が広がっています。
この小説の根底には、きちんとした宗教観が備わっている事は周知の事実です。
そう思って眺めますと、単なる暗闇の描写に過ぎないと思っていたものに、
特別の意味を持ってしまいます。
まだ全部読んだ訳ではありませんが、親がいないのに、
この兄弟の素晴らしい人間形成を鑑(かんが)みた時、
暗闇の世界・・恐れ、おののきも必要なのでは・・と思ってしまいます。

| 外は闇だった。 星光一つ見えない。まるで墨を塗ったような、真っ暗闇だ。 あまりの暗さに、外に出た拓一は、ぶるっと体をふるわせる。 いつもこうなのだ。もう 6年生だというのに、拓一は夜、 外に出るのが恐ろしい。 (中略) 用を足しながら、拓一はじっと闇に目をこらす。 手でかきまわせば、闇がねっとり手の先についてくるような 気がする。すぐ前にある収穫の終わったえんどう畠も、 その向こうにぞっくりと繁るエゾ松林も、小高い山も、 ただ闇の中だ。 (中略) ・・・7、8町向こうに、ポッと黄色い灯が見えた。 灯が右に左へ揺れる。拓一は後ずさりした。 (狐火か!?) 闇夜に見える遠い灯は無気味だ。 (提灯かも知れない) そう思った時、いきなり灯が消えた。 寒気がざわざわと背筋を走る。 と思う間もなく、又ぽっかりと灯が揺れる。 言いようもない恐ろしさに、拓一は一目散に 戸口に走る。引戸をがたぴしさせて、漸く家に入る。 三浦綾子作 「泥流地帯」 より |