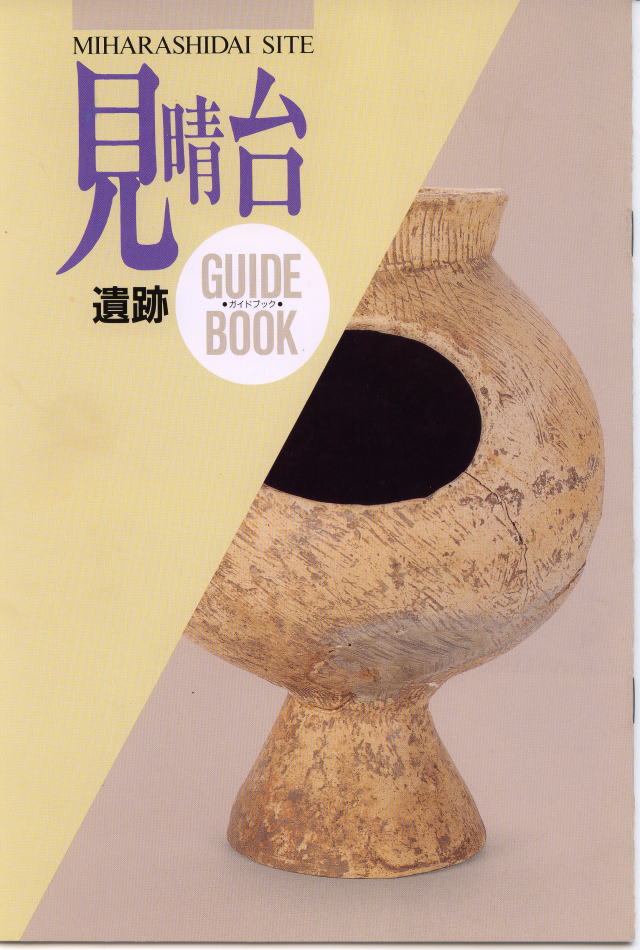家康から「源」をもらい、明眼寺から妙源寺へ
さらに、家康側についたお寺があります。こちらのほうが有名です。桑子の妙源寺です。もともとは明眼寺という字だったようです。寺内の案内板に三河一向一揆で家康側についたので、家康から「源」(源氏の源という意味でしょうか)の字をいただき、妙源寺と改めたとあります。

妙源寺 本堂
徳川氏の庇護を受けた証として葵のご紋がありました。

妙源寺を開いたのは、安藤信平と言うこの地域の在地武士のようです。1235年に親鸞を柳堂に招いて説法を受け、浄土真宗に帰依したそうです。

妙源寺 柳堂 聖徳太子の像があるそうです。
上宮寺を見張る見張り台?
三河一向一揆当時を偲ばせるような山門がありました。山門と言うより見張り台のように見えました。

桑子と上宮寺(佐々木)は、目と鼻の先です。

この見張り台から上宮寺の様子を見張り動きがあれば岡崎に知らせていたのではないでしょうか。
真宗でも武士のお墓が
裏の方にまわりましたら、大きなお墓がありました。

どれがどれだかはっきり私には分かりませんが、ネットで調べたところ、安藤直次、本多忠豊、本多忠高、高木正清、平岩親吉、長坂血槍九朗のお墓らしいです。先日の講演会で青木馨氏は浄土真宗では菩提寺としての働きはないと言っていて、しかしなお「桑子は例外です。」と言っていました。真宗高田派のお寺ですが、武士のお墓を守ることもしたようです。
さらに、家康側についたお寺があります。こちらのほうが有名です。桑子の妙源寺です。もともとは明眼寺という字だったようです。寺内の案内板に三河一向一揆で家康側についたので、家康から「源」(源氏の源という意味でしょうか)の字をいただき、妙源寺と改めたとあります。

妙源寺 本堂
徳川氏の庇護を受けた証として葵のご紋がありました。

妙源寺を開いたのは、安藤信平と言うこの地域の在地武士のようです。1235年に親鸞を柳堂に招いて説法を受け、浄土真宗に帰依したそうです。

妙源寺 柳堂 聖徳太子の像があるそうです。
上宮寺を見張る見張り台?
三河一向一揆当時を偲ばせるような山門がありました。山門と言うより見張り台のように見えました。

桑子と上宮寺(佐々木)は、目と鼻の先です。

この見張り台から上宮寺の様子を見張り動きがあれば岡崎に知らせていたのではないでしょうか。
真宗でも武士のお墓が
裏の方にまわりましたら、大きなお墓がありました。

どれがどれだかはっきり私には分かりませんが、ネットで調べたところ、安藤直次、本多忠豊、本多忠高、高木正清、平岩親吉、長坂血槍九朗のお墓らしいです。先日の講演会で青木馨氏は浄土真宗では菩提寺としての働きはないと言っていて、しかしなお「桑子は例外です。」と言っていました。真宗高田派のお寺ですが、武士のお墓を守ることもしたようです。