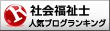『家族看護』Vol.06 No.02
いわゆる「がん家族」に焦点を当て、その立ち位置、言動が表わすこと、援助者からのとらえ方(理解するための手がかり)等が述べられている。
家族は「第二の患者」なのか?という問いから、「患者であるなら病気を有しているのか、否か…」という追及は、とても興味深い。
引用
・「家族は第二の患者」という表現は、サイコオンコロジー(精神腫瘍学)の領域から出てきたものである。
・「医療者から不可解に見える家族の言動は、実は大きなストレス下におかれた時の反応であり、(中略)家族の正常な反応なのである」


「家族の意思決定と生活の変化」を時系列で表にまとめ、説明している箇所がある。
そのなかに、「日常(生活)」「非日常(医療)」という表現があり、ターミナル期になればなるほど、「非日常(医療)」が占める部分が多くなる…となっている。
「医療=非日常」という意味なのか?
この表現が、「病院死はその人らしさを出しにくい、非日常的な空間」と同様の意味の範疇であれば、これはその通りであると思う。
しかし一方で、例えば先天性の疾患があり、常に医療と密接な間柄にいる人にとっては、この表現はとても酷なのではないかと感じた。
「病院での死が多くなり、死が日常の中にない」ということも言われている。
「日常」「非日常」・・・この表現は、とても分かりやすいようでいて、実は難しい表現であると痛感した。
いわゆる「がん家族」に焦点を当て、その立ち位置、言動が表わすこと、援助者からのとらえ方(理解するための手がかり)等が述べられている。
家族は「第二の患者」なのか?という問いから、「患者であるなら病気を有しているのか、否か…」という追及は、とても興味深い。
引用

・「家族は第二の患者」という表現は、サイコオンコロジー(精神腫瘍学)の領域から出てきたものである。
・「医療者から不可解に見える家族の言動は、実は大きなストレス下におかれた時の反応であり、(中略)家族の正常な反応なのである」


「家族の意思決定と生活の変化」を時系列で表にまとめ、説明している箇所がある。
そのなかに、「日常(生活)」「非日常(医療)」という表現があり、ターミナル期になればなるほど、「非日常(医療)」が占める部分が多くなる…となっている。
「医療=非日常」という意味なのか?
この表現が、「病院死はその人らしさを出しにくい、非日常的な空間」と同様の意味の範疇であれば、これはその通りであると思う。
しかし一方で、例えば先天性の疾患があり、常に医療と密接な間柄にいる人にとっては、この表現はとても酷なのではないかと感じた。
「病院での死が多くなり、死が日常の中にない」ということも言われている。
「日常」「非日常」・・・この表現は、とても分かりやすいようでいて、実は難しい表現であると痛感した。