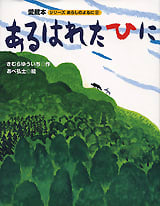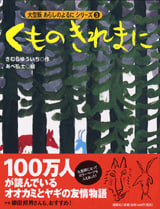グドーさんのおさんぽびより/文・たかどの ほうこ 絵・佐々木マキ/福音館書店/2018年
春夏秋冬おのおの5話づつ、春からはじまり春でおわる20話。
大事件がおこるわけではありませんが、日常生活ではちょっとした出来事が。
息の合った中年のグドーさん、イカサワさん、9歳のキーコちゃんが、お散歩したり喫茶店にいってだべったりします。
「とっさのひとこと」ってなに?
イカサワさんが、外国人の若者から道を聞かれとっさに出た英語。昔覚えた文がすらすらでてきて、「二つ目の角を曲がって、5,6分歩くと右手に駅が見えます」と答えます。でも本当は二つ目の角にあるバス停から駅生きのバスに乗ってください」といわなければならなかったのです。
言い間違えて青ざめたイトカワさんに、グドーさんは「そっちにいって偶然いいことがあるかもしれない」と無責任にいいます。
散歩をつづけていると、通りの反対側に、さっきの若者が。
若者は以前世話になったおばさんを訪ねるところでしたが、たまたまデパートに買い物に来たおばさんと出会ったのです。
イトカワさんの間違いで、若者はおばさんにあえたのです。ただしく行ったら、おばさんは留守でした。
「アマリリス」
キーコちゃんが、ゴドーさんに鉢植えのアマリリスをもっていくと、ちょうどイトカワさんと<アマリリス>を合奏するところ。
イトカワさんは、チェロ、グドーさんはフルート。キーコちゃんは体育すわりをすると合奏がはじまります。
ところが、なんともうるさい音、チェロもフルートも何とも言えない音。ところがアマリリスが音から遠ざかろうと身をかたむけ、そのうち上へ上へ伸びあがっていきます。
ところが合奏がおわったとたん、アマリリスが、とじていた花びらが、つめていた息をはきだすようにラッパの形に開きました。
音楽の偉大さに感激した三人でした。
どの話もオチがあって楽しめました。佐々木マキさんの絵もほのぼのしています。