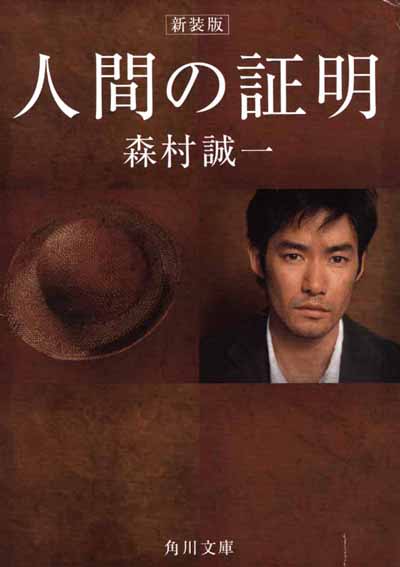つちのこカメラ13
MAMIYAC330S

生産中止直前に購入。
55mm、80mm、135mmとまとめ買いでした。
通常の撮影にはペンタ67で、シンクロの都合などで、たまにハッセルとローライと、使い分けだった。
戦後日本の復興と共に使われていたカメラが生産中止となるので、これは1台手元においておきたいと思った。15年ほど前のことです。
使い心地は、一眼レフに比べると煩雑な感はやむをえないが、写りは値段の割りに素晴らしかった。
マミヤのレンズは絞り込むと、ものすごくシャープになる物が多く、反対に絞りが開放では疑問があるものも。C330はレンズシャッターなので手持ち撮影でぶれないのが特徴。フィルムサイズが大きくぶれないから、使いようによっては威力を発揮するのです。
ストロボと連動させて外での撮影などに良い。しかし、、、ごろんとしたスタイルは、古めかしくコレを仕事に使う気にはならないでしょう。モデルさんがビックリしてしまうし、クライアントが心配顔になる。実際は、見てくれを考えなければ、素晴らしいカメラだと断言します。

C330が縦に長いのは、フィルム巻取りが、下から上へ一直線に巻き上げているからです。普通の2眼レフは下に入れた未撮のフィルムは一度90度曲げられて、上で巻き取られます。
直線的にしたのは、フィルムの平面性を考慮したからで、フィルムが曲げられるタイプは長期間入れっぱなしにされるとフィルムにクセが付くからです。
わずか、ひとコマですが、フィルムが貴重な時代には、よく出来た設計だったんでしょう。
メカニカルなカメラで、いろんな所にロックがあり、しばらく使わないと手も足もでません。動かないよー助けてクレーです。。。

横から見るとローライなどに比べ縦長で大きいのがわかる。実際持つと大きい感じがします。マミヤのRZにしても前身のRBにしても無骨なぐらいでっかい。
右上の丸ノブは巻き取りスプール用とバックを開けるもの。小さなレバーを下げてノブをプッシュする。
真ん中の大きな丸は、ファインダーの中のパララックスを修正するもの。レンズごとに切り替えします。内側がレンズ交換する時に遮光板を立てるレバー。
遮光板を立てないと、レンズにロックがかかったままで外れません。
下の棒状のようなものは、接写をしたときの、レンズによる露出倍数を表示しています。
下前の大きなノブでレンズ全体を繰り出しピントを合わせます。ノブのストッパーもあります。

マミヤの大判カメラはラックアンドピニオンと蛇腹を使った物が多い。
蛇腹を使うことで、レンズの繰り出しが大きくできます。つまり、接写がきくということで、多くのプロが使った理由のひとつでしょう。
便利な反面、やや古めかしい感じにはなります。

クランク巻上げです。
C220などは巻上げとシャッターチャージが別々だと思いました。
シャッターボタンはいちばん下にある。もうひとつが小さくLと書かれた右側の黒いレバー。シャッターボタンは使いやすいように2個ありました。
レンズ交換ができるので、180mmや250mmは重心が前に移動するので、ホールディングなどから下のボタンがやりやすかった。

ファインダーは引き上げればパチンと開いて、閉じる時もワンタッチ。ファインダーの前蓋をさらに押し込むと、素通しのアングルファインダーになる。

私は二眼レフを使う時は、よくこの素通しファインダーを使いました。
ローライ二眼レフのファインダーにはカラクリが仕込まれていて、素通しファインダー使用でも、目をわずかにずらしてピントグラスを覗き、ピントを合わせられました。
しかし、マミヤC330にはソノ機構は付いていない。レンズ交換できるので、そのほうがウリなのでしょう。

裏蓋を開けたところです。
フィルムは下から上へと直線的に巻き上げます。
この機構にこだわったため、図体が大きくなった可能性大。
レンズ交換をするため、遮光板を組み込んだり、パララックスを修正したり、考えられる全てをぶち込んだ贅沢なカメラでした。
これを外国メーカーが作ったら、5倍ぐらいの価格になったかもしれない。ローライなどは当然考えただろうけど、バカバカしくなって止めたんだと思う。それほど実直なカメラなんだC330は。すぐに一眼レフの時代になって、脚光を浴びた期間が短かったような、、、。
ローライのカラクリはロック部が特に洒落ているけど、マミヤのカラクリは、もっと馬鹿正直で一途な感じがします。

ファインダーはネジを緩めてはずします。スクリーンも交換可能。プリズムファインダーって言うのもカタログにはありました。でも、、、プリズムを使うんだったら、ペンタ67を使えよーって思うけど、、、。
このあたりの造り、発想はローライやハッセルと違い、手堅い造りだなーって思います。
ハッセルはサホドカラクリを感じないし、精度を出すのがタイヘンな造りだと思う。ハッセルの欠点と言えばそのくらいですが、わずかな歪みや衝撃で精度が落ちると故障して使えなくなる。
その点でニコンやライカは、雑に扱っても使える報道カメラとして設計されていると思います。
無骨なマミヤとスマートでコンパクトな外国製カメラの図式がその当時ありましたが、ユーザー数の多かったのが、おそらくマミヤです。ソレは日本国内だけじゃなく国外でも一緒でした。外国に行くと、なんでハッセルなど使っているの??日本には凄いRZやペンタ67があるじゃない??と言われたものです。外国のカメラマンもRZ、ペンタ、ブロニカを高く評価していました。結局、世界のプロが頼りにしていたのは、無骨でもシッカリ働いてくれる日本製カメラだったんです。車と一緒だと思いますよーーー。こんなことは、カメラ雑誌でも、グッズ雑誌でも書いてありませんが、言ったら面白みがないということなのかもしれない!!
この、マミヤC330は機構が、特にロックが煩雑です。万が一壊れても、作りが大雑把なので、意外に素人修理ができるのではと思う。

55mmが人気らしいが、135mmもいいですよ!
ゾナーの150mmに比べれば、お値段はウンでの差、、、。
写りは素晴らしくシャープ!
ある意味で高みに行き着いた二眼レフ。
アサヒペンタックス67mp記事
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20100421
フォクトレンダー ブリアントの記事
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20080828
ハッセルブラッド500Cの記事
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20071002
ローライフレックス 3.5F 220の記事
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20081024
 ランナーでファンの人は数多くいますが、近くによった時、和やかな気持にさせられるのは千葉さんがいちばんだった。
ランナーでファンの人は数多くいますが、近くによった時、和やかな気持にさせられるのは千葉さんがいちばんだった。