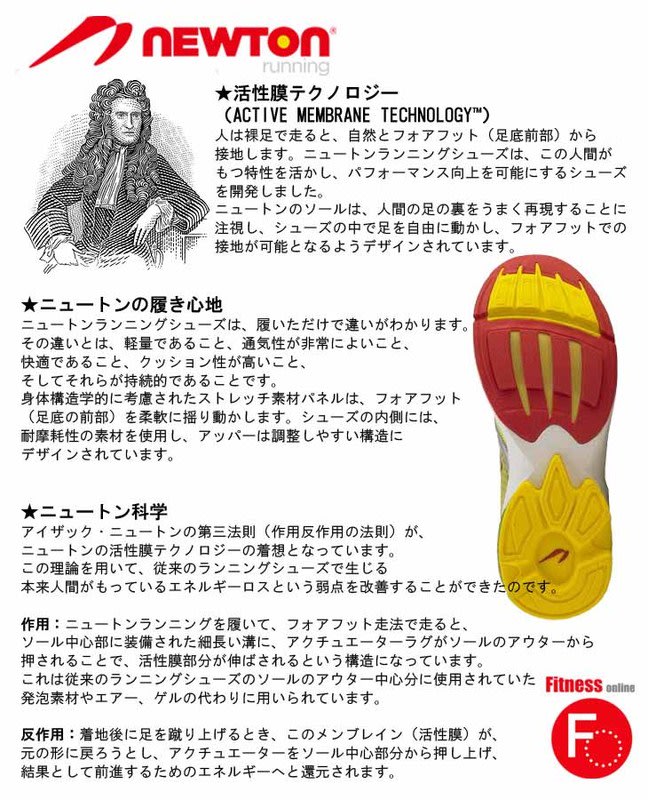つちのこカメラシリーズⅩ ②
TOYO FIELD45A
「あおり」の解説と使い方
カメラ各部の説明は
http://runshimo.blog.ocn.ne.jp/shoji/2007/06/post_adfa.html

45カメラは大きいだけじゃなく、あおりができるのが特徴。
45カメラ&あおりが世の中からなくなる前に、忘れ去られる前に、これを記します。
しかし、トヨフィールドであおりを使うのは、ほんのスパイスみたいなものでしたが、、、。

撮影スタンバイOK

フロントライズ、前上げです。
低い位置から建築などを撮影する時に使います。
この場合、後が垂直より前に倒れることはありえない。
前が若干上を向くことはあります。レンズのイメージサークルが小さかったら、逃がしのために上を向けます。
当然ピントが悪くなるので、絞り込んでピントを深くします。

フロントダウン、前下げです。
商品を上目から撮影する時の形です。
この場合は、前が若干前傾することもあります。
イメージサークルとピントの問題が発生します。
リンホフボードを取り付けると、レンズセンターが下に来ます。
前をフォールしたい時の量をこれで確保しているのです。
フロントライズの量は、上を伸ばせば増やせる可能性があるからです。

フロントライズの応用。
ベットごと上に向けて前を前傾させて垂直をだします。
後も同じようにすると、上下のあおりが大きくできます。

ベットダウンです。
かなり大きなイメージサークルを持っているレンズである必要があります。

フロントティルトですが、このティルトは前をダウンするのが普通で、このままでは使いません。ティルトの形にしただけです。
レンズのセンターとフィルムのセンターを見れば、どこを狙っているかわかります。
すると、、、真正面のものを、こんな形(ティルト)にあおって撮ることはありえません。

あまり使うことのない形です。
というか、撮影の現場ではありえない形です。
45カメラを使っている写真を見ると、「おや、おかしな使い方をしているぞ」と最近見かけます。アマチュアーの方だったら楽しみだから許されますが、プロがやっていたら鉄扇ものです。
使うなら勉強されて、奥義をきわめてください。美しい愛すべき45カメラのためにも、、、!

この形のままは使いません。
必ず全体を前に倒します。それも後が垂直になるのが原則ですが、それよりも前傾することはあります。
ただ、後が垂直より後に傾くことは光学的にあまり普通じゃない、、、。
しかし、通常ではない形ですが、やってはいけないわけではありません。

この形には普通ならないはず!
全体を上に向けて天井を撮影する時ぐらいです。
形から覚えるのもひとつです。

シフト。
フロントを右に10mm動かしました。
フィールドカメラはこの動作が苦手です。
あまり使うこともない機能ですが、あると便利です。
ビューカメラはシフト量がフィールドカメラに比べて大きい。
シフト&ライズ、フォールの量が大きいのです。

前部のスイング。
フィールドカメラでは、これが必要な撮影は少なかった。

前と後ろをスイングしています。

後スイングのストッパーはボディー下にある2つのレバー。
普通あおりを使う時は、全てのあおりを駆使していました。
この状態でテイルトする場合もあります。

トヨフィールドとトヨビューはリボリングできます。
全く同じ機構のカメラバックでした。
ただし、この位置ではフィルムにケラレがでます。
途中はなしと考えてください。

ピントグラスをはずすと理由がわかります。
角々がけられています。
回るのとこの状態で使えるのとは別。
ピントグラスをはずして、JIS規格のロールホルダーなどが使えました。

今、レンズは付いていませんが、目の位置をここに持って行き、レンズのけられなどを確認することがあります。
レンズの絞りによる口径喰がよくわかります。絞りがハマグリ状に見えます。

蛇腹が健全かどうかを確認するのは、暗い所で、蛇腹の中にランプ(100wまで)を入れて、回りから光が漏れないか見ます。
蛇腹に穴が開いていると、星のようにチラチラします。
それ以外のチェックは、難しいでしょう。
蛇腹にピンホールがあったら、フィルムに変な光りが写り込みます。おかしいなーと感じたら、たいていは蛇腹の穴か、フレームのガタなど。フィルムホルダーが意外に精度が出ていなかったり、すり減ったテレンプから光りが入ることもあります。太陽やストロボの光源が近くにあったり、カメラ本体に直射であたったりしているときは、かぶりの黒布でカメラを覆います。これはプロの儀式で、私は直射が無くても常時かぶりをカメラにかけていました。引き蓋を引くときは上を注意してください。引き蓋の隙間から光が入ることがあります。フィルムホルダーをカメラバックに差し込むときは、私たちはカメラについているレバーは使いませんでした。それを使うと、かえってホルダーが引っかかってやりにくい。カメラメーカの開発と使用する人の感性の違いです。メーカーの設計者がすべて全能ではない。おかしな所も良くあります。

カメラのバックを外すと、、、蛇腹が付いたただの箱になります。
トヨフィールドのカメラバックと、トヨビューのカメラバックが共通だったのは便利でした。
レぼリング機能は国産では当たり前でしたが、外国製の45カメラではリンフォフテヒニカぐらいだった。

下側にある2つのレバーが、後のスイングストップレバー。
うしろはスイングとティルトができます。
シフトとライズ&フォールはできません。

これからピンとグラスをのぞきます。
ピントフードの丸ポッチを触るとパタンとスプリングで開きます。

かぶり布は必需品です。
これだけじゃフレームもピントもわかりずらい。

ルーペで画面を見ますが、かぶり布がないと、全く見えません。
かぶり布は暗ければ何でもよい。適当な大きさを自分で作るのがよい。
市販である必要は全然ない。
自分では2枚作っていました。マジックテープをあちこちに縫い付けて、どこでもパッと止められて便利でした。

実際はピントフードはじゃまなもの。
プロは最初からフードをはずしていました。
ルーペで見るときにフードがじゃななんです。
簡単に外れます。トヨフィールドでは、フードはガラスの保護という意味合いがあるけど、ビューカメラだとただただ邪魔なだけ。

ピントフードのピンがスプリングになっています。

ピントグラスも外れます。
ぎざぎざの所を押さえて上に押すようにすると、下にある鍵状のつめが外れて、ピントグラスが外れます。

かぎが下にあるちいさなピンにはまります。
取り付ける時は、反対に乗っけてからぎざぎざを下に押すようにすると、ぱちんと入る。
左のレバーはレボリングのストッパーです。

このレバーはフィルムホルダーを入れるときに使うものですが、私はほとんど使わなかった。
フィルムホルダーを持ってピントグラスをちょいとつまんで、フィルムホルダーをこじ入れていた。
それがカメラマンの普通の使い方。機構としてあるけど良いわけじゃない。厚みのあるポラホルダーを入れるときぐらいでした、これを使ったのは、、、。

分解できます。
ピントグラスは適当(適切な良いものを)に自分で作ったり、ピントだししていました。ジナーやリンホフにトヨビューのグラスを使うのが普通でした。パーツは国産が意外に良いからです。全体の設計や考え方はドイツ製が良いけど、パーツが今イチのときもあります。蛇腹もフレームに好きなメーカーや特注品で作ったりしています。プロは製品をそのまま使うことはまれでした。

65mm
このレンズだけ、現役オールドカメラマンさんに使ってもらっている。
プレゼントですよーーー。

135mm

210mm

360mmにかませが3枚付けています。蛇腹長が足りないからです。
500mm(後群を変えると焦点距離が変わる)

360mmと500mmでは開放値が違い、ちょうど1絞りの差があるので、合わせる数値が違います。私は持っていなかったが720mmになるリアーもありました。
この360mm、500mmはシャープでした。他社製の長焦点など比べられなかったぐらい良いレンズです。
フジノンTを手放してこのニッコール360・500をゲットしました。通常の長玉レンズにはにじみがある。このEDレンズは、35mm用の高価なレンズの大三元レンズと同じように実にシャープです。
仕事に使っていたので要求はシビアーで、使用に耐えなくて捨てたり交換してもらったレンズは、35mm用や45用でいくつもあります。有名メーカー品でも設計が悪いのがありますから、買って使わなきゃわからないものです。
雑誌のテスト記事はけっこう甘くホントのことは書きにくいですから。
持ちつ持たれつで、悪いことは書けないのでしょう。

最後に、、、あおりを使う時は、ピントに関することは前部で、形を変形するには後部で、が光学的な原則です。
実際は、両方のあおりを組み合わせて使っていました。
トヨフィールド①組み立てかた、各部の説明は
http://blog.goo.ne.jp/photostudioon/d/20070628
OnPhotoスタジオ・ライテング講座は
http://onphoto.co.jp/newpage3.htm
お問い合わせは 東京新宿スタジオオンへ、何でも相談してください
studioon@fine.ocn.ne.jp