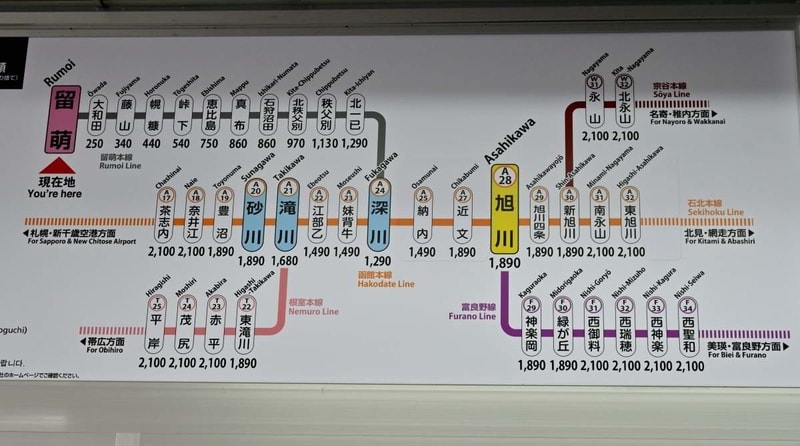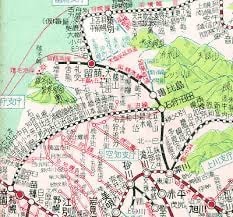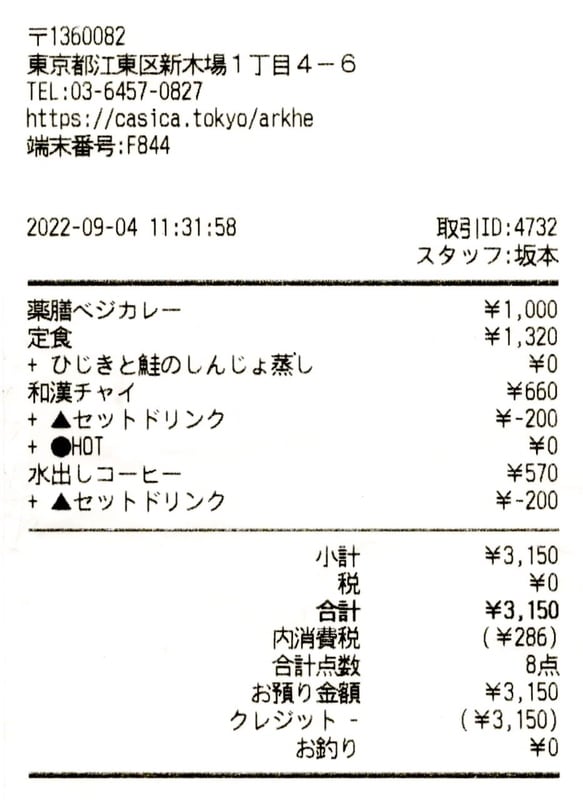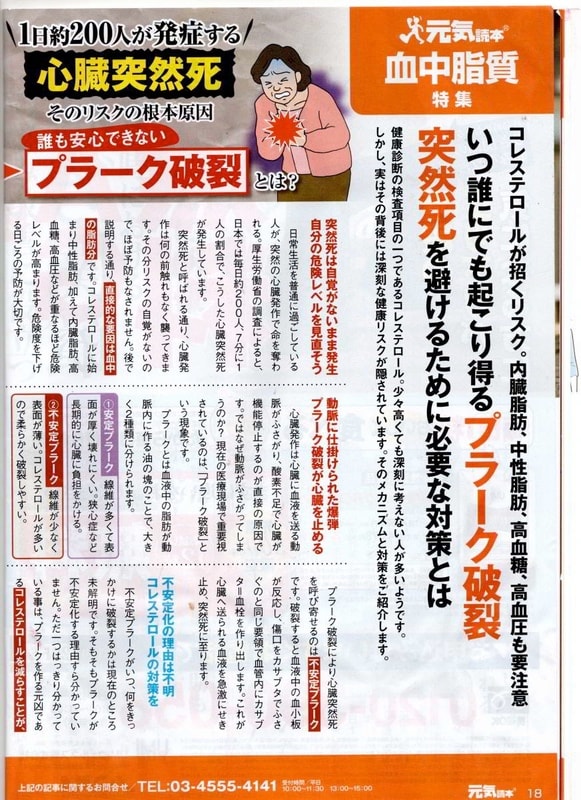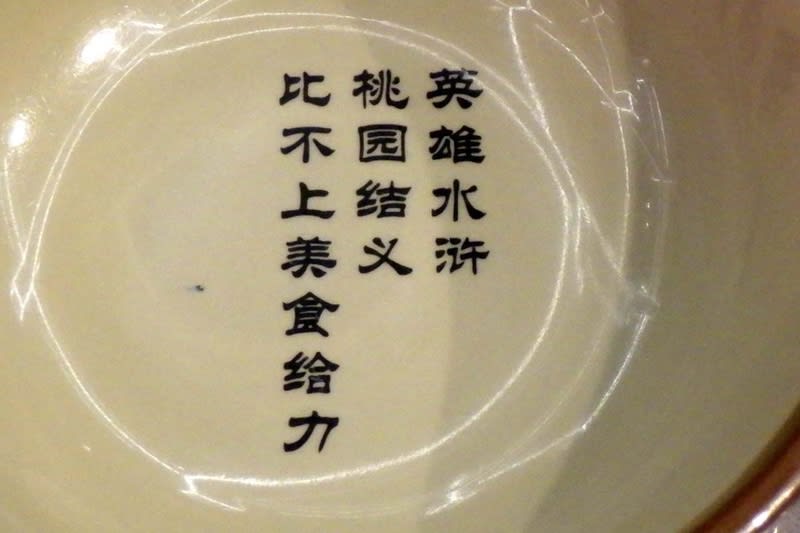歩きカメラ26、鮫洲から大森(旧東海道)
今日の歩きカメラは6人
暑い日差しの中を京浜急行の鮫洲に降り立った。
旧東海道は品川から横浜まで東京湾の海べりを通っていた。
********************
Aさんの見たものは

鮫洲の八幡神社がスタートだった。
立派な獅子のようです。
獅子の子供が足元で守られています。
神社では狛犬と言われていますが、口を開けたものが獅子で口を閉じたものが狛犬という説があります。
それで狛犬とし獅子がセットになっているのが多いそうだ。
神社ではキツネも見かけますが、それは神のお使いという立場で狛狐とは言わないそうです。
キツネは門番じゃないんんだな。
神の使いは牛や猿の場合もありますね。

現在の旧東海道は京浜運河に沿っています。
旧東海道が幹線道路として使われていた頃は、海(東京湾)に面した海辺の道だった。

コスモスの季節になりました。

お店の庭先に「江戸はあっち」という石柱があった。
人差し指で「江戸は右」を指しています。

竹の子せんべいが売っていた。
大黒屋さん立会川店です。
お話を聞いたところ、大黒屋さんは昔は目黒にお店があって、その時の頃の目黒には竹藪がいっぱいあったそうです。
そこで目黒時代に竹の子煎餅を作って売っていて名物になり、立会川に移ってきても竹の子煎餅を売り続けています。
目黒は、落語で「目黒の秋刀魚」で有名ですが、実際は竹の子のいちだい産地だった。
目黒の竹の子の育て方は、netで調べると面白い。

鮫洲、立会川、青物横丁界隈は子供が多い。
元気に自転車で走り回っていた。
********************
Bさんの見たものは

由緒ありそうな八幡神社。
鮫洲の由来が書いてあった。
鮫洲は昔は海辺だったので、砂の中から清水が湧き出ていたので「 砂水 さみず 」と言われ、それが変化したものと言われている。

神社には大きな神輿が安置してあった。
これだけのお神輿だと担ぐのに60人は必要です。
1960年頃に浅草の宮本与之助商店で修理されたと書いてあった。
当時のお金で30万円だったそうです。
今でいえば1千万円ぐらいかな。
でも最近はこの巨大神輿の出番はないそうです。
60人で4クルーだったら240人の揃った担ぎ手が必要になります。
今だったら浅草だったらいざしれず、そんな人数を集められる町内は少ない。
新宿・淀橋青果市場の巨大神輿も日本中から援軍(バス何台も連ねてくる)を呼ばなきゃ祭りでかつげません。
ただ1回だけ担がせてもらったら、屈強な担ぎ手が揃っていると、小さなお神輿でバラバラな担ぎ手よりも、はるかに楽だった。

品川花街道と呼ばれている。
以前は雑草だらけで、誰も近寄らなかった運河沿いだったが、住人達の整備で10年で見違えるようになった。

先っぽに花が咲いていた。

散歩にもランニングにも良さそうです。
桜の木が植えてあるので、春など花見にいいのではないか?

私たち歩きカメラの面々は大森までで終了。
そのちょっと手前に歴史で有名な「鈴ヶ森の処刑場」を参拝しました。
江戸時代の刑場で、重罪犯などが磔刑になったり火炙りの刑が、ここで行われた。
磔刑は木の角柱に縛り付けられて、左右から槍で脇腹から肩に抜けるように刺殺されたそうです。
それも槍を刺すのは1回じゃなく、20回も左右から刺すので足元は血だらけで内臓が飛び散っていたそうです。
火炙りの刑は、生きたまま鉄柱に縛り付けられて足元から火を燃やされた。
火炙りの刑では、「八百屋お七」が処刑ののちに文学、文楽、歌舞伎などで取り上げられて庶民の涙を誘った。
火炙りの刑は大きな焚き火じゃなく、小さな消えいるような焚き火で燃やされた。
すると風が吹くと焚き火が消え、また火をつけて罪人は何度も悶絶した。
結局火で死ぬのではなく煙で死ぬことが多かったそうです。
特に、八百屋お七の悲鳴は数キロ四方まで聞こえたといいます。
時に16歳の娘さんの恋心から発した放火とはいえ、、、見せしめの意味があって酷いことでした。
江戸が300年間も続いたのは治安が良かったからでしょう。
次回歩きカメラは西武遊園地の予定です。
代々木健康友の会の「歩きカメラ部」
03−5411−9589
https://blog.goo.ne.jp/yoyogiken