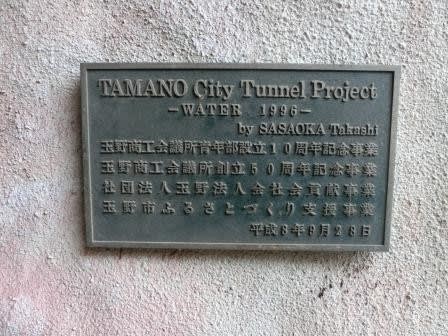玉野市電の走る「玉野」の地名は、玉比咩神社の巨大な「立岩」が、
玉のようであったため「玉石」と名付けられた。
これが由来となったとの説も有るらしい。
嘗て海の入り江に屹立していた御神体は、今では直接触れることが出来、
パワースポットとしても知られている。

相変わらず線路跡は駐車場になっているが、滅多に車の出入りも無く
歩くには安心だ。玉比神咩社前駅から300m程の所に、神社前駅とは同
日開業した「玉小学校前駅」が有った。
小学校は右手に見えるが、駅がどの辺りに有ったのか、周辺が余りにも
変りすぎ今となっては特定出来ないらしい。
距離的にはお堂の辺りかと思うが、それらしき痕跡は何もない。

この先から廃線跡の駐車場は終わり、道幅が少し狭まって歩行者自転
車の専用道路に変る。前方には、中国電力ネットワーク(株)日比変電
所の巨大な送電線の鉄塔が見えてくる。
線路跡の専用道路は、川幅の半分ほどを占め、変電所の塀に沿って少し
左にカーブしながら延びている。

変電所を過ぎると、前方に小さな児童公園が見えてくる。
と言っても特別な遊具が有るわけでも無く、何本かの植木と、金網フェ
ンスに囲まれただけのごく普通のありふれた広場である。
玉小学校前駅からは240mしか離れていない場所で、この辺りが玉野市
電の終点であった。

道路脇に、「すこやかセンター」入口を示す道路標識があり、終着駅
の玉遊園地前駅はこの少し手前辺りに有ったと言う。
駅名はこの北山児童公園の存在に由来しているが、とても駅名になるほ
どの大層な遊園地ではないが、玉野市条例ではこうした公園は「児童遊
園地」と言うのが正式名らしい。(続)