今年の芸術文化振興基金による、文楽の地方公演は、昼の部は「桂川連理柵」(カツラガワレンリノシガラミ)のうち、下巻の六角堂の段、帯屋の段、道行朧の桂川、が上演されました。「曽根崎心中」や「心中天の網島」などと違って、同じ世話物の心中ものでも、あまり鑑賞の機会がないので、夜の部の千本桜にも思いを残しつつ、昼の公演に出かけていきました。
初々しいお半の人形を吉田蓑二郎が、帯屋長右衛門は吉田玉女が遣っていました。今年は浄瑠璃の人間国宝、竹本住大夫さんの姿がないのが寂しい事でした。

アンケートで先年要望を出していた人形の展示が実現し、会場入り口で、若いお二人が夜の部の禿の人形を遣って、東日本の復興への募金をしていました。

桂川連理柵に関して、興味とお時間がおありの方は、このサイトに写真や詳しい解説などがあります。










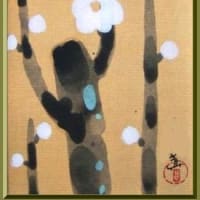
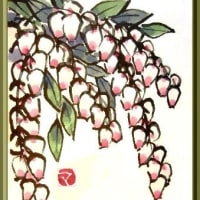
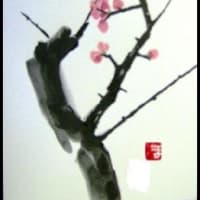
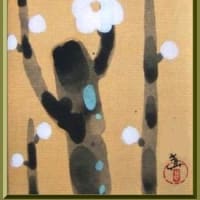






雀さん、美術展で素晴らしいもの沢山触れていらしたのですね!私も、大好きで美術展を追いかけ廻っておりました。ここしばらく大人しくしておりますが、雀さんの記事を拝見して作品を前にするときのときめき、作品に息づく作者の指の戸惑い、決断、視線の熱さに圧倒される感覚を思い出しております。文楽は大阪に住まう私どもには、身近なもので住大夫さんも、よく存じておりますが最近は文楽も危機的な状況…。雀さんのような方のいてくださることは心強いことです。素敵な記事をありがとうございました!
地方では、年1回の巡回公演しか鑑賞の機会がないので、ほぼ毎年出かけるのを楽しみにしています。
住大夫さんも元気になられて、また舞台をつとめられる日が近いことを祈念しています。
鈍感な私はアレルギーとは無縁と思っていましたが、今年は外出が続くと喉がいがらっぽくなります。
迷惑な飛来物です。どうかお大事になさってください。