本日はスペインの作曲家ホアキン・ロドリーゴの「アランフェス協奏曲」と「アンダルシア協奏曲」をご紹介します。どちらもクラシックでは珍しいギターのための協奏曲で、クラシックギタリストにとっては定番となっています。ロドリーゴは他にも「ある貴紳のための幻想曲」と言うギターとオーケストラのための作品を残しており、いかにもギター専門の作曲家のようですが、本人はピアノが専門でギターは弾けなかったそうです。
まず紹介するのは「アランフェス協奏曲」から。この曲の第2楽章は今さら説明の必要もないぐらい有名ですね。マイルス・デイヴィスも「スケッチ・オヴ・スペイン」で取り上げるなどさまざまなジャンルでカバーされています。日本人だと「必殺仕事人」のテーマを思い浮かべますが、あれは一応オリジナル曲とのこと(ほぼパクリですが)。哀愁を帯びた主題が印象的ですが、一方でメロディがややベタすぎる気もします。個人的には第1楽章の方が好きですね。ギターの軽やかな調べと明るく開放的なオーケストラサウンドが心が浮き立つようなメロディを奏でて行きます。
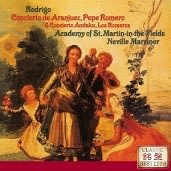
「アンダルシア協奏曲」は「アランフェス協奏曲」の30年ほどに書かれた作品で、作曲年は1967年。完全に現代の作品です。ちなみにロドリーゴは世紀末の1999年まで生きて、村治佳織さんなんかとも面識があったようです。意外と最近の人なんですね。作風的には「アランフェス協奏曲」とほぼ同じ。ソロギターのみの「アランフェス」に対し、4本のギターアンサンブルのために書かれたという違いはあれど、明るい第1楽章、哀愁を帯びた第2楽章、そして再び陽気な第3楽章と構成まで一緒です。とは言え、単なる二番煎じではなく旋律も魅力的です。「アランフェス」に比べるとマイナーですが、一聴の価値のある作品と思います。CDはネヴィル・マリナー指揮アカデミー・オヴ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズのものです。ソリストはスペインが生んだ世界的ギタリスとであるペペ・ロメロ、「アンダルシア」にはその父親のセレドニオ・ロメロと2人の兄弟(セリン&アンヘル)が加わっています。
まず紹介するのは「アランフェス協奏曲」から。この曲の第2楽章は今さら説明の必要もないぐらい有名ですね。マイルス・デイヴィスも「スケッチ・オヴ・スペイン」で取り上げるなどさまざまなジャンルでカバーされています。日本人だと「必殺仕事人」のテーマを思い浮かべますが、あれは一応オリジナル曲とのこと(ほぼパクリですが)。哀愁を帯びた主題が印象的ですが、一方でメロディがややベタすぎる気もします。個人的には第1楽章の方が好きですね。ギターの軽やかな調べと明るく開放的なオーケストラサウンドが心が浮き立つようなメロディを奏でて行きます。
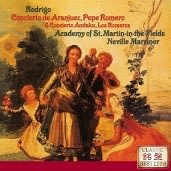
「アンダルシア協奏曲」は「アランフェス協奏曲」の30年ほどに書かれた作品で、作曲年は1967年。完全に現代の作品です。ちなみにロドリーゴは世紀末の1999年まで生きて、村治佳織さんなんかとも面識があったようです。意外と最近の人なんですね。作風的には「アランフェス協奏曲」とほぼ同じ。ソロギターのみの「アランフェス」に対し、4本のギターアンサンブルのために書かれたという違いはあれど、明るい第1楽章、哀愁を帯びた第2楽章、そして再び陽気な第3楽章と構成まで一緒です。とは言え、単なる二番煎じではなく旋律も魅力的です。「アランフェス」に比べるとマイナーですが、一聴の価値のある作品と思います。CDはネヴィル・マリナー指揮アカデミー・オヴ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズのものです。ソリストはスペインが生んだ世界的ギタリスとであるペペ・ロメロ、「アンダルシア」にはその父親のセレドニオ・ロメロと2人の兄弟(セリン&アンヘル)が加わっています。















