本日はニッコロ・パガニーニのヴァイオリン協奏曲をご紹介します。パガニーニは19世紀前半に活躍した作曲家ですが、生前はむしろヴァイオリニストとして一世を風靡する存在でした。その人間離れした超絶的な技巧は悪魔に魂を売り渡して手に入れたと噂され、酒・女・博打に溺れたスキャンダラスな私生活と相まって、まさに「鬼才」と呼ぶにふさわしい人物だったようです。作品についてはほとんどが自分の演奏会用に書かれたヴァイオリンのための曲で、協奏曲も6曲が現存していますがそのうち演奏される機会が多いのは今日取り上げる1番と2番だけです。
パガニーニのヴァイオリン協奏曲の特徴は超絶技巧があちこちに散りばめられていること。時に不協和音とまで言えるほどの高音や気忙しくなるほどの速弾きが多用されます。これもパガニーニが自らのテクニックを誇示するためのものでやや「やり過ぎ」感もなくはないです。ただ、旋律はイタリア人らしくオペラのアリアを思わせるような歌心あふれるもので、特に第1番はロッシーニを思わせる陽気な第1楽章、悲劇的な序奏から静かに燃え上がる第2楽章、超絶技巧満載の第3楽章ロンドとエンターテイメント感あふれる作品に仕上がっています。
第2番は「ラ・カンパネッラ」の愛称がついていますが、これは第3楽章を後にリストがピアノ曲用に編曲し、「ラ・カンパネッラ」の題で一躍有名になったため。今ではパガニーニ原曲よりそちらの方が有名かもしれませんね。聴きどころはもちろん情熱的な第3楽章ですが、オペラ風旋律の第1楽章も捨て難いです。
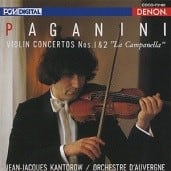
CDですが、パガニーニの第1番に関してはほとんどのヴァイオリニストが録音を残していますが、第2番もセットになっているのは意外と少ないです。そんな中で購入したのはフランスの名ヴァイオリニスト、ジャン=ジャック・カントロフがオーヴェルニュ管弦楽団を弾き振りしたもの。デンオンのクレスト・シリーズで廉価なのが最大の魅力ですが、演奏も一級品でパガニーニ特有の超絶技巧パートも見事に弾きこなしています。
パガニーニのヴァイオリン協奏曲の特徴は超絶技巧があちこちに散りばめられていること。時に不協和音とまで言えるほどの高音や気忙しくなるほどの速弾きが多用されます。これもパガニーニが自らのテクニックを誇示するためのものでやや「やり過ぎ」感もなくはないです。ただ、旋律はイタリア人らしくオペラのアリアを思わせるような歌心あふれるもので、特に第1番はロッシーニを思わせる陽気な第1楽章、悲劇的な序奏から静かに燃え上がる第2楽章、超絶技巧満載の第3楽章ロンドとエンターテイメント感あふれる作品に仕上がっています。
第2番は「ラ・カンパネッラ」の愛称がついていますが、これは第3楽章を後にリストがピアノ曲用に編曲し、「ラ・カンパネッラ」の題で一躍有名になったため。今ではパガニーニ原曲よりそちらの方が有名かもしれませんね。聴きどころはもちろん情熱的な第3楽章ですが、オペラ風旋律の第1楽章も捨て難いです。
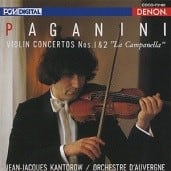
CDですが、パガニーニの第1番に関してはほとんどのヴァイオリニストが録音を残していますが、第2番もセットになっているのは意外と少ないです。そんな中で購入したのはフランスの名ヴァイオリニスト、ジャン=ジャック・カントロフがオーヴェルニュ管弦楽団を弾き振りしたもの。デンオンのクレスト・シリーズで廉価なのが最大の魅力ですが、演奏も一級品でパガニーニ特有の超絶技巧パートも見事に弾きこなしています。














