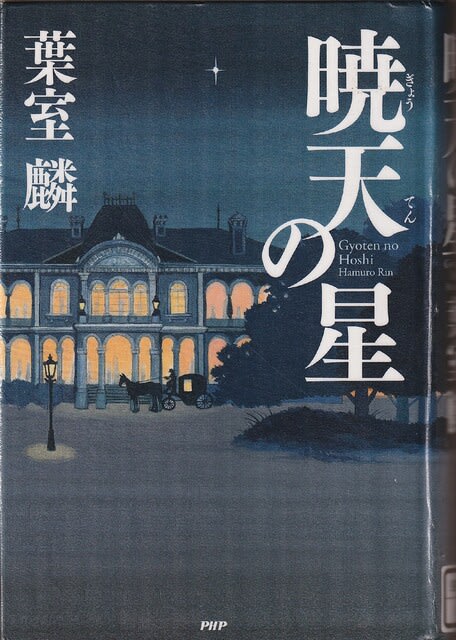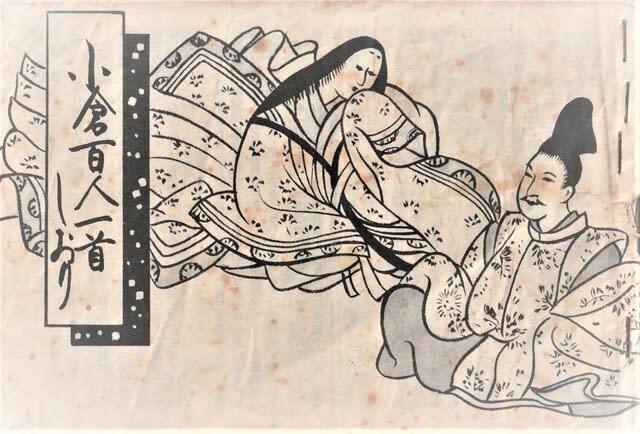今冬最強寒波にみまわれ、ここ数日、全国各地で、降雪、積雪、
特に、青森県等では、記録的積雪による大きな被害が発生、
大雪の暮らしの大変さを知る北陸の山村育ち、心が痛む。
世の中は、今日から3連休、
おとなしく、冬将軍が撤退してくれることを願うばかりだ。
関東南西部山沿いの当地、
今日も「晴」、最低気温=-5℃、最高気温=11℃
朝の内は、この時期相応の厳しい冷え込みで、家籠もりを決め込んでいたが、
しばらく、散歩・ウオーキングを休んでおり(サボっており)
いかん、いかん、
そろそろ再始動?、しなくっちゃ、
午後になり、やおら重い腰を上げ、ちょこっと近くを歩いてきた。
風が弱まったせいで、陽だまり等では、体感的に温かくも有り、
スマホの歩数計で、約5,700歩。




イノシシ出没?の痕跡か?

モズ?・・・かな?



コガモ?















 ⇓
⇓