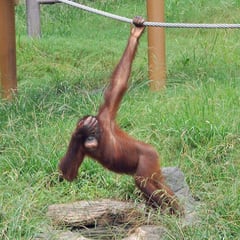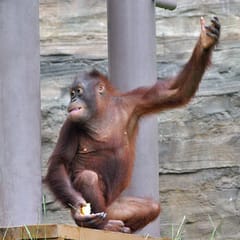9月16日の多摩動物公園から。

奇蹄目サイ科の「インドサイ」。
体長は全長3~4m、肩の高さは1.5~2m、体重1,500~2,000kg。


インドサイは角が1本(アフリカのサイは2本)。ヨロイのような皮膚もインドサイの特徴。
草食で寿命は40年ほど。

角をねらった狩猟で一時は数百頭に激減した。
近年は保護されて若干増えたものの現在約2000頭しか生存していない。

奥のほうにはカモ目カモ科の「インドガン」。
この姿からは想像もつかないけれど「ナショナルジオグラフィック ニュース」によると、わずか8時間でヒマラヤ山脈を一気に飛び越え、世界で最も高く飛ぶ鳥と判明したという。インドから繁殖地のモンゴルへ向かうGPS発信器を取り付けた25羽のインドガンの記録によると、最高高度は6437メートルに達し、渡りの期間はおよそ2カ月、移動距離は最大8000キロに及んだとのこと。
(詳しくは「インドガン」で検索して「ナショナルジオグラフィック ニュース」のページを見て下さい)

奇蹄目サイ科の「インドサイ」。
体長は全長3~4m、肩の高さは1.5~2m、体重1,500~2,000kg。


インドサイは角が1本(アフリカのサイは2本)。ヨロイのような皮膚もインドサイの特徴。
草食で寿命は40年ほど。

角をねらった狩猟で一時は数百頭に激減した。
近年は保護されて若干増えたものの現在約2000頭しか生存していない。

奥のほうにはカモ目カモ科の「インドガン」。
この姿からは想像もつかないけれど「ナショナルジオグラフィック ニュース」によると、わずか8時間でヒマラヤ山脈を一気に飛び越え、世界で最も高く飛ぶ鳥と判明したという。インドから繁殖地のモンゴルへ向かうGPS発信器を取り付けた25羽のインドガンの記録によると、最高高度は6437メートルに達し、渡りの期間はおよそ2カ月、移動距離は最大8000キロに及んだとのこと。
(詳しくは「インドガン」で検索して「ナショナルジオグラフィック ニュース」のページを見て下さい)