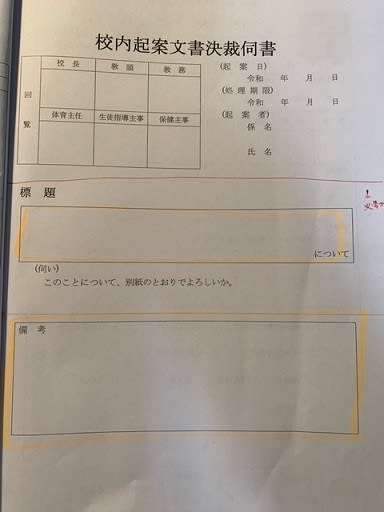(情報機器に詳しい方はスルーして下さい)
アイフォンがおかしい。
通信速度が3Gのままで遅い。
周りの人(同じ通信会社)は、ちゃんと4Gの速さで通信できているのに。
設定を確認してみても原因が分からない。
こういうときに試してみる方法を忘れていた。
再起動である。
携帯電話でもパソコンでも、考えられる手立てをとってみて、うまくいかないときは、試す価値がある。
早速試した。
(アイフォンの場合)
○ サイドの電源ボタンとどちらか片方の音量調節ボタンを同時に長押しし、電源オフスライダが表示されたら離す。
○ スライダをドラッグし、デバイスの電源が切れるまで待つ。
○ 電源を再び入れるために、 サイドにある電源ボタンをリンゴマークが表示されるまで長押しする。
これでうまくいった。
ちゃんと4Gの通信速度になっている。
原因は分からなかったが、問題は解決したので、これでいいのだ。
アイフォンがおかしい。
通信速度が3Gのままで遅い。
周りの人(同じ通信会社)は、ちゃんと4Gの速さで通信できているのに。
設定を確認してみても原因が分からない。
こういうときに試してみる方法を忘れていた。
再起動である。
携帯電話でもパソコンでも、考えられる手立てをとってみて、うまくいかないときは、試す価値がある。
早速試した。
(アイフォンの場合)
○ サイドの電源ボタンとどちらか片方の音量調節ボタンを同時に長押しし、電源オフスライダが表示されたら離す。
○ スライダをドラッグし、デバイスの電源が切れるまで待つ。
○ 電源を再び入れるために、 サイドにある電源ボタンをリンゴマークが表示されるまで長押しする。
これでうまくいった。
ちゃんと4Gの通信速度になっている。
原因は分からなかったが、問題は解決したので、これでいいのだ。