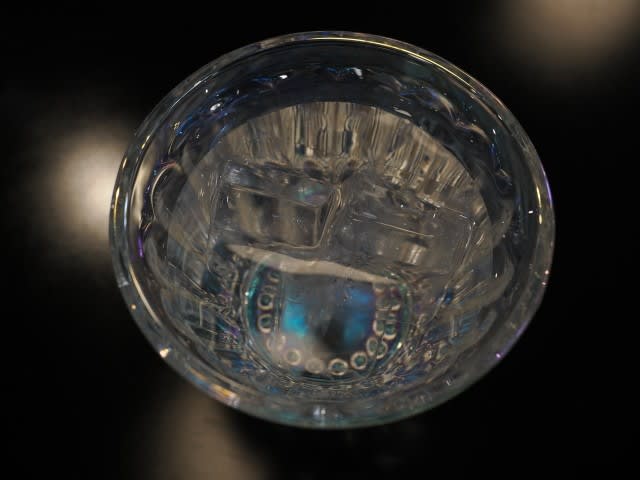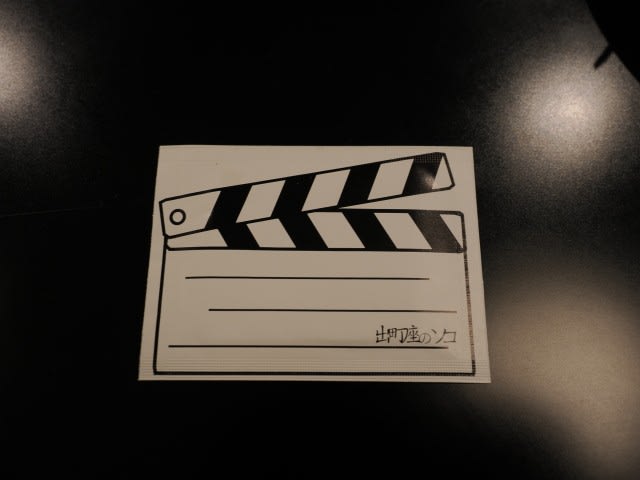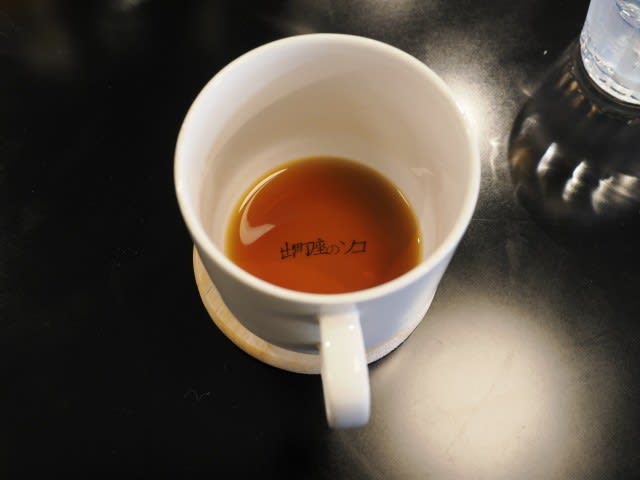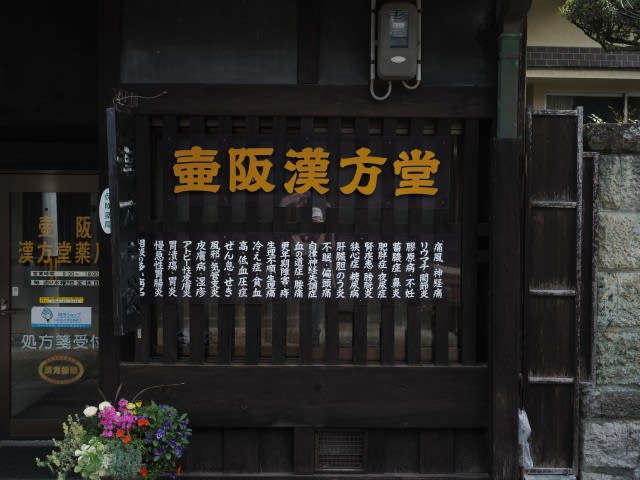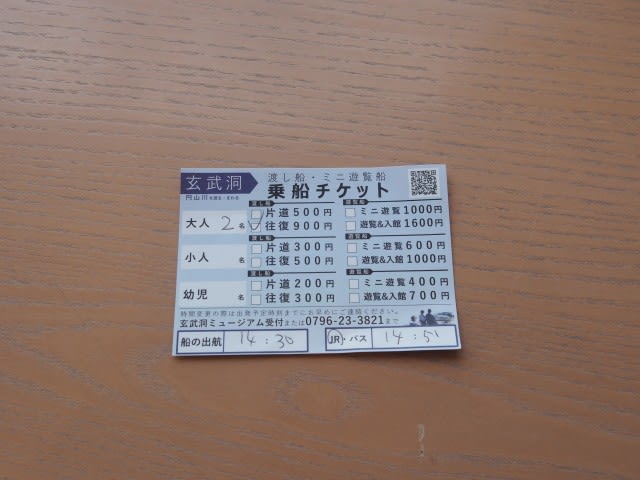京阪電車で出町柳から三条へと下る。
KYOTOGRAPHIE、次の目的地は高瀬川のほとりに建つTIME'Sという建物。
安藤忠雄建築だそう。
ここで、マーティン・パーと吉田多麻希の作品を観る。

マーティン・パーの写真は世界の観光地を訪れる観光客を撮ったもの。
風光明媚な景観を楽しもうと来ているのに、そこには自分以外の観光客が溢れ、景色を観に来てるのだか、観光客を見に来てるのだかよく分からない状態なのを風刺している。
自分もこの内の一人だなあと苦笑い。

吉田多麻希の作品はシャンパーニュ地方の農園に滞在し、大地と生命の循環について考察し写真に落とし込んだもの。
プリントした写真を土に埋め、その後掘り出したものを展示していた。
作品を作成するのにかけた努力、向けた情熱のご褒美として遭遇したシャンパーニュの森からの贈り物(立派な牡鹿)との出会い。
その一瞬もモノにしている。

この二つの展示以外にSIGMAが保有する写真集を一般に開放する部屋が設けられていた。
一部の稀少品には手を触れられないが、ほとんどの写真集は手に取って閲覧可能。
年代順に並べられた国内・海外のたぶんそうそうたる顔ぶれの写真家達なのだろう名前が並ぶ様は壮観だ。
しかし昔からもし見つけたら見てみたいと思っていた写真家の名前が思い出せない。
背表紙の名前を見たら思い出すかもと順に読んでいくが、背表紙を眺めるだけで終わってしまった。