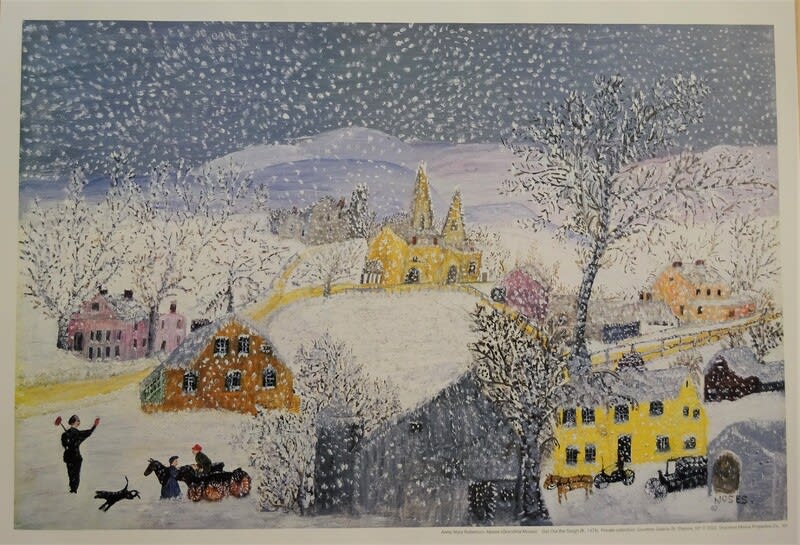時は受験シーズンであり、世に受験関連の話題が溢れている。
先程も、2022.01.17付朝日新聞内に大学受験関連のコラムを見つけた。
「受験する君へ」と題するコラムの、その日の話手は お笑い芸人の 水川かたまり氏だった。
原左都子としてはまったく存じない人物だが、水川氏による「第一志望校 なじめずお笑いへ」とのコラム内容の一部を以下に要約引用しよう。
小学校はスポーツ少年団、中高は部活でサッカーに打ち込んだ。 高校は進学校で、入学して最初のテストでは下から3番目。 それで「勉強、もういいや」と。 成績は低いままだったが、目標は京大文学部だった。(中略)
数学が苦手で、担任から「現実を見ろ」と言われてカチンと来た。
数学が苦手で、私立大に目標を変更。
勉強は意外と苦じゃなく、頭がハイになった。 本番は慶應のほか、早稲田、同志社も受かった。
でも、慶応に入学した後、どうにもキャンパスになじめなかった。 学部の決め方もいい加減だったから、授業にもなじめない。 とどめは6月頃にあったクラス会。 岡山弁が抜けず、内部進学者からいじられて心が折れた。学校へ行かなくなった。
年明けには「芸人になろう」と決め、2011.04に吉本興業の芸人要請所へ入った。 そして21年、キングオブコントで優勝できた。
受験生のみなさんは今,必死だろう。でも大学がすべてではない。 楽しいことはたくさんある。 そう考えれば、プレッシャーも和らぐでしょう。
(以上、朝日新聞記事より一部を引用したもの。)
そうでしたか。
その後、お笑い芸人の水川かたまりさんは独特な世界観のコントが人気で、32歳になられている現在尚、芸人として活躍されているとのことのようですね。
原左都子の私事及び私見に入ろう。
この私も、高校生時代に特段やりたい事も目指したい方向も無かったに等しい人間だ。
とにかく親から「大学は地元の国立!!」と厳しく義務化されてしまい、選択肢がそれしかない状況下におかれてしまった。
そんな中、英数が得意だった事実に助けられて自ら理系志望は早期に決定していた。
ただ実際、家庭の影響等何もない環境下で、自分が将来何をやりたいかなど思い描けるすべもなかった。
そんな私が進学したのは、医学部パラメディカルコースだった。
この選択が大きく功を奏し、私は国家資格取得後上京して専門分野にて就業することが叶った。
高い報酬下で大満足の大都会暮らしを堪能しつつ、私なりに描いていた成功の道程を歩んだものだ。
そんな時に我が脳裏に過ったのは、新たな学問に挑みたい!とチャレンジ精神だった。 医学業務のお蔭で自身の資金力が十分にある私にとって、その夢を叶えるのは簡単なことだった。
そして、私は30歳にして再び大学受験(特別選抜制度を利用した)に挑み“軽々と”合格をゲットした。 (と豪語できるのは、選抜には面接もあったのだが、その時英語担当の面接官より「貴方は英語力に長けているようですが、何か特別な教育を受けてきましたか?」と尋ねられた故だ。
(これは、絶対合格通知が届くぞ!)と確信していたところ案の定それが届けられ、私は30歳にして2度目の大学生生活に入った。
その後、2度目の大学では結果として「経営法学」分野へ進み、大学院修士課程にて「経営法学修士」を取得し現在に至っている。
この「経営法学修士」取得も、既に高齢域に達している我が身を確実に助けてくれている。
この知識を有効利用して、晩婚にての婚姻先の「不動産貸付業」青色申告を毎年担当しているのはこの私だ。
冒頭に掲げたお笑い芸人の水川かたまり氏とは、大いに異質な我が人生だが。
原左都子が水川氏に同意できるのは、私自身にそのような事情があるが故だ。
特に理系進学者の場合は、将来の職種が決定していると言って過言でないであろう。
そんな私ではあったが、自己の意志により人生途中で敢えて自身の進路変更にチャレンジした人間であると言えよう。 (その後も、また医学の道に舞い戻ったりもしつつ、幅のある有意義な人生を送っている原左都子であると、豪語させていただこう。)
とにかく、今現在受験に直面されている受験生の皆さん。
人の人生とは、今後末長く続くものです。
もしも今冬の受験の結果が芳しくなかったとしても。
貴方の未来には、様々な輝ける選択肢が待ち受けていることでしょう!!