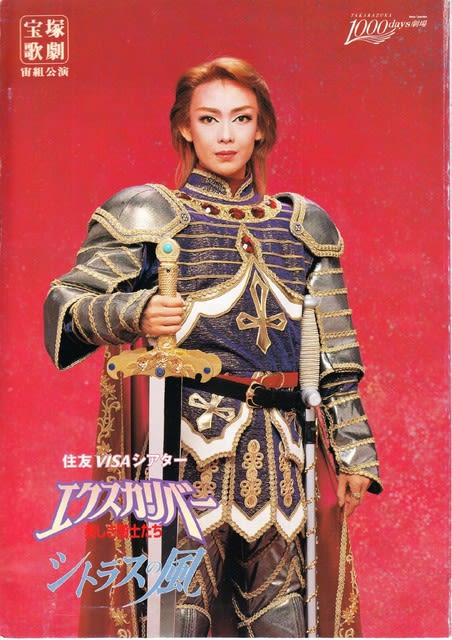=課題=
古代英語文学(Old English Literature)と中世英語文学(Middle English Literature)における特質の相違を明らかにしなさい。ただし、『ベーオウルフ』『カンタベリー物語』『農夫ピアズの夢』『アーサー王の死』は必ず取り上げること。
厨川文夫訳;『ベオウルフ』岩波文庫、昭和16年。「厨川文夫著作集」第1巻、金星堂に収録。または、忍足欽四郎訳『ベーオウルフ』岩波文庫、平成2年。
西脇順三郎訳;『カンタベリ物語』世界文学大系『チョーサー、ラブレー』筑摩書房、昭和36年に収録。(上)(下)ちくま文庫、昭和62年。または繁尾久編訳;『カンタベリ物語選』荒地出版社、昭和60年。
池上忠弘訳;『農夫ピアズの幻想』新泉社、昭和50年。中公文庫、平成5年。
厨川文夫・圭子訳『アーサーの死』世界文学大系、筑摩書房、昭和49年。ちくま文庫、昭和61年。
(これらが入手できない場合は、大学の図書館を利用してください。)
「異教古代ゲルマンの文化とキリスト教ラテン文化とが結びついて、アングロ・サクソンの文化は形成された。OEの詩にもこのことは反映されている。ゲルマン民族の英雄叙事詩『Beowulf』の作者は、異教ゲルマンの口碑に題材を採り、キリスト教時代の王者の道を示し、武士の理想を表わそうとした。第一部・第二部共に各々類似する作品はいくつもあるが、この作品ではそれら異教の伝説材料がキリスト教的に修正されている。妖怪Grendelは単なる怪物巨人ではなく、「造物主がカインの族なる彼に罪を定め給ひしより、幸を失ひし者」であり、地獄を住処とする。Beowufが、Grendel母子を倒したのは、キリスト教の善の代表者が悪魔を倒す、という意味をもつ。罪に汚れた者が神の裁きを受けたのだ。また、龍と戦ったのは、宝を得ることよりも国民を危機から救うのが主な動機である。彼は、人民の幸福のために人民の敵を倒す、しかも自分の生命を犠牲にしてしまう。勇敢であり、恥を知り、義務に忠実である古代ゲルマンの英雄の理想像そのものである。が、作者の視線は、悲しみの時も歓びの時も死の時も、人間の営みは空しく、「全能の君」たる超自然的な運命の神の力の前には、はかなく滅び去ってゆくものだ、という位置にある。優れた王たるBeowulfも老いては「身体より生命を話し分つべき運命の神は甚だ近くに」忍び寄ってきて、「運命はわが血族、血気盛んなる武士らの凡てを宿命の定めし処へ掃き去りしなり。我は彼らの後より行かざるべからず」と言って絶命する。作者にとってこの作品の世界は、一曲の悲劇である。
Englandは、ヨーロッパ各地に侵入し、北フランスにノルマンディ公国を建てたノルマン人に、1066年征服された。両者は当初あまり交わらなかったが、ノルマン人が大陸での領地を失ってからは、急速に融合が進む。その結果、ノルマン人の話すフランス語の明るい、洗練された柔らかい響きとOEの男性的な重々しい口調とが結び合わさって行く。OE詩の主調が沈うつで厭世的であったのに対して、ME詩の主調は明るく楽天的である。自分たちの住む世界を愉しいと見る人が多く出て来た。ノルマン征服後、人々の習慣や考え方が著しく変化したのである。文学においては、騎士道に要約される時代精神と密接な関係をもつロマンスが誕生。宮廷風恋愛がロマンスを艶っぽくはなやかにさせた。さらに、ケルト的神秘の要素が加わったのが『アーサー王の死』である。
この作品の主題は、Arthurの盛衰だが、そこにLancelotとGwineverの愛がもう一つの主題として深くかかわってくる。二人の愛は《神を畏れぬ行為》であり《おごり》だった。キリスト教の名における男性的文化と秩序の確立を示す円卓騎士団の中でも、武勇と高潔の誉れ高く最高の騎士たるLacelot。だが、一方でキリスト教徒として最も罪深い者であることは、聖杯探究の失敗に象徴的に表されている。ケルトの世界では、豊穣・死と再生をもたらす器を意味した聖杯が、Arthurの世界に入るとキリスト教的になる。キリスト教受難の時に流れる血を受けとめた器という形になり、キリスト教的純潔の象徴とされる。純粋無垢性という絶対性に価値基準をおく聖杯探究は、神を畏れぬ者には初めから失敗することが定められていた。聖杯探究の旅から戻ったLancelotは、王妃のもとへ足繁く通うようになり、「せっかく探究の際にたてた誓いや精進を忘れてしまった。王妃Gwineverは、ケルト伝承と異なり、歴史的・人間的王妃として描かれている。何度も嫉妬で怒り狂い、Lancelotを追放しては激しく後悔し、詫びて和解する。感情をそのまま吐露する生身の女の姿である。Lancelotは、いつも王妃の言うがままを受けとめ、「いつも王妃さまを許さないのではいられないのです。そのために私がどれほど悲しみをなめようとかま」わない。
二人の愛は深まって行くかばりのようだ。が、その代償はあまりにも大きかった。円卓騎士団にひびを入れ、王国崩壊の原因となったのである。うねりをあげて迫って来る運命の力を変えることはできない。しかし、キリスト教社会の中で禁欲的に生きる人々の理想を求めながらも、自らの思うところを全うした生身の人間として二人を描いた作者の、二人への眼差しはあたたかいように思う。最後には、二人は共に自らを悔い改め、天に召されていった。作者は記す「王妃はこの世にある限り、まことの恋人であった。だからこそその最期は立派だった」と。神を畏れぬ者となったのである。
中世後期は、教会や聖職者に対する攻撃や諷刺が盛んに行われた時代でもあった。人それぞれがキリスト教社会の中で、さまざまな個の経験を活かし始めた。Chuacerは『カンタベリ物語』の中に、巡礼の旅という形でさまざまな人々を一堂に集結させ、聖俗共にあるがままを描こうとした。がそのためにかえって、皮肉めいた人物描写が生まれた。権威側の期待するあるべき姿と、現実の見聞という経験世界とのずれをみることに、Chuacerの視線はある。「刑事の話」では、gropeという英語の聖俗両用の意味を巧みに利用して、托鉢僧の皮肉めいた恥辱を引き出している。理想の托鉢僧は、良心を審理(grope)し、説教によって人々の魂をキリストに向ける者だ。トマス家を訪れたジョンは、女房を「しっかり両腕に抱えながら、やさしく接吻した。好色的に触れる意のgropeである。そして、理想的な托鉢僧であることを誇示した彼は、トマスの良心を吟味(grope)しようとする。が、懺悔を勧めて牧師にすませたと言われると、本音を出して寄付を求める。結果、「わしの背中から手を入れて、ずっと下のほうをさぐって(gropeして)下さい。お尻の下にかくしておいたものがあるのじゃ」と言われるとおりにすると、屁をお見舞いされた。「天国から人間が追放されたのも、その貪欲のためでした」と言ったばかりの彼が、貪欲のために追放されたのである。
このように、各個人の心の奥に起こる罪への傾斜、各個人の性格が描かれる。この頃、悔悛は個人的な罪とその責任として扱われるようになった。罪は人間にとって共通なものであっても、聴罪者の前で客観化され、分析・詮索されると個人の問題になる。罪が単に偶発的なものでなく、個人の問題として内的外的状況が掘り下げられる。罪の分析を契機として、人は悔い改めへと導かれるのである。個人の責任が意識されるが、それは依然として中性的キリスト教階級構造の社会においてであった。その社会との関係で意識されていた。だから、悔悛も個人の責任においてなされる。「托鉢僧の話」では、職業のもつ権利をふりかざして悪事に濫用できるところが罪の源となる強欲な刑事の性格が描かれている。悪魔が獲物を捕らえる方法を語らせながら、実は今日の獲物は当の刑事であるという皮肉な結末を作者は周到に準備した。罪をどう扱っても最後は「悪魔に捕えられないうちに、自らその罪業を悔い改めるように反省するがよい」へ辿りつく。巡礼者の各々が生き生きと語るそれぞれの話はまさに人生であり、人生という巡礼は悔悛で終わらなければならない。最後に、牧師が「作り話」を捨て「教訓話」ならするということで聴罪手引書の型を借りた悔い改めについての話をする。「贖罪」と「告解」と「痛悔」についての話から始まり、七罪源の話、罪の告解の勧めと祈りで終わる。最後の悔悛の勧めとなるのは償罪行為としての巡礼の本来の姿にたちかえって、カンタベリ巡礼の遊びを完了させようとする姿勢である。およそ巡礼は人の子の故国なる「天のエルサレム」への旅であることを、各々に思い起こさせ、悔悛へと彼らを誘った。
『農夫ピアズの幻想』も、人間の罪への傾斜と悔悛への意識が強く出た作品である。作者は夢の中に、神意に従いながら自然の秩序に基づく世界をつくろうと努力している。キリスト教社会において、神によって配剤された人それぞれの職域を、人それぞれが愛によってその役割を果たすべきだ、という理想が基本にはある。第一の夢で〈聖なる教会〉姫が登場し、〈真理〉が一番すぐれていると説く。第二の夢では、七罪源の擬人化されたのが罪の告解を行う。罪を犯した信徒は心からその罪を悔い、告白によって罪の許しと永遠の罪からの免除を得る。が、こうした告解によっても免ぜられずに残る有限の罰については、その罪の償いを果たす方法として真理探究の巡礼が求められる。ここで突然「聖ペトロにかけて」と農夫Piersが登場し、人々の案内役を買って出る。Piers像は、時と場所に拘束されずに、その属性を次々と変えて行く。
ここでの彼は、肉体労働に励む現実的な農夫であると同時に〈真理〉の所在を知らない群衆の魂の救済をあずかる聖職者としての役目もしている。そのPiersが、次ぎには〈真理〉から送られてきたラテン語の免罪符を怒ってズタズタに引き裂いてしまう。彼は、その内容を否定したのではなく、「これは免償ではない」と中世の神学者がよくやる注釈をした司祭の説明に同意できなかったと考えられる。免罪符は、最後の審判の日における赦しの約束救霊の象徴を意味し、まだ罪ある者でも救われる余地があることを意味していた。それが濫用・悪用されている現実に対する作者の怒りが表われている。Piersの免罪符に示される善行は、神の愛によってのみ実現されるべきものである。キリストに学んで愛の行いをすること、隣人を愛し己が分限の仕事に励むことである。彼は「祈りと贖罪の生活」を送ることを宣言する。胃の腑の為には神は既に我らに十分与えてくださっている。これからは、我が肉への関心よりは魂への関心を優先させようと言うのである。神の国とその正義を求める努力は、たゆまぬ精神生活、日常の営みにおける魂への絶えざる関心によって実る。これが〈真理〉を求むる心であり、善行の生活信条である。」
参考文献
『厨川文夫著作集 第一巻 べーオウルフ』(金星堂)
『カンタベリ物語』西脇順三郎訳(ちくま文庫)
『農夫ピアズの幻想』池上忠引訳(中公文庫)
『アーサー王の死』厨川文夫・圭子訳(ちくま文庫)
『英語のなかの歴史』オウエン・バーフィルド、渡部昇二・土家典生訳(中央高論社)
『ベオウルフ』大場啓蔵訳(篠崎書林)
『アーサー王の死』四宮満著(法政大学出版局)
『英文学を学ぶ人のために』坂本完春編(世界思想社)
『中世のイギリス文学』斎藤勇著(南雲堂)
平成7年に書いたレポート、評価はB、
講師評は「かなりよく分析できています。具体的に引用文もまとめて分かりやすい、よいリポートです。ただそれではOE文学とME文学はどのように相違するのかという講論の結びが書かれていません。たんぽぽさんの筆でまとめるべきでした。惜しいB!!」でした。