私が「エリーゼのために」弾いたところでピアノやめちゃった、という話は何度か書いていますが。
 ←スポンサーのご意向、というのはやっかいなもので
←スポンサーのご意向、というのはやっかいなもので
このとき小学三年生、バイエルとブルグミュラー25番が終わってちょうどこれからツェルニー30番デビューというところ。発表会のときには簡単なソナチネとか弾いてたかな。この進行は、母のピアノ教室的標準進行からいうと、ごく並かやや遅め。
三歳半からピアノを習い、環境的にはずいぶん恵まれているハズでこの進行(^^;;
(母に習っていたわけではない)
…というところは、母が私のピアノを「見切る」(本人がやめたいといっているものを引き留める価値がないと判断する)上でひとつの大きな材料になったものと思われます。
おおよそ、「一本のものさし」というか「ひとつのカリキュラム」に沿ってみんな習うわけで、進行の早い遅いというのは大変比較しやすい世界でありました。それで、母のピアノ教室においては、だいたいのところ、その進行の早さで素質を占う(もちろん早いほうがいいのだ)ということであまり間違いや例外はなかったんですよ。
高校生になってツェルニー50番やバッハ平均律やショパンのエチュードなんか弾いてた子はわりと音大行ったりして、
それより進行遅い子はだいたいその手前でやめちゃうんだけどね。中学生くらいとか。同じ年齢の子より明らかに遅れが大きくなるとやめちゃうことが多かったと思う。
(小学三年生はちと諦め早すぎ)
ところで、昨日リンクを貼った「ピアノ曲の進度と実力は本当に比例する?」でいう「ゆっくり進行」はどのくらいかというと、
ピアノを年少から始めて四年間。まだバイエルが終わりません
というので、確かにまぁ前述の昭和時代某ピアノ教室的基準からいってもかなりゆっくり。
でもこの「Aちゃん」をコンクールに出したら全国大会に進んだ。そして
> このAちゃんよりもっと進度の早い生徒たちもいますが、コンクールを受けさせるところまでは、残念ながらいきません・・・
といっています。
進行ゆっくりの子は「片手の練習を必ずする。同じ曲を長く弾いていますから、内容も深く、また音の質についても細かく指導することができました。」「30分で1曲ですから、ゆっくりとこのような音質とフレーズなどについての勉強ができるわけです。」
一方、進行が早い子は「それに比べ、譜読みの早い子はたくさんの曲を持ってきます。レッスン時間は同じ30分ですから、細かく指導する時間がありません。スラスラ弾ければ終わりという形をとらざるをえないのです。」
この二つのピアノ教室「早いのが良い」「遅いのがかえって良い」の感覚の違いがどこから来るかというと…
私は「時代が違う」と思いました(^^;;
つまりどういうことかというと、母の場合、譜読みが速い子がどんどん先まで勝手に持ってきて、どんどんマルあげなきゃいけないってことがなかったのですね。
あくまで、母から指示された曲を練習してきて、
母のいうとおり片手ずつレッスンしたり、
母がこの曲はOKというところまで弾けたらマルになってたわけです。
単純に言って、ある曲のマルは同じクオリティーまで来たらマルなわけで(実際はそこまで単純でなく、うまい下手はありますが)、いい加減に先に進ませるってのはなかったんです。だから、早く先に行く子は素質がある子だったんです。
昔は先生ってそういうもので、中身があってもなくても偉かったのよ。昭和の時代。
親はピアノのことをよく知らないことが多いし、中身とかはそんなに注文をつけなかった、つけられなかったですから。
ピアノ教室同士の競合も少なく、
ほかの習い事との競合も少ない牧歌的な時代でした。
もちろん、ある曲がいつまでたってもマルにならないと、生徒も先生も嫌になっちゃうので、そういうときは甘くしてマルにするんですが、「一本のカリキュラム」に迂回路を足していました。つまり、バイエルやりながら、メトードローズも使うとか、ツェルニー30番の前に100番も使うとか、要するに先に進まずに曲数を増やすんです。
ピアノの先生がよいと思う指導ペースでなく、子どもや親の要望に従ってどんどん曲(の数も難易度も)が進んでしまい、音の質がよくなく、演奏が雑だとぼやいているようでは、サービスが良すぎるというべきか悪いというべきか。でもこれが「今」の教室が置かれた状況なのでしょう。
「今」の時代に、母の教室があったらたぶんつぶれますよねー
どんどん曲を進ませて、コンクールで賞を取らせる「メソッド」というのは、スポンサーのニーズにお応えするために発達したともいえそうです。
あんまりストイックなのも、あんまりイケイケドンドンで音楽の本質から離れるのも、どっちも好きじゃありません。
折衷案的な、今も楽しく将来も楽しいくらいのミックスメソッドってのは、ありうると思うんですけどね…
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社 ←またろうがイラストを描いた本(^^)
←またろうがイラストを描いた本(^^)

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)
このとき小学三年生、バイエルとブルグミュラー25番が終わってちょうどこれからツェルニー30番デビューというところ。発表会のときには簡単なソナチネとか弾いてたかな。この進行は、母のピアノ教室的標準進行からいうと、ごく並かやや遅め。
三歳半からピアノを習い、環境的にはずいぶん恵まれているハズでこの進行(^^;;
(母に習っていたわけではない)
…というところは、母が私のピアノを「見切る」(本人がやめたいといっているものを引き留める価値がないと判断する)上でひとつの大きな材料になったものと思われます。
おおよそ、「一本のものさし」というか「ひとつのカリキュラム」に沿ってみんな習うわけで、進行の早い遅いというのは大変比較しやすい世界でありました。それで、母のピアノ教室においては、だいたいのところ、その進行の早さで素質を占う(もちろん早いほうがいいのだ)ということであまり間違いや例外はなかったんですよ。
高校生になってツェルニー50番やバッハ平均律やショパンのエチュードなんか弾いてた子はわりと音大行ったりして、
それより進行遅い子はだいたいその手前でやめちゃうんだけどね。中学生くらいとか。同じ年齢の子より明らかに遅れが大きくなるとやめちゃうことが多かったと思う。
(小学三年生はちと諦め早すぎ)
ところで、昨日リンクを貼った「ピアノ曲の進度と実力は本当に比例する?」でいう「ゆっくり進行」はどのくらいかというと、
ピアノを年少から始めて四年間。まだバイエルが終わりません
というので、確かにまぁ前述の昭和時代某ピアノ教室的基準からいってもかなりゆっくり。
でもこの「Aちゃん」をコンクールに出したら全国大会に進んだ。そして
> このAちゃんよりもっと進度の早い生徒たちもいますが、コンクールを受けさせるところまでは、残念ながらいきません・・・
といっています。
進行ゆっくりの子は「片手の練習を必ずする。同じ曲を長く弾いていますから、内容も深く、また音の質についても細かく指導することができました。」「30分で1曲ですから、ゆっくりとこのような音質とフレーズなどについての勉強ができるわけです。」
一方、進行が早い子は「それに比べ、譜読みの早い子はたくさんの曲を持ってきます。レッスン時間は同じ30分ですから、細かく指導する時間がありません。スラスラ弾ければ終わりという形をとらざるをえないのです。」
この二つのピアノ教室「早いのが良い」「遅いのがかえって良い」の感覚の違いがどこから来るかというと…
私は「時代が違う」と思いました(^^;;
つまりどういうことかというと、母の場合、譜読みが速い子がどんどん先まで勝手に持ってきて、どんどんマルあげなきゃいけないってことがなかったのですね。
あくまで、母から指示された曲を練習してきて、
母のいうとおり片手ずつレッスンしたり、
母がこの曲はOKというところまで弾けたらマルになってたわけです。
単純に言って、ある曲のマルは同じクオリティーまで来たらマルなわけで(実際はそこまで単純でなく、うまい下手はありますが)、いい加減に先に進ませるってのはなかったんです。だから、早く先に行く子は素質がある子だったんです。
昔は先生ってそういうもので、中身があってもなくても偉かったのよ。昭和の時代。
親はピアノのことをよく知らないことが多いし、中身とかはそんなに注文をつけなかった、つけられなかったですから。
ピアノ教室同士の競合も少なく、
ほかの習い事との競合も少ない牧歌的な時代でした。
もちろん、ある曲がいつまでたってもマルにならないと、生徒も先生も嫌になっちゃうので、そういうときは甘くしてマルにするんですが、「一本のカリキュラム」に迂回路を足していました。つまり、バイエルやりながら、メトードローズも使うとか、ツェルニー30番の前に100番も使うとか、要するに先に進まずに曲数を増やすんです。
ピアノの先生がよいと思う指導ペースでなく、子どもや親の要望に従ってどんどん曲(の数も難易度も)が進んでしまい、音の質がよくなく、演奏が雑だとぼやいているようでは、サービスが良すぎるというべきか悪いというべきか。でもこれが「今」の教室が置かれた状況なのでしょう。
「今」の時代に、母の教室があったらたぶんつぶれますよねー
どんどん曲を進ませて、コンクールで賞を取らせる「メソッド」というのは、スポンサーのニーズにお応えするために発達したともいえそうです。
あんまりストイックなのも、あんまりイケイケドンドンで音楽の本質から離れるのも、どっちも好きじゃありません。
折衷案的な、今も楽しく将来も楽しいくらいのミックスメソッドってのは、ありうると思うんですけどね…
にほんブログ村 ピアノ ←ぽちっと応援お願いします
にほんブログ村 ヴァイオリン ←こちらでも
にほんブログ村 中高一貫教育

「はじめての中学受験 第一志望合格のためにやってよかった5つのこと~アンダンテのだんだんと中受日記完結編」ダイヤモンド社

「発達障害グレーゾーン まったり息子の成長日記」ダイヤモンド社
(今回もイラストはまたろう)










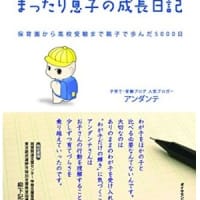












表面的な物が多い中、本質をつかみながらの言葉はやっぱり面白いです。
その代わりと言うか、どの子もどの子も中学生になっても相変わらず通って来てて、何人かは高校生になっても通って来てる。うちのムスメは遂にお休みせずに受験期を乗り切っちゃったし。
正直、小学生の内に1回くらいコンクールに出したかったなぁ。という感情もあるのだが、まぁ、これはこれそれはそれ、という事かしらね・・・。
私も(高校までは片田舎に住んでいましたが)、アンダンテさんのお母様の教室と同じカリキュラムで習っていました(昔は全国どこでも結構一律だったのですね?!)。
で、田舎だけに(?!)、辞めるタイミングがなかなかなく…
結局ツェルニー50番&バッハ平均律にようようたどり着いた直後に
「音大をを目指す予定はなく、大学受験の勉強時間をもっと取りたいので…」となどという理由で辞めました。
弟も同じ先生に習ってましたが、私のやめ方を見て何かを学んだらしく中3ぐらいで「上を目指すのでなく、楽しく弾ける、レベルに合った曲を指導してほしい」と自らお願いして、休み休み高3まで続けていたそうです。
迎えてくれたのは、ふんわりとした雰囲気の先生。
いつもは中高年の女子(笑)の先生だから、いい意味で拍子抜け。
優しい口調で、曲の表情の付け方を丁寧にレッスンしてくださり、娘は感激していました。今までそんな弾き方習ったことがないって。
今、習っている先生は指導のメソッドとしてはきちんと確立されていて、真面目にこなすとそれなりに上達すると思います。ただ、豊かに楽しく演奏する、という点においては大いに問題あり、ですね。音楽性の違いかな?
私もピアノを習ってましたが、いわゆる昭和の指導法で、ぜんぜん上達しなかったし、つまらなかった。楽典も音符の足し算とか引き算とかやらされて、チンプンカンプンでした。途中で挫けました。指導法自体も微妙だったけど、私が成長がゆっくりな子どもだったからかもしれません。なんでピアノが弾けなかったのかなって振り返ると、譜読みができなかったためではないかと…。ヘ音記号が読めませんでした。大人になったら、楽譜が読める!発見でした(笑)
極端な話、昭和の時代では中村紘子のLPだけ聴いたけど、今はyoutubeでプロからアマチュアの演奏が無数、さらにチュートリアルまであります。
うちのピアノの先生は、年齢は高くないのですが二代目ピアニスト兼先生(母上から受け継がれた昭和のやり方)で、ブレハッチくらいの若手よく知らないしドビュッシーとか教えないし。偏っているんです。つまらなくて困るんですよね、昭和のやり方のままって。技術が最優先で。大赤字のパナソニックとか日本の商品もそんな感じ。デザインや使い勝手がいまいち。
むかし、水が飲めないとかうさぎ跳びをやらされましたが、今の子はやりませんよね。練習曲も先生の指示だからやっていますが、本当にいいものなのか。
あと、言いたいのはこうした昭和な先生が、クラシック音楽好きを育てる事を軽視しているんです。
その(テクニック大好き)先生はテクニックにはうるさくなく、楽譜をしっかり見るようにと言っていました。
先生自身は学生時代、暗譜を義務づけられていましたが、大人だと速い曲を弾かないので楽譜を見ながら弾く方が理にかなっています。
あるピアニストは音符を耳で覚えていたので、小学校高学年になるまで楽譜が読めなかったそうです。
音符を耳で覚えると早く弾けるようにはなるかもしれませんが、楽譜が読めないのは不便だろうと思います。
子供さんにはできるだけ美しい音を聞いて欲しいと思います。
美しい音を聞くとピアノから離れられなくなります。
尊敬するかおる先生からお褒めいただきたいへんうれしいです!!
この場合、「尊敬」は文章を書くという観点からです。
だってかおる先生の演奏聞いたことないしレッスンも受けたことないですからね~
でも、ブログからわかる範囲で、ポリシーやコンセプトからすると、素敵なピアノ教室なんだろうなーと想像しながら読んでます。
いつか演奏をお聞きしたいです(^^)
あ、こじろうもやめなかったけどあれは純粋に…ほんとに純粋に、レッスンのとき以外弾かなかったからね。
中学生になっても高校生になってもやめないピアノ教室というのは、ひとつの「現代にマッチした」解だという気がします。コンクールに出なくても、何か別の価値を提供してるんですよね。
> で、田舎だけに(?!)、辞めるタイミングがなかなかなく…
え、田舎とかって関係あるのそれ??
> 「上を目指すのでなく、楽しく弾ける、レベルに合った曲を指導してほしい」と自らお願いして、
おとうとくん賢いわね(^^)
うまくいきそうですね。よかった!!
もちろんピアノのテクニックとして必要なことを習得していくのは大事ですが、先生の演奏というか表現が目指す方向と違うのではこの先、つらすぎますからよいタイミングだったのではないでしょうか。
> 私が成長がゆっくりな子どもだったからかもしれません。
昭和な指導法の特徴は、良くも悪くも「一律」ということで、合わないとほんとやめる以外ないんですよね。
> 大人になったら、楽譜が読める!発見でした(笑)
はは。
大人になったら、そのへんはぐっと楽になるよね~