The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“我関わる、ゆえに我あり”
“Cogito,ergo sum”とはDescartesの有名な言葉“我思う、ゆえに我あり”のラテン語だが、浅学菲才にしてラテン語を知らないので、どれが“我思う”であり、どれが“我あり”なのか分らない。何より、日本語に比べ簡潔な言い回しに奇異な気分を抱く。昔、大学受験に際し、これくらいは覚えておいた方が、英訳・英作や世界史に役立つと言われとにかく頭ごなしに覚えたものだ。したがい、“我関わる、ゆえに我あり”をラテン語で言うとどうなるのかは不明だ。
さて、この“我関わる、ゆえに我あり”とは 誰のセリフか。実は最近出た新書の標題で、副題が“地球システム論と文明”とある。地球物理学者で元東大教授の松井孝典氏が著者である。洒落た標題に衝動買いしてしまった。
但し、この本を読む前に、宇宙論を多少は理解しておく必要があるだろうと 2冊の本を読んだのだが、それが前々回投稿したものだ。お蔭で、この本の前半を読むにあたっては、雑駁でもある程度の素地があったので、結構イメージをつかみ易かったし、逆に宇宙論理解の“おさらい”にもなった。しかし、そういう予備知識が無くても、非常に読み易い良書ではないかと思われる。恐らく“松井教授の東大駒場講義録”を分り易くした本なのだろう。
現代は、人の劣化dumbing-downの時代だと言われている。日本の選良で構成されているはずの政府の政治家や高級官僚の打出す政策やパフォーマンス、一流とされる企業とそこに勤める社員等のパフォーマンス劣化が著しい。何より、原発事故もそうした現象の一つと考えられる。そこには、思考放棄の姿勢が日本社会に普遍化していることがある。世の中の変化が早く、また激しく、それをフォローすることが困難になっている。その中で、あふれる情報を適当につなぎ合わせれば、何とか仕事になっているという安易さがある。しかも、この混沌とした世相に多様な価値観が入り乱れている。そんな状況が背景にあるのだろう。だが、それにもかかわらず、社会には難問が山積している。何を信じて、どういうパラダイムを自分なりに築けば良いのか不明な時代なのだ。
こういう時代には、自分を客観視できる視点を外部に求めるべきであり、“内からの視点では世界は語れない”と著者は主張し、こういう時代閉塞を打ち破った歴史的事例として、明治維新を引き合いに出している。そして、次のように宣言する。“現代という時代において「我々、あるいは人間とは何か」を問うことが、本書の目的”である。そして環境や資源・エネルギー、人口問題等々の“問題は、基本的に全て文明の問題であり、我々がつくりだした問題”であり、“我々(は何なのか)を問わずして、それらの問題の根本的な解決”は無い、と言っている。
そして、話題は自らの地球惑星物理学の研究を通じて得た、世界観の変化の体験に移って行く。その結果、“地球システム論”や“人間圏”という概念を確立して行く過程を述べている。その後、“地球システム論”の解説へと入って行く。
地球システムは、基本的には地圏(地殻、マントル、コア等)、水圏(海)、大気圏より成っていて、そこに生命が誕生し生物圏が生まれた。これが、“生命の惑星”段階の地球システム。そして、その生物圏の中に人類が誕生し、その人類が農耕牧畜を開始し、生物圏とは一線を画した独立した人間圏を形成し、“文明の惑星”段階を迎える。
人間圏を形成できたのは、現人類のホモ・サピエンスだけである。それはホモ・サピエンスだけが脳内に外界を投影した内部モデルを構築し、言語を獲得し、それにより判断や解釈を行い、その結果 共同幻想を描き、共同体を構成し、高度な抽象的思考も共有するようになった。つまり、言語を用いて考えることにより我は存在し、外界の認識を通じて我がつくられる、と言える。そこで、“我関わる、ゆえに我あり”となる。“我なくして、思考あるいは認識することはできないが、その我は外界と関わることでつくられる。関わりによって形づくられるもの、それが我という存在”となると言う。
やがて、その人間圏で、産業革命以降 化石燃料をエネルギー源として“自らの内部に駆動力を持つ”ことになり、自然頼みの文明が爆発的に拡大し、一部を地球システムからはみ出す程までになる。“駆動力に注目すれば、人間圏は地球システムの駆動力をはるかに超える”ようになる。“そのため、人間圏と地球システムの関係は非常に不安定”となるが、“地球システムと調和的な人間圏という意味では、(人間圏は)地球システムを越えて大きくなることができないため、その内部で何らかの強制的な変化を求められる”と指摘している。
そして、さらに続く記述は深刻である。“文明の誕生と発展が、我々の認識の時空を拡大し、宇宙における観測者として、その宇宙が存在することに意味をもたらすことになったことは、実は文明とは何かを問う上で忘れてはならない”。しかし“その存在の一方で、文明の存続に関わる問題を引き起こしているという「文明のパラドックス」に、我々は挑むしかない”のである。
そして、この議論は東日本大震災によって、さらに拍車がかかり、“自然エネルギー”が注目を集めているが、“地球システム論的な観点に立てば、太陽光、風力などをエネルギー化するという考えかたも、地球システムにおける物質・エネルギー循環をダイレクトに人間圏内に駆動力として組み入れるという意味では、原子力や他の化石エネルギーと何ら違いは”ない、と断言している。そして、単なる“右肩上がりの人間圏の「復元」”を目指すのならば、“それは実は、地球が最終的に金星化に向かう”ことを意味する、つまり 高温の大気の金星状態になると言っている。従って、“地球システムと調和した新たな人間圏の「創造」”が必要である、としている。すなわち“駆動力を減らした場合の人間圏の構成要素、構成要素間の関係性について考えることこそ”が重要であると説いている。
しかしこの前半の議論は、私は理解できない。それは、例えばソーラー・エネルギーは、地球に降り注いだものを人間圏に有効に取り込もうとしているため、地球システム内での配分問題であり、それが地球システム全体の高温化(金星化)の原因になるとは思えない。ただ、地球システムへ供給されたエネルギーの内部分配の変化により、それまでの調和が崩れ生物圏をはじめ、他の構成要素に、大きな影響を与えることに懸念するべきではある。すべての“自然エネルギーの有効利用”には、それが大規模化した時の問題点がそこにあると思うべきであるのだが・・・。
この本は、宇宙論や単なる地球学の本ではない。難問山積の現代にあって、どのようにそれに対処して行くべきかを示した哲学的入門書だと言える。
19世紀の終わり、ゴーギャンが絵画を通して投げかけた問い“我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか”に対し、“すべての答えは、「我々はどこに行こうとしているのか」の中にある”と答えるべきだと言っている。著者は“地球システム論と歴史に基づく旧来の知の統合”により、“チキュウ学(「地球」と「知求(新しい認識を求める)」、「知球(体系化された知の全体を図に表したもの)」)”を創造してきたという。そんな“地球を俯瞰する視点”を持って、“人間とは何か”との問いには、“我々が普遍を探る、自らの思索と行動の中にこそある”と、答えるべきだと言って、この本は終わっている。
宇宙が生まれて137億年、地球が生まれて46億年、人類が誕生して700万年。現人類ホモ・サピエンスが出現して20万年。“地球を俯瞰する視点”を持って、CO2地球温暖化論を見た場合、経済活動を見るような短期的視野で気候変化を捉えているように思える。つまり、観測結果によれば温暖期・氷河期が12万年間隔で繰り返されているにもかかわらず、IPCCをはじめとするCO2地球温暖化論者は、数十年から百年単位での見方しかしていない。経済学的には長期視野かも知れぬが、まさしく地球温暖化を金儲けのネタとして捉えているためではないかという気さえしてくる。なぜならば12万年間隔で繰り返されている温暖期・氷河期に合わせて大気中のCO2濃度も増減している事実がある。つまり、人間の活動が、大気中のCO2濃度を変化させると思わせるほど大規模でなかった頃もCO2濃度は大きく増減していた。ならば今のCO2増加も そういう大自然のサイクルの中の一部と考えるのが普通ではないのか。どうして 高々数百年の気候の変化だけをクローズアップし、こじつけてまでして人々の不安を煽る必要があるのだろうか。
“地球を俯瞰する視点”を持てば、放射能への見方も変わってくる。太陽は核融合、地球は内部の核分裂を駆動力にしている。宇宙空間には、宇宙線が満ちている。 “生物がそのような環境下で生まれ、進化してきたことは知っておく”べきだ。従って、生命の生存には、放射能絶対ゼロの世界でなければならない、などとしたり顔で言い募る科学者がいるとすれば、それは科学者としては怪しいと思った方が良いことが分かる。
“地球を俯瞰する視点”を持てば、環境や資源・エネルギーの問題の根源は地球上の人口過剰に帰結することが容易に理解できる。だから、日本を含め先進国の人口減少は好ましい傾向である。だが、人口減少を経済発展の駆動力とすることは、これまでの経済学にはない。この本の著者は“日本という国は、人間圏のサブシステム”なので“21世紀の人間圏システムのモデルとして、新しい文明原理に基づく内部システムを構築することができれば、それはまさに21世紀の人間圏のモデルとなりうる”と鼓舞している。しかし、人口減少の中で、日本が世界の大国の地位を保持しつつそのような成功モデルを構築することは困難を極める道である。これまでに全くない発想による改革が求められる。
だがしかし、この本には確かな科学的知見に基づく、客観的で偏らない知識・情報がある。読み終えて何だかスッキリしたすがすがしさを覚えた。
ところで、私達は これから“具体的に何に、どのように関われば良い”のだろうか。それは、自分自身で考えるべきなのだろう。それでこそ正に、“我思う、ゆえに我あり”となれるからだろう。
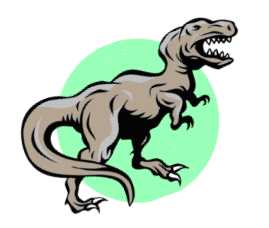
さて、この“我関わる、ゆえに我あり”とは 誰のセリフか。実は最近出た新書の標題で、副題が“地球システム論と文明”とある。地球物理学者で元東大教授の松井孝典氏が著者である。洒落た標題に衝動買いしてしまった。
但し、この本を読む前に、宇宙論を多少は理解しておく必要があるだろうと 2冊の本を読んだのだが、それが前々回投稿したものだ。お蔭で、この本の前半を読むにあたっては、雑駁でもある程度の素地があったので、結構イメージをつかみ易かったし、逆に宇宙論理解の“おさらい”にもなった。しかし、そういう予備知識が無くても、非常に読み易い良書ではないかと思われる。恐らく“松井教授の東大駒場講義録”を分り易くした本なのだろう。
現代は、人の劣化dumbing-downの時代だと言われている。日本の選良で構成されているはずの政府の政治家や高級官僚の打出す政策やパフォーマンス、一流とされる企業とそこに勤める社員等のパフォーマンス劣化が著しい。何より、原発事故もそうした現象の一つと考えられる。そこには、思考放棄の姿勢が日本社会に普遍化していることがある。世の中の変化が早く、また激しく、それをフォローすることが困難になっている。その中で、あふれる情報を適当につなぎ合わせれば、何とか仕事になっているという安易さがある。しかも、この混沌とした世相に多様な価値観が入り乱れている。そんな状況が背景にあるのだろう。だが、それにもかかわらず、社会には難問が山積している。何を信じて、どういうパラダイムを自分なりに築けば良いのか不明な時代なのだ。
こういう時代には、自分を客観視できる視点を外部に求めるべきであり、“内からの視点では世界は語れない”と著者は主張し、こういう時代閉塞を打ち破った歴史的事例として、明治維新を引き合いに出している。そして、次のように宣言する。“現代という時代において「我々、あるいは人間とは何か」を問うことが、本書の目的”である。そして環境や資源・エネルギー、人口問題等々の“問題は、基本的に全て文明の問題であり、我々がつくりだした問題”であり、“我々(は何なのか)を問わずして、それらの問題の根本的な解決”は無い、と言っている。
そして、話題は自らの地球惑星物理学の研究を通じて得た、世界観の変化の体験に移って行く。その結果、“地球システム論”や“人間圏”という概念を確立して行く過程を述べている。その後、“地球システム論”の解説へと入って行く。
地球システムは、基本的には地圏(地殻、マントル、コア等)、水圏(海)、大気圏より成っていて、そこに生命が誕生し生物圏が生まれた。これが、“生命の惑星”段階の地球システム。そして、その生物圏の中に人類が誕生し、その人類が農耕牧畜を開始し、生物圏とは一線を画した独立した人間圏を形成し、“文明の惑星”段階を迎える。
人間圏を形成できたのは、現人類のホモ・サピエンスだけである。それはホモ・サピエンスだけが脳内に外界を投影した内部モデルを構築し、言語を獲得し、それにより判断や解釈を行い、その結果 共同幻想を描き、共同体を構成し、高度な抽象的思考も共有するようになった。つまり、言語を用いて考えることにより我は存在し、外界の認識を通じて我がつくられる、と言える。そこで、“我関わる、ゆえに我あり”となる。“我なくして、思考あるいは認識することはできないが、その我は外界と関わることでつくられる。関わりによって形づくられるもの、それが我という存在”となると言う。
やがて、その人間圏で、産業革命以降 化石燃料をエネルギー源として“自らの内部に駆動力を持つ”ことになり、自然頼みの文明が爆発的に拡大し、一部を地球システムからはみ出す程までになる。“駆動力に注目すれば、人間圏は地球システムの駆動力をはるかに超える”ようになる。“そのため、人間圏と地球システムの関係は非常に不安定”となるが、“地球システムと調和的な人間圏という意味では、(人間圏は)地球システムを越えて大きくなることができないため、その内部で何らかの強制的な変化を求められる”と指摘している。
そして、さらに続く記述は深刻である。“文明の誕生と発展が、我々の認識の時空を拡大し、宇宙における観測者として、その宇宙が存在することに意味をもたらすことになったことは、実は文明とは何かを問う上で忘れてはならない”。しかし“その存在の一方で、文明の存続に関わる問題を引き起こしているという「文明のパラドックス」に、我々は挑むしかない”のである。
そして、この議論は東日本大震災によって、さらに拍車がかかり、“自然エネルギー”が注目を集めているが、“地球システム論的な観点に立てば、太陽光、風力などをエネルギー化するという考えかたも、地球システムにおける物質・エネルギー循環をダイレクトに人間圏内に駆動力として組み入れるという意味では、原子力や他の化石エネルギーと何ら違いは”ない、と断言している。そして、単なる“右肩上がりの人間圏の「復元」”を目指すのならば、“それは実は、地球が最終的に金星化に向かう”ことを意味する、つまり 高温の大気の金星状態になると言っている。従って、“地球システムと調和した新たな人間圏の「創造」”が必要である、としている。すなわち“駆動力を減らした場合の人間圏の構成要素、構成要素間の関係性について考えることこそ”が重要であると説いている。
しかしこの前半の議論は、私は理解できない。それは、例えばソーラー・エネルギーは、地球に降り注いだものを人間圏に有効に取り込もうとしているため、地球システム内での配分問題であり、それが地球システム全体の高温化(金星化)の原因になるとは思えない。ただ、地球システムへ供給されたエネルギーの内部分配の変化により、それまでの調和が崩れ生物圏をはじめ、他の構成要素に、大きな影響を与えることに懸念するべきではある。すべての“自然エネルギーの有効利用”には、それが大規模化した時の問題点がそこにあると思うべきであるのだが・・・。
この本は、宇宙論や単なる地球学の本ではない。難問山積の現代にあって、どのようにそれに対処して行くべきかを示した哲学的入門書だと言える。
19世紀の終わり、ゴーギャンが絵画を通して投げかけた問い“我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか”に対し、“すべての答えは、「我々はどこに行こうとしているのか」の中にある”と答えるべきだと言っている。著者は“地球システム論と歴史に基づく旧来の知の統合”により、“チキュウ学(「地球」と「知求(新しい認識を求める)」、「知球(体系化された知の全体を図に表したもの)」)”を創造してきたという。そんな“地球を俯瞰する視点”を持って、“人間とは何か”との問いには、“我々が普遍を探る、自らの思索と行動の中にこそある”と、答えるべきだと言って、この本は終わっている。
宇宙が生まれて137億年、地球が生まれて46億年、人類が誕生して700万年。現人類ホモ・サピエンスが出現して20万年。“地球を俯瞰する視点”を持って、CO2地球温暖化論を見た場合、経済活動を見るような短期的視野で気候変化を捉えているように思える。つまり、観測結果によれば温暖期・氷河期が12万年間隔で繰り返されているにもかかわらず、IPCCをはじめとするCO2地球温暖化論者は、数十年から百年単位での見方しかしていない。経済学的には長期視野かも知れぬが、まさしく地球温暖化を金儲けのネタとして捉えているためではないかという気さえしてくる。なぜならば12万年間隔で繰り返されている温暖期・氷河期に合わせて大気中のCO2濃度も増減している事実がある。つまり、人間の活動が、大気中のCO2濃度を変化させると思わせるほど大規模でなかった頃もCO2濃度は大きく増減していた。ならば今のCO2増加も そういう大自然のサイクルの中の一部と考えるのが普通ではないのか。どうして 高々数百年の気候の変化だけをクローズアップし、こじつけてまでして人々の不安を煽る必要があるのだろうか。
“地球を俯瞰する視点”を持てば、放射能への見方も変わってくる。太陽は核融合、地球は内部の核分裂を駆動力にしている。宇宙空間には、宇宙線が満ちている。 “生物がそのような環境下で生まれ、進化してきたことは知っておく”べきだ。従って、生命の生存には、放射能絶対ゼロの世界でなければならない、などとしたり顔で言い募る科学者がいるとすれば、それは科学者としては怪しいと思った方が良いことが分かる。
“地球を俯瞰する視点”を持てば、環境や資源・エネルギーの問題の根源は地球上の人口過剰に帰結することが容易に理解できる。だから、日本を含め先進国の人口減少は好ましい傾向である。だが、人口減少を経済発展の駆動力とすることは、これまでの経済学にはない。この本の著者は“日本という国は、人間圏のサブシステム”なので“21世紀の人間圏システムのモデルとして、新しい文明原理に基づく内部システムを構築することができれば、それはまさに21世紀の人間圏のモデルとなりうる”と鼓舞している。しかし、人口減少の中で、日本が世界の大国の地位を保持しつつそのような成功モデルを構築することは困難を極める道である。これまでに全くない発想による改革が求められる。
だがしかし、この本には確かな科学的知見に基づく、客観的で偏らない知識・情報がある。読み終えて何だかスッキリしたすがすがしさを覚えた。
ところで、私達は これから“具体的に何に、どのように関われば良い”のだろうか。それは、自分自身で考えるべきなのだろう。それでこそ正に、“我思う、ゆえに我あり”となれるからだろう。
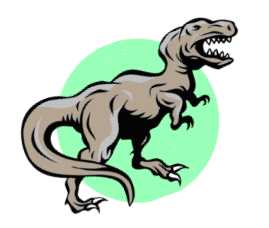
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 大阪府立大学“... | ゴールデン・... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |





