The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“ISOを活かす―69. 資格認定は、高度な技能や技術に対して行なうことよって役に立つ?”
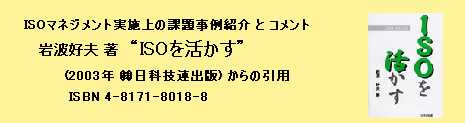
今回は、工程作業内容の軽重に応じた資格認定のあり方についての論議です。
【組織の問題点】
自動車部品の加工・組立を行なっているA社では、品質にもっとも影響を与える工程は、旋盤を使った精密部品を加工する工程です。この工程はベテラン作業者が担当していますが、特に資格認定をしているわけではありません。
一方、加工後の寸法・外観の検査には それほど高度な技能は必要ありませんが、検査員としての資格認定された人が従事することになっています。
このやり方はISO9001マネジメントにふさわしいやり方でしょうか、という課題です。
【磯野及泉のコメント】
著者・岩波氏が この本で指摘しているように、資格認定が必要であると考えるのは、一般的には まず“検査員”、“特殊工程従事者”、“設計・開発従事者”でしょう。
そこで、このA社でも こうした固定観念に従い、検査者を資格認定したものと思われます。恐らく、その背景には、ISO審査員やコンサルタントが、この固定観念に従い、検査者を資格認定するように勧めたことがあり、その言葉に従って A社のISO担当者は ある意味安心して、そうしたものと思われます。
しかし、この結果は ISO審査員やコンサルタントの指導の拙劣さにもよりますが、むしろA社の側の 主体性の問題とも言えます。
これまでのように繰り返しますが、A社のどの工程が品質上重要なのかを まず考えるべきです。この場合、それは“旋盤を使った精密部品を加工する工程”であると明確になっています。であれば、A社ではその作業者を 従来から十分に教育する必要を感じており、そのように行って来たものと思われます。また、その作業者を 訓練水準に応じて資格認定していたものと思われます。この資格認定のためには どのような能力が必要か、従来 どんな関門を設定していたかを、よく整理するべきです。
検査者については、著者・岩波氏は次のように指摘しています。“ISO9001では「製品のリリース(次工程への引渡し、出荷)を許可した人を、記録に明記すること」(8.2.4項)と述べていますが、検査員の資格認定のことは述べていません。簡単な検査であれば、資格認定する必要はありません。”
基本的に、取分け製造業においては 製品の出荷検査はきわめて重要です。なので、一般的には 検査員を資格認定することになるのですが、作り込みが発展し、それが高度に進化した組織においては 検査が不要になるような場合もあります。品質工学でいうロバストな製品を生むプロセスであれば 検査は不要と言われています。そのような 製品の検査においても従来通り、資格認定が必要と考えるのは 意味がないでしょう。
ここでも ことの軽重を主体的に考慮することが 求められるのです。主体的な検討が無い場合、無意味なことをしているという“ISOの弊害”を生むのです。
この“ISOの弊害”は 実は 組織自身の“主体性の欠如”によるところが大きいのです。自己の問題を 他者のせいにするのも“主体性の欠如”が原因なのでしょうが・・・・。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 神は細部に宿... | サミットと原... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |





