The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
佐藤智恵・著“ハーバード日本史教室”を読んで
隣国半島の両政権首脳の会談が板門店で行われるとの発表に引き続き、その後に米朝首脳会談も5月までに開かれる見通しへと驚きの急展開となった。今までのチキン・レースは一体何だったのかと、思わざるを得ない。だが、御蔭で今低迷する日本の株式市場も4月から反転するのではないかとの見通しに、期待が持てることになった。何故ならば、米軍の北攻撃があれば、日本に北による反撃被害が出るのが予測され、それは市場の暴落を想起させるたからだ。その戦端が開かれる前に手持ちを相当数売却しておく必要があったのだ。
それにしても北の駆け引きは見事と言う外はない。板門店での首脳会談は韓国側の施設で行われるという。ヒョッとして、そこで北首脳の“亡命”もあり得るかもしれない。何でもアリを想定しておいた方が良いのではないか。そうなれば北の国家としての崩壊と、巨大な混乱となるだろう。何よりも、既にあるという核爆弾を確実に米側の管理下になるようにしなければ、日本をはじめ周辺国の大きな脅威になるだろう。
森友学園問題に絡んで財務省の記録改竄は、近畿財務局の担当者の自殺、当時の上司の国税庁長官の辞任、退職へと繋がってしまった。特に人命が失われたことは大きい。これは最高権力者御夫婦のなせる究極の結果であるにも関わらず、御当人たちには一向に響いていないように見受ける。この国の現実は忖度しても丸損。だが、これで一件落着とはいかないのではないか。どこまで進展するのか、当事者たちにも見えない、という。兎に角、この国は気真面目な人間ほど生き難い。それで良い国と言えるのか。
女子レスリングのパワー・ハラスメント問題は、騒ぎの素となった小ボスは“体調不良”だという。レスリングの指導者がこの程度のことで“体調不良”だとは、何だか軟弱な印象。ここへ来て“弱さ”を装って幕引きを期待しているのか。どことなく情けなさが漂う。
この国のボスどもの人としての小ささに、情けなさばかりが目立つ。どうして小粒の人間ばかりを指導者としてあがめ、その小粒の人間に汲々として忖度し、結果、犠牲となる、その連鎖は果たして正しいのか。
さて、こうしたこの国の情けない実態を世界はどう見ているのか気になるところだが、ブログ投稿ネタに困っていた時、書店書棚で、偶然にもこの本が目に入った。帯に“なぜ世界最高の知性は日本史から学ぶのか”とあった。表題は“ハーバード日本史教室”とある。単に、こういう類の表題の本を見ると日本の実態を正確に把握した上でのことだろうか、何か誤解があるのではないかと、読んでもその時間が無駄!と思ってしまい手にすることもはばかっていた。しかし、今回は目次を見て、結構 魅力的な印象を持ってしまった。そのまま書店の棚に一旦戻し、店内他所を暫くウロウロして、この本以上に読みたくなる本は見当たらず、やっぱり戻って購入することにした。
この本は、日本研究者である現役のハーバード大学教授に、日本の現状の問題点を中心にインタビューした記録である。著者は1970年兵庫県生まれ、92年東京大学教養学部(国際関係論)卒業。作家、コンサルタント、とある。兵庫県ということから高校はどこだろうか、少々気になるがネットでは分からなかった。
その著書の表題には“MBA”や“ハーバード”や“スタンフォード”の文言が目立つ。特に最近は“ハーバード”が目立つようで、一時流行った“白熱教室”の波に乗ろうとしたのだろうか。
とは言うものの、やはりこの本の構成は微妙に上手くできているように感じる。つまり、実際のインタビューの順序は分からないが、食いつきの良いテーマの研究者から始まり、著者の目玉とする研究者を最終のトリに配したのではなかろうか。中には聞いたことのある名の研究者も居るが、浅学にしてほとんどは私は知らない。そのトリのアマルティア・セン氏も私は知らなかったが、調べてみると日本語による著書・講演集も結構あるようなので、今後読んでみたいと思っている。
目次は次の通りだ。
第1講義 教養としての『源氏物語』と城山三郎―日本通史 アンドルー・ゴードン
第2講義 『忠臣蔵』に共感する学生たち―江戸時代 デビッド・ハウエル
第3講義 龍馬、西郷は「脇役」、木戸、大久保こそ「主役」―明治維新 アルバート・クレイグ
第4講義 ハーバードの教授が涙する被災地の物語―環境史 イアン・ジャレッド・ミラー
第5講義 格差を広げないサムライ資本主義―アジア研究 エズラ・ヴォーゲル
第6講義 渋沢栄一ならトランプにこう忠告する―経営史 ジェフリー・ジョーンズ
第7講義 昭和天皇のモラルリーダーシップ―リーダー論 サンドラ・サッチャー
第8講義 築地市場から見えてくる日本の強みと弱み―和食の歴史 テオドル・ベスター
第9講義 日本は核武装すべきか―日米関係史 ジョセフ・ナイ
第10講義 世界に日本という国があってよかった―経済学 アマルティア・セン
“日本人がはじめてハーバードに留学したのは1872年。”金子堅太郎だという。この金子はその後ハーバード同窓のセオドア・ルーズベルトと意気投合し、日露戦争終結の仲介を当時の米大統領だったルーズベルトに依頼し、ポーツマス条約を日本に有利に締結することを可能にしたという。ポーツマス条約の日本全権大使の小村寿太郎もまた官費によるハーバード留学生だったという。その後は、松下乙彦や山本五十六が、ハーバード卒で個人的にも日米親善に努めたようだが結果として、上手く行かなかった。
2017年現在約100人の日本人学生がいるが、中国からは約900人、韓国からは約300人だという。この日本人の数では、講義で日本の立場を代弁する学生がいないので、多くの教授が残念がっているという。
ハーバードでは1973年にエドウィン・O・ライシャワーの尽力で日本研究所が設立されたという。このライシャワーは日本で生まれ育ち、第2次世界大戦では米政府で対日情報戦に従事後、ハーバード大学教員となり日本研究者として要職を歴任、1961年から年間は駐日大使も務めた。1964年に当時19歳の統合失調症患者にナイフで大腿を刺され重傷を負い、この時の輸血で肝炎に罹患、その後持病となった肝炎が1990年に悪化し、自ら延命治療を拒否し79歳で死亡。遺灰は、「日本とアメリカの架け橋になりたい」との遺言により太平洋に撒かれた。
ライシャワーにより、日本研究所設立の“追い風となったのは当時の田中角栄政権がアメリカにおける日本研究を支援する方針”だったことによるという。国際交流基金を通じて、ハーバード等日本研究プログラムを持つ10の大学に総額1000万ドル(当時のレートで約30億円)という通称“タナカ・テン”を提供したのが契機だったという。
この本で示されたのは、このように長年培われた研究の成果だといってよいのだろう。国際的な知の巨人達の日本観は一体どうなのだろうか、これに興味が持てないとは、余程日本という国に関心のない人物ではないだろうか。だからこの本が気になったのだ。しかも今のこの瞬間だけの日本ではなく、全般に歴史的に見て日本を評価するという研究姿勢で“日本史教室”となったのだろう。
アンドルー・ゴードン教授とデビッド・ハウエル教授は“アジアの中の日本、世界の中の日本”という授業を持ち、約3カ月で日本の通史、つまり6週間で縄文から江戸時代まで、7週間で明治からの近現代史をするという。特にゴードン教授は“(日本と)世界との関連性を含めて捉え、日本史を「支配者の政治史」だけでなく、社会史、経済史、文化史を含めた重層的に語る”ことを心掛けているという。そんな本があれば読んでみたい気がする。どうやら“日本の200年― 徳川時代から現代まで(上・下)”という著書があるようだ。
ゴードン教授は教材に“源氏物語”、“今昔物語集”、“方丈記”、“放屁論(平賀源内)”、“北越雪譜(鈴木牧之)”、大塩平八郎の檄文を使うという。ちなみに、“源氏物語”は女子学生の共感を得てはいないが、エリート層には良く知られているので、“日本人の教養”として必読ではないかと著者は警告する。
また、“チョコレートと兵隊”(1938年・佐藤武監督)の邦画も教材にし、多くの学生が感動するという。当時の国策映画で巧妙なプロパガンダで、そのメッセージは“どんな困難なことがあっても、一致団結して耐え抜こう”という“国民の団結を静かに訴えている”ということに感動するというのだ。そういえば前にこのブログで紹介した“陸軍”(1944年・木下惠介監督)という戦前の映画も何か内に秘めた感動的なラスト・シーンがあった。
またゴードン教授は、岡倉天心の次のようなエピソードを授業で紹介しているという。天心はアメリカに居る時は日本の着物を着て、日本では洋服を着ていたそうで、アメリカで闊歩していると、地元のアメリカ人から“お前たちは何ニーズ?チャイニーズ?ジャパニーズ?ジャワニーズ?”と聞かれて、天心は“私たちは日本の紳士。あなたこそ何キー?ヤンキー?ドンキー?モンキー?”(ドンキーはノロマ・バカの意がある)と流暢な英語でやり返した。ここから、当時のアメリカ人の人種差別意識と、それに対照的な天心の日本人としての誇りを失わなかったこと、そして冷やかしを英語のジョークで即座に返した機転に感心する、という。
デビッド・ハウエル教授は、通史で縄文から江戸時代までを担当。日本の武士で幕末の大名・須坂藩(1万石)の堀直虎に興味があるという。幕府からは外様にもかかわらず、譜代と同様の扱いをうけた、国際派の大名だったという。自らを“ストレート・タイガー(直虎)”と呼び、大名になると藩政改革を断行し反対派を大量粛清し借金を返済、洋式軍制を導入したという。鳥羽伏見の戦いで幕軍が敗走後、江戸に逃げ帰った慶喜に若年寄りの直虎は何かを進言し、直後に切腹してしまう。33歳だったという。“(国際派でありながら武士としての責務を全うしたという、)新しさと伝統が共存しているところに魅かれる”という。学生には直虎の写真を見せて教えるという。
ハウエル教授は“忠臣蔵(赤穂事件)”も教えているが、“大義のためにすべてを犠牲にする”という姿は、日本人だけの考え方ではなく普遍的で、多くの学生が共感するという。
室町時代に津軽半島にある十三湖のほとりに広がっていた港湾都市・十三湊も授業で紹介するという。14世紀から15世紀にかけて東日本の巨大な国際貿易センターだったという。そこを統治していた安東氏が南部氏との戦いに敗れて後、十三湊も急速に衰退し壊滅したという。
普通の日本人が知らないエピソード満載だ。一般に教えられている通史すら、偏っているのかも知れない、と思わざるをえない。自らの歴史すら十分に知ったつもりになっていて、実は良く知ってはいないのではないか。外国人がどうしてこのように埋もれた歴史を発掘できるのだろうか。又ここまで来るだけで既に目一杯になってしまう気にさせられた。
そして、“日本人は明治のリーダーのように、もっとコスモポリタンになってほしい。”と忠告する。要は、客観的に自分を見つめ、異なる考えも乗り越えてお互いを利する関係をもつことで学び合えるからだという。
“ジャパン・アズ・ナンバー・ワン”のエズラ・ヴォーゲル教授の名前は日本人には良く知られている。しかし、私はその本を読んではいない。この本、アメリカの一般人にはあまり読まれなかったらしい。だがエリート層には知られていて、日本の産業研究の端緒になったようだ。日本以外では東南アジアで読まれたそうだ。マレーシアの当時のマハティール首相にも大きく影響したようだ。中国では後に首相になる朱鎔基も読んでいたらしい。
同氏も格差拡大を懸念している。トランプ大統領は長続きしないとも言明。この本に登場する教授たちはほぼ同じ立場の様だ。経営史のジェフリー・ジョーンズ教授も渋沢栄一に仮託して、トランプに“世界からリベラル資本主義が失われている”と忠告するするだろうと指摘している。
日本には米国や中国と違い“フェア・シェア”という基本原理が江戸時代から醸成されてきたというのが、ヴォーゲル教授の結論のようだ。つまり日本では権力者が利益を独占しないという原理だが、最近の日本の指導者のメンタルは残念ながら序文で述べたように大きく変化しているのが現実ではないだろうか。どうして、そうなったのだろうか。
サンドラ・サッチャー教授は、モラルリーダーシップ論を教える。これは、1980年代から教えられている選択科目だが、これほど長続きしている科目は珍しいという。目的は人道主義的な立場から戦争を考えること。そのために開戦の決断には“道徳的に十分な根拠があること”、二つ目に自らの決断の正当性を検討・評価する正しいプロセスを持っていること、だという。
現在、米軍では“トップは他の隊員からの意見を聞くことなく、最終決断を下してはならない”という。意見を聞いた上で“隊長は少なくとも三つの代替案を検討した上で最終決断を下す”という。さらにその最終決断では“軍事専門弁護士が戦時法規の観点から深く関わっていること”になっている。同じ文化の中の部下の意見を聞くよりも、戦時法規が歯止めになっているというのは重要で、これは良いことかもしれない。
こうした観点からトルーマンの原爆投下の決断は正しかったのかの議論が授業でなされるのだという。そこからトルーマンの決断の甘さが見えて来ているということだ。
昭和天皇の“終戦の詔勅”をその授業で必ず取り上げるという。学生は昭和天皇の決断に共感をもつという。“負けた側のリーダーの行為の背景には、どんな目的があり、意味があり、動機があったのか。そこからモラルリーダーシップを学べることは多々ある。・・・昭和天皇の行動はまさにモラルリーダーシップを実践している”とサッチャー教授は評価している。
しかし、授業では昭和天皇の開戦の決意についての議論はないようだ。日本史ではそれを間違えなかったことの方が重要なのだが・・・実際は天皇は部下の将軍たちに意見を求めたという。さて果たしてその時、戦時法規に対してどうだったのか、興味あるところだ。その結果としての天皇の戦争責任が語られるべきなのかも知れない。
ジョセフ・ナイ教授は国際安全保障の専門家と思っていたが、ここではその議論は少ない。この本でナイ教授に割かれた分量も少ない。やっぱりナイ教授は日本の核武装には否定的である。やっても安全保障としては効果がないとの指摘で、逆に中国を刺激するだけだという。現状の“米日同盟に勝る抑止力はない”と言っている。また日本への助言で“国民が清貧であることに耐えられるはずがない”と言うのだ。小さくともプラス成長を維持しながら、問題解決に全力を挙げることが良く、日本にとっての最大の問題は人口減少である、と言っている。
さて、最後にこの著者が取りとしたのがインド人アマルティア・セン教授だ。
セン教授は最初に仏教的考えと、十七条憲法の重要性を訴えている。十七条憲法は独断による判断を否定し、“皆で議論をした結果でなければならない”としている点を強調する。これは、“和を持って貴しとなす”の訳を言っているのだろうか。もしそうならば、日本では議論の前に“忖度”も介在した結果の“和”を強調していて、少し違う意味になっている。むしろ“皆で議論”は“和して同ぜず”という基本姿勢が重要で、違いを明らかにして、可能な限り“小異を捨てて、大同に付く”努力をするべきなのだが、“大人”の発想で始めから“違い”を隠した“なぁなぁ”の“和”が強調されるのが日本なのだ。しかし“違い”を明確化した上での“皆で議論”した結果を検討の上で得た結論を大切にするのは、サッチャー教授のモラルリーダーシップ論を想起させる点で、それは真理なのだろう。
日本で仏教が果たした役割は、経典の印刷技術の発達に寄与し、“知識”の重要性を日本人に教えたことだと言っている。これは、ラビンドラナート・タゴールが設立した学校での初等教育で学んだことだという。私は“知恵”が大切だと思っていたが、その“知恵”は“知識の集積”で得られたある結果なので、その前提となる“知識”は確かに大切なのだと気付かされる。
著者はセン教授が“経済学に人間性を取り入れた最初の学者”と持ち上げたが、同氏はアダム・スミスが最初だと即座に否定する。確かにスミスは、“国富論”以外に“道徳感情論”を著しているのは世界の常識だ。セン教授は、その要素はその誕生から経済学の中に存在すると指摘し、それが希薄化したことが問題だと言っている。確かに最近は心理学かとさえ思われる行動経済学が隆盛しつつあるのは事実だ。そして、強く影響を受けている日本の経済学者の名前を多数列挙する。その中には私も注目していた故・森嶋通夫の名前もあった。
そして、日本の識字率が高かったこと、公衆衛生を重視したことの重要性を訴える。特に、仏教国で識字率が高いことを指摘している。仏陀は“人間にとって大切なのは、一に知識、二に善い行い、三に信仰”とし、“知識の獲得は信仰より大切だ”としている。一方、キリスト教は信仰を第一にしている。だから仏教国の方が“知識の獲得に熱心”なのだという。
最後に著者の“日本の目標”の質問に、次のように応じている。“日本は日本だけではなく世界全体をよくする役割を担っていると思います。人々が、もっと快適で、もっと安全な人生を、もっと長く生きられるような世界にするにはどうしたら良いのか。それを日本は指し示して行くべきです。GDPの成長率を高めることよりも、目標とすべきことはたくさんある。”と言っている。これはナイ教授と真反対のことを言っているのではないと解釈するべきだ。ナイ教授は“善いことを為すには、先ず国民レベルで生活基盤をしっかりさせることが大切だ”と言っているだけと考えるべきだろう。だから“少しのプラス成長で良い”と言っているのだ。“衣食足りて礼節を知る”なのだ。
そして、“もし、世界に日本という国がなかったら・・・”?と著者の問いに対して“世界はより悲しい場所になっていたでしょう。世界に日本という国が存在してくれてよかった、と心から思います。”と言い放って終わっている。それでもどこから、そんな結論が出るのか、このインタビューからは分からなかった。
知の巨人たちでさえ、御世辞を言うのかと思わざるを得ない。しかし、日本が世界に果たした役割には、ある程度の善きものがあったのは事実だろう。それを素直に是認しながら、日本人であることに岡倉天心のように誇りを持つことは大切だが、夜郎自大では意味がない。そうならないためには、様々な目による評価とその結果の重層的知識を持っていることが必要なのだろう。やっぱり“実るほど首を垂れる稲穂かな”。そのためにはこの本は期待通りであった。
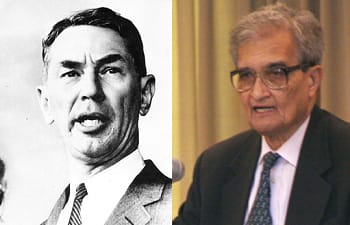
それにしても北の駆け引きは見事と言う外はない。板門店での首脳会談は韓国側の施設で行われるという。ヒョッとして、そこで北首脳の“亡命”もあり得るかもしれない。何でもアリを想定しておいた方が良いのではないか。そうなれば北の国家としての崩壊と、巨大な混乱となるだろう。何よりも、既にあるという核爆弾を確実に米側の管理下になるようにしなければ、日本をはじめ周辺国の大きな脅威になるだろう。
森友学園問題に絡んで財務省の記録改竄は、近畿財務局の担当者の自殺、当時の上司の国税庁長官の辞任、退職へと繋がってしまった。特に人命が失われたことは大きい。これは最高権力者御夫婦のなせる究極の結果であるにも関わらず、御当人たちには一向に響いていないように見受ける。この国の現実は忖度しても丸損。だが、これで一件落着とはいかないのではないか。どこまで進展するのか、当事者たちにも見えない、という。兎に角、この国は気真面目な人間ほど生き難い。それで良い国と言えるのか。
女子レスリングのパワー・ハラスメント問題は、騒ぎの素となった小ボスは“体調不良”だという。レスリングの指導者がこの程度のことで“体調不良”だとは、何だか軟弱な印象。ここへ来て“弱さ”を装って幕引きを期待しているのか。どことなく情けなさが漂う。
この国のボスどもの人としての小ささに、情けなさばかりが目立つ。どうして小粒の人間ばかりを指導者としてあがめ、その小粒の人間に汲々として忖度し、結果、犠牲となる、その連鎖は果たして正しいのか。
さて、こうしたこの国の情けない実態を世界はどう見ているのか気になるところだが、ブログ投稿ネタに困っていた時、書店書棚で、偶然にもこの本が目に入った。帯に“なぜ世界最高の知性は日本史から学ぶのか”とあった。表題は“ハーバード日本史教室”とある。単に、こういう類の表題の本を見ると日本の実態を正確に把握した上でのことだろうか、何か誤解があるのではないかと、読んでもその時間が無駄!と思ってしまい手にすることもはばかっていた。しかし、今回は目次を見て、結構 魅力的な印象を持ってしまった。そのまま書店の棚に一旦戻し、店内他所を暫くウロウロして、この本以上に読みたくなる本は見当たらず、やっぱり戻って購入することにした。
この本は、日本研究者である現役のハーバード大学教授に、日本の現状の問題点を中心にインタビューした記録である。著者は1970年兵庫県生まれ、92年東京大学教養学部(国際関係論)卒業。作家、コンサルタント、とある。兵庫県ということから高校はどこだろうか、少々気になるがネットでは分からなかった。
その著書の表題には“MBA”や“ハーバード”や“スタンフォード”の文言が目立つ。特に最近は“ハーバード”が目立つようで、一時流行った“白熱教室”の波に乗ろうとしたのだろうか。
とは言うものの、やはりこの本の構成は微妙に上手くできているように感じる。つまり、実際のインタビューの順序は分からないが、食いつきの良いテーマの研究者から始まり、著者の目玉とする研究者を最終のトリに配したのではなかろうか。中には聞いたことのある名の研究者も居るが、浅学にしてほとんどは私は知らない。そのトリのアマルティア・セン氏も私は知らなかったが、調べてみると日本語による著書・講演集も結構あるようなので、今後読んでみたいと思っている。
目次は次の通りだ。
第1講義 教養としての『源氏物語』と城山三郎―日本通史 アンドルー・ゴードン
第2講義 『忠臣蔵』に共感する学生たち―江戸時代 デビッド・ハウエル
第3講義 龍馬、西郷は「脇役」、木戸、大久保こそ「主役」―明治維新 アルバート・クレイグ
第4講義 ハーバードの教授が涙する被災地の物語―環境史 イアン・ジャレッド・ミラー
第5講義 格差を広げないサムライ資本主義―アジア研究 エズラ・ヴォーゲル
第6講義 渋沢栄一ならトランプにこう忠告する―経営史 ジェフリー・ジョーンズ
第7講義 昭和天皇のモラルリーダーシップ―リーダー論 サンドラ・サッチャー
第8講義 築地市場から見えてくる日本の強みと弱み―和食の歴史 テオドル・ベスター
第9講義 日本は核武装すべきか―日米関係史 ジョセフ・ナイ
第10講義 世界に日本という国があってよかった―経済学 アマルティア・セン
“日本人がはじめてハーバードに留学したのは1872年。”金子堅太郎だという。この金子はその後ハーバード同窓のセオドア・ルーズベルトと意気投合し、日露戦争終結の仲介を当時の米大統領だったルーズベルトに依頼し、ポーツマス条約を日本に有利に締結することを可能にしたという。ポーツマス条約の日本全権大使の小村寿太郎もまた官費によるハーバード留学生だったという。その後は、松下乙彦や山本五十六が、ハーバード卒で個人的にも日米親善に努めたようだが結果として、上手く行かなかった。
2017年現在約100人の日本人学生がいるが、中国からは約900人、韓国からは約300人だという。この日本人の数では、講義で日本の立場を代弁する学生がいないので、多くの教授が残念がっているという。
ハーバードでは1973年にエドウィン・O・ライシャワーの尽力で日本研究所が設立されたという。このライシャワーは日本で生まれ育ち、第2次世界大戦では米政府で対日情報戦に従事後、ハーバード大学教員となり日本研究者として要職を歴任、1961年から年間は駐日大使も務めた。1964年に当時19歳の統合失調症患者にナイフで大腿を刺され重傷を負い、この時の輸血で肝炎に罹患、その後持病となった肝炎が1990年に悪化し、自ら延命治療を拒否し79歳で死亡。遺灰は、「日本とアメリカの架け橋になりたい」との遺言により太平洋に撒かれた。
ライシャワーにより、日本研究所設立の“追い風となったのは当時の田中角栄政権がアメリカにおける日本研究を支援する方針”だったことによるという。国際交流基金を通じて、ハーバード等日本研究プログラムを持つ10の大学に総額1000万ドル(当時のレートで約30億円)という通称“タナカ・テン”を提供したのが契機だったという。
この本で示されたのは、このように長年培われた研究の成果だといってよいのだろう。国際的な知の巨人達の日本観は一体どうなのだろうか、これに興味が持てないとは、余程日本という国に関心のない人物ではないだろうか。だからこの本が気になったのだ。しかも今のこの瞬間だけの日本ではなく、全般に歴史的に見て日本を評価するという研究姿勢で“日本史教室”となったのだろう。
アンドルー・ゴードン教授とデビッド・ハウエル教授は“アジアの中の日本、世界の中の日本”という授業を持ち、約3カ月で日本の通史、つまり6週間で縄文から江戸時代まで、7週間で明治からの近現代史をするという。特にゴードン教授は“(日本と)世界との関連性を含めて捉え、日本史を「支配者の政治史」だけでなく、社会史、経済史、文化史を含めた重層的に語る”ことを心掛けているという。そんな本があれば読んでみたい気がする。どうやら“日本の200年― 徳川時代から現代まで(上・下)”という著書があるようだ。
ゴードン教授は教材に“源氏物語”、“今昔物語集”、“方丈記”、“放屁論(平賀源内)”、“北越雪譜(鈴木牧之)”、大塩平八郎の檄文を使うという。ちなみに、“源氏物語”は女子学生の共感を得てはいないが、エリート層には良く知られているので、“日本人の教養”として必読ではないかと著者は警告する。
また、“チョコレートと兵隊”(1938年・佐藤武監督)の邦画も教材にし、多くの学生が感動するという。当時の国策映画で巧妙なプロパガンダで、そのメッセージは“どんな困難なことがあっても、一致団結して耐え抜こう”という“国民の団結を静かに訴えている”ということに感動するというのだ。そういえば前にこのブログで紹介した“陸軍”(1944年・木下惠介監督)という戦前の映画も何か内に秘めた感動的なラスト・シーンがあった。
またゴードン教授は、岡倉天心の次のようなエピソードを授業で紹介しているという。天心はアメリカに居る時は日本の着物を着て、日本では洋服を着ていたそうで、アメリカで闊歩していると、地元のアメリカ人から“お前たちは何ニーズ?チャイニーズ?ジャパニーズ?ジャワニーズ?”と聞かれて、天心は“私たちは日本の紳士。あなたこそ何キー?ヤンキー?ドンキー?モンキー?”(ドンキーはノロマ・バカの意がある)と流暢な英語でやり返した。ここから、当時のアメリカ人の人種差別意識と、それに対照的な天心の日本人としての誇りを失わなかったこと、そして冷やかしを英語のジョークで即座に返した機転に感心する、という。
デビッド・ハウエル教授は、通史で縄文から江戸時代までを担当。日本の武士で幕末の大名・須坂藩(1万石)の堀直虎に興味があるという。幕府からは外様にもかかわらず、譜代と同様の扱いをうけた、国際派の大名だったという。自らを“ストレート・タイガー(直虎)”と呼び、大名になると藩政改革を断行し反対派を大量粛清し借金を返済、洋式軍制を導入したという。鳥羽伏見の戦いで幕軍が敗走後、江戸に逃げ帰った慶喜に若年寄りの直虎は何かを進言し、直後に切腹してしまう。33歳だったという。“(国際派でありながら武士としての責務を全うしたという、)新しさと伝統が共存しているところに魅かれる”という。学生には直虎の写真を見せて教えるという。
ハウエル教授は“忠臣蔵(赤穂事件)”も教えているが、“大義のためにすべてを犠牲にする”という姿は、日本人だけの考え方ではなく普遍的で、多くの学生が共感するという。
室町時代に津軽半島にある十三湖のほとりに広がっていた港湾都市・十三湊も授業で紹介するという。14世紀から15世紀にかけて東日本の巨大な国際貿易センターだったという。そこを統治していた安東氏が南部氏との戦いに敗れて後、十三湊も急速に衰退し壊滅したという。
普通の日本人が知らないエピソード満載だ。一般に教えられている通史すら、偏っているのかも知れない、と思わざるをえない。自らの歴史すら十分に知ったつもりになっていて、実は良く知ってはいないのではないか。外国人がどうしてこのように埋もれた歴史を発掘できるのだろうか。又ここまで来るだけで既に目一杯になってしまう気にさせられた。
そして、“日本人は明治のリーダーのように、もっとコスモポリタンになってほしい。”と忠告する。要は、客観的に自分を見つめ、異なる考えも乗り越えてお互いを利する関係をもつことで学び合えるからだという。
“ジャパン・アズ・ナンバー・ワン”のエズラ・ヴォーゲル教授の名前は日本人には良く知られている。しかし、私はその本を読んではいない。この本、アメリカの一般人にはあまり読まれなかったらしい。だがエリート層には知られていて、日本の産業研究の端緒になったようだ。日本以外では東南アジアで読まれたそうだ。マレーシアの当時のマハティール首相にも大きく影響したようだ。中国では後に首相になる朱鎔基も読んでいたらしい。
同氏も格差拡大を懸念している。トランプ大統領は長続きしないとも言明。この本に登場する教授たちはほぼ同じ立場の様だ。経営史のジェフリー・ジョーンズ教授も渋沢栄一に仮託して、トランプに“世界からリベラル資本主義が失われている”と忠告するするだろうと指摘している。
日本には米国や中国と違い“フェア・シェア”という基本原理が江戸時代から醸成されてきたというのが、ヴォーゲル教授の結論のようだ。つまり日本では権力者が利益を独占しないという原理だが、最近の日本の指導者のメンタルは残念ながら序文で述べたように大きく変化しているのが現実ではないだろうか。どうして、そうなったのだろうか。
サンドラ・サッチャー教授は、モラルリーダーシップ論を教える。これは、1980年代から教えられている選択科目だが、これほど長続きしている科目は珍しいという。目的は人道主義的な立場から戦争を考えること。そのために開戦の決断には“道徳的に十分な根拠があること”、二つ目に自らの決断の正当性を検討・評価する正しいプロセスを持っていること、だという。
現在、米軍では“トップは他の隊員からの意見を聞くことなく、最終決断を下してはならない”という。意見を聞いた上で“隊長は少なくとも三つの代替案を検討した上で最終決断を下す”という。さらにその最終決断では“軍事専門弁護士が戦時法規の観点から深く関わっていること”になっている。同じ文化の中の部下の意見を聞くよりも、戦時法規が歯止めになっているというのは重要で、これは良いことかもしれない。
こうした観点からトルーマンの原爆投下の決断は正しかったのかの議論が授業でなされるのだという。そこからトルーマンの決断の甘さが見えて来ているということだ。
昭和天皇の“終戦の詔勅”をその授業で必ず取り上げるという。学生は昭和天皇の決断に共感をもつという。“負けた側のリーダーの行為の背景には、どんな目的があり、意味があり、動機があったのか。そこからモラルリーダーシップを学べることは多々ある。・・・昭和天皇の行動はまさにモラルリーダーシップを実践している”とサッチャー教授は評価している。
しかし、授業では昭和天皇の開戦の決意についての議論はないようだ。日本史ではそれを間違えなかったことの方が重要なのだが・・・実際は天皇は部下の将軍たちに意見を求めたという。さて果たしてその時、戦時法規に対してどうだったのか、興味あるところだ。その結果としての天皇の戦争責任が語られるべきなのかも知れない。
ジョセフ・ナイ教授は国際安全保障の専門家と思っていたが、ここではその議論は少ない。この本でナイ教授に割かれた分量も少ない。やっぱりナイ教授は日本の核武装には否定的である。やっても安全保障としては効果がないとの指摘で、逆に中国を刺激するだけだという。現状の“米日同盟に勝る抑止力はない”と言っている。また日本への助言で“国民が清貧であることに耐えられるはずがない”と言うのだ。小さくともプラス成長を維持しながら、問題解決に全力を挙げることが良く、日本にとっての最大の問題は人口減少である、と言っている。
さて、最後にこの著者が取りとしたのがインド人アマルティア・セン教授だ。
セン教授は最初に仏教的考えと、十七条憲法の重要性を訴えている。十七条憲法は独断による判断を否定し、“皆で議論をした結果でなければならない”としている点を強調する。これは、“和を持って貴しとなす”の訳を言っているのだろうか。もしそうならば、日本では議論の前に“忖度”も介在した結果の“和”を強調していて、少し違う意味になっている。むしろ“皆で議論”は“和して同ぜず”という基本姿勢が重要で、違いを明らかにして、可能な限り“小異を捨てて、大同に付く”努力をするべきなのだが、“大人”の発想で始めから“違い”を隠した“なぁなぁ”の“和”が強調されるのが日本なのだ。しかし“違い”を明確化した上での“皆で議論”した結果を検討の上で得た結論を大切にするのは、サッチャー教授のモラルリーダーシップ論を想起させる点で、それは真理なのだろう。
日本で仏教が果たした役割は、経典の印刷技術の発達に寄与し、“知識”の重要性を日本人に教えたことだと言っている。これは、ラビンドラナート・タゴールが設立した学校での初等教育で学んだことだという。私は“知恵”が大切だと思っていたが、その“知恵”は“知識の集積”で得られたある結果なので、その前提となる“知識”は確かに大切なのだと気付かされる。
著者はセン教授が“経済学に人間性を取り入れた最初の学者”と持ち上げたが、同氏はアダム・スミスが最初だと即座に否定する。確かにスミスは、“国富論”以外に“道徳感情論”を著しているのは世界の常識だ。セン教授は、その要素はその誕生から経済学の中に存在すると指摘し、それが希薄化したことが問題だと言っている。確かに最近は心理学かとさえ思われる行動経済学が隆盛しつつあるのは事実だ。そして、強く影響を受けている日本の経済学者の名前を多数列挙する。その中には私も注目していた故・森嶋通夫の名前もあった。
そして、日本の識字率が高かったこと、公衆衛生を重視したことの重要性を訴える。特に、仏教国で識字率が高いことを指摘している。仏陀は“人間にとって大切なのは、一に知識、二に善い行い、三に信仰”とし、“知識の獲得は信仰より大切だ”としている。一方、キリスト教は信仰を第一にしている。だから仏教国の方が“知識の獲得に熱心”なのだという。
最後に著者の“日本の目標”の質問に、次のように応じている。“日本は日本だけではなく世界全体をよくする役割を担っていると思います。人々が、もっと快適で、もっと安全な人生を、もっと長く生きられるような世界にするにはどうしたら良いのか。それを日本は指し示して行くべきです。GDPの成長率を高めることよりも、目標とすべきことはたくさんある。”と言っている。これはナイ教授と真反対のことを言っているのではないと解釈するべきだ。ナイ教授は“善いことを為すには、先ず国民レベルで生活基盤をしっかりさせることが大切だ”と言っているだけと考えるべきだろう。だから“少しのプラス成長で良い”と言っているのだ。“衣食足りて礼節を知る”なのだ。
そして、“もし、世界に日本という国がなかったら・・・”?と著者の問いに対して“世界はより悲しい場所になっていたでしょう。世界に日本という国が存在してくれてよかった、と心から思います。”と言い放って終わっている。それでもどこから、そんな結論が出るのか、このインタビューからは分からなかった。
知の巨人たちでさえ、御世辞を言うのかと思わざるを得ない。しかし、日本が世界に果たした役割には、ある程度の善きものがあったのは事実だろう。それを素直に是認しながら、日本人であることに岡倉天心のように誇りを持つことは大切だが、夜郎自大では意味がない。そうならないためには、様々な目による評価とその結果の重層的知識を持っていることが必要なのだろう。やっぱり“実るほど首を垂れる稲穂かな”。そのためにはこの本は期待通りであった。
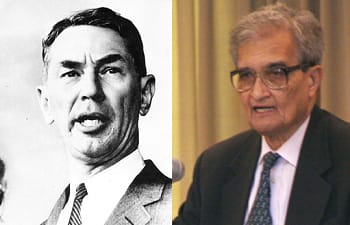
コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « 香田洋二・著“... | 古代京都観光... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |





