The Rest Room of ISO Management
ISO休戦
“ISOを活かす―70. ISOでは、ルールは変更した方がい?”
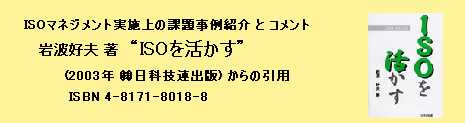
今回は、ルール変更のあり方についてがテーマです。
【組織の問題点】
コンピュータ・ソフト・ウェア会社のA社での内部監査の指摘事項で、“品質マニュアルどおりに仕事を行っていない”というものがありました。これは、企画部の担当者は、品質マニュアルどおりに仕事をおこなうと効率がよくないため、自分で工夫していたためだったのです。
しかし、内部監査員は 当然 品質マニュアルどおりに仕事はするべきであると、譲らないとのこと。
ISOでは ルールや品質マニュアルの変更についてどのように考えるべきか、という課題です。
【磯野及泉のコメント】
組織活動において、ルールを順守することは重要です。組織に従事する人々は全て定められた手順に従ったシステムの中で活動しているからです。個人の勝手な判断で仕事をされると 次のプロセスの担当者が困る場合が出てくるのです。これは、組織活動の混乱の原因となります。
またルールは 過去の失敗の経験を踏まえていることも多く 一見無駄に見える行為も意味のある行為であるため手順として無視できないのです。いわば、組織の知恵・知識の集大成である場合が多いのです。
この事例では “品質マニュアルどおりに仕事を行っていない”ことで、次のプロセスに悪影響を与えている様子はないように見受けますが、それでも ルールを順守する(品質マニュアルどおりに仕事をする)ことは重要です。それは、“ルールを順守しないこと”が 組織が機能しなくなる 小さな原因となるからです。
通常の感覚では これぐらい 良いじゃないか、と考える傾向にありますが、どこかでユルミが生じますと これがあらゆる局面に伝播し、組織活動がガタガタになるのです。これが いわゆる“躾”の部分だと思います。
“決めたことは 必ず守る”習慣は 組織運営の基礎であり、非常に大切です。
では この事例のようにルール(品質マニュアルの規定)が 不合理であった場合はどうするべきか、というのが 今回のテーマなのですが、その場合は 所定の手続きを経て、ルールを変更するのが 普通のやり方になります。
また ルールは ここでは品質マニュアルに規定され、文書化されています。このように ルールは文書化され、客観化されているのが普通のやり方です。なぜならば、ルールは人によって異なると組織混乱の素になるからです。組織や手順が複雑化している現代では ルールは必ず文書化されています。
従って、ルール改訂の所定の手続きはISO9001 4.2.3に規定された手順によることになります。

この4.2.3が 組織の要員が自然に順守するようになっていないといけません。これは品質マニュアルに限らず、品質にかかわるルールを定めた品質文書すべてについて言えることです。
4.2.3の文書のレビューなどの所定の手順を順守している余裕がなく 即座に現場で対応できない場合には 別途 臨時の指示文書の体系を作っておくという便法をルール化(文書化)しておくべきです。これは、組織が大きくなり 様々な責任と権限の所有者が錯綜している場合などに有効です。
また、こうした臨時の指示文書によって、工程条件などの変更の工程実験をして その条件変更結果の確立・確認をしてから、恒常的なルール化(品質文書化)するというやり方に応用も可能です。改善提案の内容を 実験的に確認するのも この手順を適用すると良いでしょう。
世の中の進歩・変化は 多様で 早いのでこうした 変更・確認が、多数実施されていることは、ある意味組織の活性状態のバロメータと見ることもできます。
この観点で、品質マニュアルの改訂件数と、改訂内容に着目するISO9001審査員は多いのです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )
| « サミットと原... | コラム記事“「... » |
| コメント |
| コメントはありません。 |
| コメントを投稿する |





